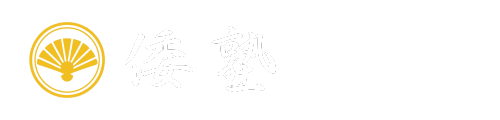戦後の世界を覆う混乱の根は、実は五百年にわたる人類の「罪悪感」にあるのかもしれません。
植民地支配と人種差別、その果てに訪れた価値の逆転。
過去を直視できなかった痛みが、いまも理想や正義の名のもとに暴走を生み出している。
東郷潤先生との対談を通じて、人類史の深層を探ります。
Ⅰ.「日本を抑え込めば平和になる」という幻想
戦後の世界秩序は、日本やドイツを「敵国」として位置づけたまま再構成されました。
しかしその後も、戦争は絶えることがありませんでした。
朝鮮戦争、ベトナム戦争、アルジェリア、アフガニスタン、湾岸・イラク、ウクライナ、中東紛争・・・いずれも、敗戦国である日本やドイツが直接の当事者ではないにもかかわらず、世界の火種は消えることがなかったのです。
この現実は、
「日本を抑え込めば平和になる」
「過去の悪を糾弾すれば世界が浄化される」
という発想が幻想であったことを示しています。
戦後の“平和”は、実は支配と懲罰の論理を温存したままの延長線上に築かれてきたのです。
Ⅱ.五百年の悪業──植民地支配の後遺症と罪悪感
東郷先生は、現代の混乱を「五百年の悪業」として捉えます。
ヨーロッパ列強による植民地支配は、広大な領土と富を奪うと同時に、現地の民族や文化を分断しました。
人種差別、搾取、宗教的支配、そして「文明化の使命」と称された暴力。
この過去を直視することは、加害者側にとってあまりにも重いものでした。
そのため、多くの人々は無意識のうちに罪悪感から逃避しようとしました。
その逃避の形が、今日の過剰な理想主義や偽善的な人道主義、暴力による正義の演出などとして現れています。
つまり、罪悪感の処理不全が、社会的行動の過剰化を生み出しているのです。
自分たちの歴史的非道を直視できないまま「善の側」に立とうとする心理。
これが、過剰なモラリズムや「人権」を名目とした価値観の押しつけを生み、他者を支配するための新たな装置となってしまっているのです。
罪の意識が強いほど、人は自らの「正義」を誇示しなければ心の均衡を保てなくなるのです。
Ⅲ.脱・二元論へ――人間観の回復こそ未来への道
東郷先生が強調するのは、「善と悪」「加害者と被害者」という二元的な思考からの脱却です。
現代社会に蔓延する分断と対立は、この二元論的思考の産物にほかなりません。
善悪のどちらか一方に自分を置こうとする限り、人間は常に誰かを「悪」として排除し続けてしまいます。
必要なのは、過去の誤りを否定ではなく理解へと変えることです。
そして、自他の痛みを引き受けながら、行為そのものの責任で語り合う成熟した人間観。
そこから初めて、真の対話と共生が生まれます。
日本が戦後の焼け跡から歩んできた道は、まさにその「脱・二元論」の実践でした。
報復でも、怨念でもなく、誠実な履行と努力によって世界から信頼を得た。
その歩みは、これからの世界が進むべき「共鳴と再生」の道を示しています。
【所感】
今回の東郷先生のお話は、まさに貴重なものでした。
先生が語られた「五百年の悪業」と「罪悪感の逃避」は、決して遠い世界の話ではありません。
それは、いまこの瞬間の私たちにも突きつけられている課題です。
もちろん、日本が他国を蹂躙したり、虐殺や支配を繰り返した歴史はありません。
けれど、日本国内では戦後の混乱期に、暴力や不正によって富や地位を得た人々がいたことも事実です。
その行為は、当人たちの心に深い罪悪感を刻みました。
しかし、それを認めればすべてを失うという恐怖がある。
そのため、代わりに過剰な正義感、過剰な理想主義、国家や自己への過剰な否定に走ってしまう。
そうした心の揺れが、いまなお街頭での過激な妨害行為や、極端な政治的対立として噴き出しています。
過剰化が生むのは、「対話の断絶」です。
人が罪悪感を受け入れず、他者に投影し続ける限り、社会は冷静な協調を失います。
必要なのは、罪を糾弾することではなく、行為で責任を取り、制度で冷却し、言葉で理解を深めることです。
善悪の二元を超えたその先に、人間としての成熟と、ほんとうの「共鳴文明」への道が開けます。
その意味で、戦後の混乱の中で生まれた人々を憎む気持ちはありません。
大切なのは、そうした出来事を日本という国が与えられた試練と捉え、その試練を乗り越えてきた歩みに誇りを持つことです。
対立よりも調和を、
恐怖よりも信頼を、
支配ではなく共創を、
孤立ではなく共鳴を。
この道こそ、新しい日本、そして新しい文明を切り拓いていく道だと確信しています。