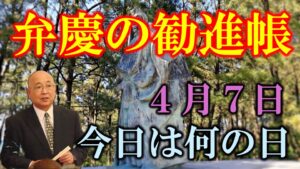百人一首第25番の歌に込められた「男の誠実」を通じて、日本古来の公に尽くす美徳を解き明かします。逢いたい想いを胸に秘め、私欲を抑えた右大臣・藤原定方の歌に、日本人の精神が映し出されています。
◉ 藤原定方の恋心と葛の蔓が語るもの
百人一首25番の歌「名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな」は、一見すると秘めた恋を詠んだ恋歌のように見えます。しかし、歌人の名前があえて「三条右大臣」と表記されていることからも、この歌が単なる恋愛歌でないことは明白です。
逢坂山の「逢う」、さねかづらの「さね(小寝)」、「かづら(葛)」、そして「くる(来る・繰る)」など、歌の中には複数の掛詞が込められており、逢いたい想いと身体的な情熱の両面が巧みに表現されています。それだけに、この歌はただの密かな恋ではなく、深い情愛を秘めた、切実な思いが綴られていることがわかります。
葛は、急傾斜でも力強く繁茂する植物であり、その生命力は藤原定方の情熱にも重なります。相手の女性への想いがどれほど強かったかが伝わる一方で、「くるよしもがな」という願望表現にとどまっている点が、この歌に重要な意味を与えています。
◉ 「公」を守る覚悟──右大臣の選択
当時の通い婚制度においては、男性が女性のもとに通うのが習わしでした。しかし、右大臣という国家の重責を担う立場にあった藤原定方には、それすらも自由にはできません。自分の想いに従えば、私欲を優先した行為となり、国家に仕える立場として失格です。
日本では、政治権力者は支配者ではなく、天皇から「おほみたから(大御宝)」を預かる者であり、その民を支えるのが役目とされます。だからこそ、民を支配対象とする諸外国の価値観とは大きく異なり、権力者であっても勝手に欲望を満たすことは許されません。
定方が女性への強い想いを抱きながらも、「人に知られで来るよしもがな」と詠むにとどめたのは、「公人」としての責務を果たす覚悟の現れです。その姿に、日本的なリーダー像、公に尽くす者のあるべき姿を見ることができます。
◉ 日本人が守ってきた「誠」と「道徳」の伝統
この歌が伝えるのは、「誠実さ」と「私欲を抑える覚悟」、そして「民を守る公人としての矜持」です。日本では、たとえ誰も見ていなくても「お天道様が見ている」という感覚が道徳の基盤であり、上に立つ者ほど自己を律することが求められてきました。
儒教が支配する中国や韓国では「諱(い)」という、上の者を庇うために嘘をつく思想が重視されましたが、日本はそれを受け入れませんでした。つまり、日本には古来より、自らの責任と正しさを貫く文化が存在し、それが「誠実な男の美学」として歌にも表れています。
私情に流されることなく、恋心さえも「もがな」と願望にとどめる姿に、日本の「公」の精神を見ることができます。そしてその姿は、今を生きる私たちにも通じる普遍的な価値を語りかけてくれます。