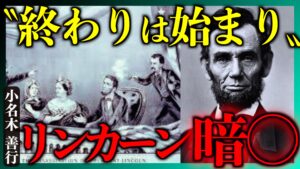今回は縄文時代から続く「勾玉」についてお話ししました。祖先の証として争いを防ぎ、人々をつないできた勾玉は、日本人の「思いやり」や「助け合い」の文化の象徴であると感じています。歴史を通じてその意味を考えました。
◉ 勾玉の起源と伝播、そして歴史観のねじれ
今回のテーマは「勾玉(まがたま)」です。この不思議な形の装身具は、日本国内では1万年以上前の縄文遺跡からも出土しています。ところが現在の歴史学界では「朝鮮半島起源」とされ、6世紀の仏教伝来と共に日本へ伝わったという主張がなされています。
しかし、実際には日本の方が圧倒的に古い出土例を持っており、3000年前の朝鮮半島の勾玉が、なぜか1万年前の日本の勾玉より「古い」とされている。このような矛盾した解釈の背景には、近隣諸国条項による“配慮”があり、歴史がゆがめられている現状を考えさせられます。
◉ 勾玉が果たした「親戚の証」としての役割
私が十数年前に聞いた話によると、勾玉は単なる装飾品ではなく「祖先からの証」として村々をつなぐ役割を果たしていたという説があります。
かつて日本では上方様(うわかたさま)と呼ばれる王族が、末子相続制のもとで全国へ子孫を分散させていたとされます。子や孫が新天地に旅立つ際には、親から「勾玉」を授かり、それを家宝として大切に守っていたそうです。
そして時を経て、別々に発展した村同士がぶつかりそうになったとき、互いに勾玉を見せ合って「親戚である」と確認し合うことで、戦争を回避し、酒を酌み交わして和解に至った――そんな物語が語り継がれているのです。
この話は記録に残っているわけではありませんが、縄文時代に戦争の痕跡がほとんどないことからも、実際にそのようなことがあったのかもしれないと感じています。
◉ 勾玉に象徴される日本人の心と歴史の学び方
翡翠などの硬い素材でつくられる勾玉は、1つ完成させるのに数年かかるほどの手間がかかります。その分、深い想いと時間が込められており、それが「命を守るお守り」としての意味を持っていたのだと思います。
日本の人口が少なかった縄文時代において、私たち日本人はみな祖先をどこかで共有している――すなわち、私たちは皆「親戚」なのです。そのつながりを思い出させ、争いを避けるための知恵として、勾玉が使われてきたのではないでしょうか。
災害時に略奪が起こる国もある中、日本では助け合い・譲り合いの精神が自然と発揮されます。その精神は歴史や文化の中に息づいており、まさに「勾玉」がその象徴のように思えてなりません。
歴史や神話を学ぶ際に、現代の感覚で批判するのではなく、謙虚に「何を学ぶか」という姿勢が大切です。過去を学ぶことで、未来をつくる知恵や勇気を得ることができる――そのような学びを、私は大切にしたいと思っています。
⸻
引き続き、歴史や神話の中にある“日本人の心”を皆様と共に探ってまいります。
次回もどうぞよろしくお願いいたします😊