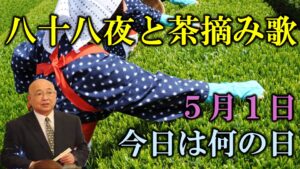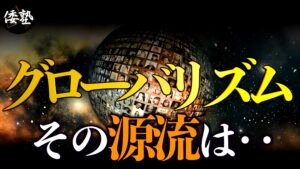世界まぐろデーの由来から、回遊魚の象徴「鮪」の語源を紹介。そして、日本語と酷似する構造を持つバスク語や、2018年に終焉した独立運動を通じて、国家・文化・言語の本質を考察します。
◉ 世界マグロデーと「鮪」の漢字に込められた意味
5月2日は「世界マグロデー(World Tuna Day)」として国連により制定されています。世界的に人気の高いマグロですが、実は個体数が少なく、乱獲の危機に晒されている魚でもあります。特に日本ではマグロの稚魚を守る伝統がある一方、海外ではそうした配慮が少ない現状があります。
マグロは常に泳ぎ続けないと酸欠になるという生態から、漢字では「魚へんに有」と書いて「鮪」となります。これは「どこにでも有る魚=回遊魚」としての特徴が示されているのです。この漢字ひとつからも、自然と共に生きるという日本人の感性が垣間見えます。
◉ バスク人と日本人──言語と文化の不思議な近縁性
今日の本題は、2018年に終焉を迎えた「バスク人の独立運動」についてです。スペインとフランスの国境地帯に広がるバスク地方は、古来より独自の文化と言語を守り続けてきた地域。特に「バスク語」は印欧語族に属さないヨーロッパ唯一の孤立言語で、語順や構造が日本語と驚くほど近いことで知られています。
司馬遼太郎氏が紹介した有名な小話──「悪魔でさえ3年間バスク語を学ばされると神に許しを乞うた」──に象徴されるように、非常に習得が難しい言語です。実際に「はい(Bai)」と「いいえ(Ez)」すら覚えられなかったというジョークも残されています。
また、ベレー帽を民族衣装の一部とするなど、独特の文化をもつバスク人たちは、長年スペイン・フランス両国に抵抗し独立を求め続けてきました。その運動は2018年、「バスク祖国と自由(ETA)」の解散によって事実上の終焉を迎えます。
日本に伝道したフランシスコ・ザビエルも、実はバスク人。彼が感じた“日本との相性の良さ”は、文化や精神性の共通点から来ていたのかもしれません。
◉ 歴史の中の「5月2日」──枢密院の廃止と尊皇の系譜
5月2日は、歴史的にも意味深い日です。1947年には、明治憲法体制のもとで天皇の諮問機関として設置された「枢密院」が廃止されました。これは翌日(5月3日)の新憲法施行にともなう体制転換の一環でした。もしこの機関が戦前に機能していれば、開戦を阻止できた可能性もあったかもしれません。
さらに、1948年の同日には講道館で第1回全日本柔道選手権大会が開催されました。GHQの統制下にあった日本で、柔道が「競技」として再認識されるきっかけとなった重要な出来事です。
また、1864年(元治元年)には、筑波山で藤田小四郎らによる「天狗党の乱」が勃発。この尊皇攘夷運動は、水戸藩の学問「水戸学」を背景に、日本の独立と伝統を守ろうとする志に支えられていました。
◉ 日本の未来に重ねて──“民族文化の消滅”をどう防ぐか
現在の日本も、ある意味で「静かな分断」や「文化の希釈化」が進んでいます。バスク人が人口100万人を切り、スペイン語・フランス語との同化が進むように、日本人もまたアイデンティティを問われる時代に差し掛かっています。
外国人の大量受け入れや政治的な無策により、「日本人としての魂」が損なわれる未来が現実味を帯びてきています。言語、文化、歴史の全てを他人任せにしていては、次の世代に受け継ぐべき“何か”が消えてしまう──。そんな危機感を、今日のテーマは静かに投げかけてくれます。
ザビエルをはじめとする“魂でつながる縁”に目を向けつつ、私たちは「民衆こそが国家の根幹である」という日本的精神を改めて見つめ直すべき時なのかもしれません。