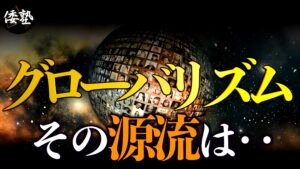執行草舟氏と小名木善行が、日本文明の核心を語り合います。縄文以来の「肚の文化」や、夫婦・母性の尊さ、直立不動の敬意に宿る日本人の誇りと精神を深掘りします。
◉ 縄文の魂と「肚の文化」──日本人の根底にある感性
今回の対談は、執行社長が「小名木善行は日本国家の宝である」と、たいへん恐縮なお言葉から始まりました。
歴史好きであった執行社長は、多くの歴史書を読んできたものの、どうしても腑に落ちない点が多くありました。それが、小名木の講義を通じて根底から「つながり」始めたと語られます。
特に感銘を受けたのが「縄文文明」に対する独自の捉え方で、これは単なる古代史ではなく、日本人の精神文化の源流を現代に引き戻す鍵だとされています。
「肚(はら)の文化」とは、知識ではなく感得、理屈ではなく実感によって語られる生き方であり、執行社長は小名木の語りにその「肚の力」を強く感じたと語ります。
頭で理解する西洋的思考とは異なり、日本には「肚で感じて決める」という文化が縄文以来連綿と続いています。
戦後の日本が西洋式の「頭脳教育」に傾いた結果、登校拒否や心の病が増えていると執行社長は指摘します。
しかし、これはむしろ日本人の深層にある「肚」が、頭の教育に拒否反応を示している結果であり、教育に適応できない子どもたちは「正常」なのだと捉えるべきだと述べられました。
学校で要領よく過ごしている子どもよりも、不器用で悩んでいる子のほうが、もしかしたらよほど「真っ当」なのかもしれないという見解も示されました。
このような「肚の文化」こそが、今こそ再発見されるべき日本の文明の中核であり、それを感じ、受け継ぎ、語れる人材こそが、これからの社会を支える真の知性です。
◉ 夫婦・親子・家族──日本人の「関係性」に宿る道徳観
対談のもう一つの柱となるのが、「家族」「夫婦」「親子」といった人間関係に潜む日本的価値観です。
執行社長は、「夫婦は必ず前世からの縁である」という考えを紹介し、戦後に崩れてしまった夫婦観を憂えます。
かつての日本では、喧嘩をしても添い遂げるのが夫婦であり、「墓は一緒」ということが当たり前でした。
これは合理的な制度ではなく、深い精神文化に基づいた生き方でした。
象徴的なのが、田中角栄元首相が総理大臣在任中に母親から電話がかかってきた際、直立不動で応じたというエピソードです。
さらには、執行社長自身の若き日、三崎港で悪漢政という字も読めない伝説の漁業親分であり大社長が、明治天皇の話を聞いて直立不動になった場面も紹介されます。社会的地位や教養ではなく、「敬意によって人間の価値が測られていた」時代の空気がそこにあります。
財産や地位に関係なく、年長者を敬うという価値観が、古代日本ではすでに定着していたのです。
現代では「愛している」と言葉にすることが尊ばれがちですが、かつての日本では「言葉にならない思い」こそが本物の愛と考えられていました。
表現されずとも、通じ合っていた、その精神性は、失われたのではなく、今なお多くの日本人の深層に眠っているのではないかと、執行社長は問いかけられます。
◉ 女性の潜在意識と母性愛──文明再生の核心は「女性」
さらに話題は、「女性」の本質的な役割と力へと進みます。
執行社長は、自身の母親の記憶を語ります。幼少期の些細な出来事や失敗をすべて覚えている母の姿から、「愛とは、すべてを記憶する力である」と語られます。
母親が持っていた記憶は、単なる能力ではなく「愛の深さ」の表れです。
家庭という小さな共同体の精神的支柱は、常に女性だったのです。
戦前の女性たちは、自らの幸せを家族に重ね合わせ、自分を差し出すことに誇りを持っていました。
それは決して「差別」などではなく、「与えることが幸福である」という日本的美徳の実践でした。
現代ではこうした生き方が見失われがちですが、かつての日本ではそれが普通であり、社会の安定を支えていたのです。
また、「渚のバルコニー」の歌詞解釈について、執行社長は「女性の持つ霊的な直観力と愛情の系譜が、日本社会を支えてきた」と共感を寄せられます。
日本では古来、神と繋がる役割(巫女)は女性の専任とされ、女性こそが「神の声」を降ろす存在でした。
これは、西洋の魔女狩りとは正反対の文化であり、女性が尊敬され、恐れられ、崇められてきた歴史を物語っています。
執行社長は、自らの若き日に妻を早くに亡くした体験を語りつつも、「最初から妻は怖かった」と回想します。
その怖さがあったからこそ、良き姿を見せようと努力した──女性の存在は、男性を精神的に成長させる鏡でもあったのです。
■ おわりに──「文明の再生」は家庭から始まる
この対談全体を通して、語られたメッセージは極めてシンプルかつ深遠です。
文明を再生させる鍵は、壮大な改革や政策にあるのではなく、
家庭、夫婦、親子、地域といった身近な関係性の中にあります。
理屈よりも「肚」
言葉よりも「思い」
制度よりも「敬意」
そして、文明の背骨を支えてきたのは、
名もなき母たち、妻たち、祖母たち──女性たちの無言の愛でした。
執行社長との対談は、「本当に大切なことは何か」を思い出させてくれる珠玉の時間でした。
そしてこの「思い」を胸に、私たち一人ひとりが「日本の真の姿」を取り戻していくことが、これからの未来をつくる第一歩になるのだと思いました。
◉執行社長へ感謝の言葉
今回、執行社長とこうして心ゆくまで語り合う機会をいただけたことに、心からの感謝を申し上げます。
縄文の精神、肚の文化、そして女性が育んできた無言の愛といった、私たちが忘れかけていた「日本の真の姿」が、この対話の中で鮮やかに蘇ったように思います。
社長のお話のひとつひとつが、私自身にとっても学びであり、気づきであり、何より「人間とはかくあるべき」という深い温もりに満ちておりました。
私たちは、時に現代の喧騒に流され、大切なものを見失いがちですが、こうした語らいを通じて、再び“日本人としての心の軸”を取り戻すことができるのだと、あらためて感じました。
このご縁に、深く、深く感謝申し上げます。
小名木善行 拝
【執行草舟チャンネル】歴史を支えているものとは―小名木善行先生×執行草舟特別対談
https://youtu.be/HjWzKREZThY?si=HZLFtTSpYYpm2Wgu