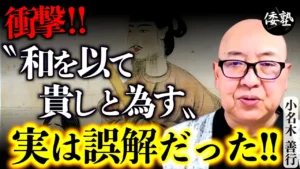「みどりの日」の由来や祝日法改正の背景に加え、ツツジとサツキの違いや日本酒の醸造技術、藤田まこと氏の話を通じて、日本の美意識と文化の豊かさ、そして「休み方」の本質に迫ります。
◉「みどりの日」とは何か──自然と心の潤いを育む祝日
5月6日(※振替休日としてのみどりの日)は、元々4月29日だった「みどりの日」が、2007年から5月4日に移されたことに伴い制定された祝日です。その意義は、「物質的には満足できる生活水準に達した今こそ、心の潤いやゆとりといった“心の豊かさ”を育むことが大切である」と内閣が述べたように、自然に親しみ、その恩恵に感謝しながら生きるという、日本人らしい感性の表れにあります。
昭和天皇が植物をこよなく愛したことも背景にあり、緑を敬うこの日には、その美意識と調和の精神が息づいているといえるでしょう。
◉ ツツジとサツキ──似て非なる“葉っぱ”の物語
この季節、美しく咲き誇るツツジとサツキ。見分けが難しそうに思われがちですが、実は「葉っぱの大きさ」で簡単に区別できます。
・ツツジの葉は4〜5cmでやや柔らかく、毛が生えている
・サツキの葉は約2cmでツツジの半分ほどのサイズ
花の形は似ていても、葉の大きさを見ることで一目瞭然。この時期、街路や公園でツツジとサツキを見分けるちょっとした知識が、日々の散歩に彩りと会話の花を添えてくれるかもしれません。
◉ 祝日の意味を見直す──「分散型休暇」のすすめ
ゴールデンウィークのように休暇が特定の時期に集中する現在の形は、観光地の混雑やインフラへの過剰な負担を生んでいます。東郷先生との対談でも話題となったように、「一斉休暇」から「分散型休暇」への転換が、地方の活性化や真の豊かさにつながるのではないかと語られました。
実際、昔の日本では酒造りの職人たちが2〜3ヶ月の集中労働の後、長期休暇を取るのが当たり前。日々のリズムに合わせて柔軟に休むという生き方の知恵が、かつての日本にはあったのです。祝日を減らしても、好きな時にしっかりと休む社会構造のほうが、文化的にも経済的にも持続可能なのではないでしょうか。
◉ 和をもって貴しとなす──5月6日と十七条憲法
意外にも、5月6日は604年、聖徳太子が十七条憲法を制定した日でもあります。その第1条が「和を以て貴しと為す」。この言葉は、単なる「仲良くする」という意味ではなく、「異なる意見を話し合い、納得の上で一致を目指す」ことを意味します。和とは忖度でも空気読みでもなく、「顔を合わせてしっかり語り合う」ことなのです。
この精神は、現代日本の職場や政治、家庭においても改めて見直すべき価値です。議論ではなく“話し合い”を重ねて一致点を探る。それが本来の「和」の姿であり、日本文化の核にある倫理観といえるでしょう。
◉ 藤田まことと「てなもんや三度笠」──笑いと誇りの文化
また本日5月6日は、1962年にテレビ番組『てなもんや三度笠』が放送開始された日でもあります。主演の藤田まこと氏は、その後『必殺仕置人』でのシリアスな役柄にも挑戦し、コミカルさと誇り高き日本男児像を両立させました。笑いの中に芯のある強さを持つ姿は、多くの日本人の理想像であったともいえるでしょう。
「馬鹿になれる者こそ大物」という言葉のとおり、余白と遊び心を大切にする日本文化の精神が、こうした人物像にも表れていたのです。
✿ 結びに
5月6日という日は、表向きには「振替休日」にすぎないかもしれませんが、実は十七条憲法制定、そして昭和天皇の植物愛、さらには昭和の笑い文化を彩った記念すべき出来事が重なる、豊かな意味を持つ一日です。
日本は歴史の長い国です。そして日本の歴史は誠実とまごころの歴史でもあります。
日々の何気ない日にも、私たちの“心の豊かさ”を育むヒントが隠されているのです。