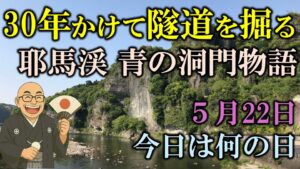坂東氏が語る警察の現場では、取調室の可視化によって真実を引き出す力が奪われ、被疑者に甘く、被害者に冷たい社会が進行中。制度の限界と国民の責任を鋭く問う。
◉ 苦しむ警察官と、取調室の現実
元警察官の坂東氏は、自身の体験を交えながら、警察官の現場がいかに過酷で、追い詰められているかを語りました。
可視化された取調室では、取り調べの一部始終が録画され、警察官が被疑者に対して少しでも強く出ると「脅された」「強要された」と主張されるリスクがあります。
こうした制度の中で、真実を引き出すことが難しくなり、警察官自身が萎縮し、精神的・肉体的に疲弊している現状があります。
さらに共犯関係を持つ外国人被疑者の場合、録画を理由に口を閉ざす例も多く、司法手続きの限界が浮き彫りになっています。
◉ 不起訴の増加と制度の崩壊
坂東氏は、現在の司法制度において、明らかな犯罪でさえ不起訴になるケースが増加していると指摘します。
検事と刑事、警察と弁護士の対立構造、過剰な人権配慮が本来の正義を損ね、「捕まえても裁けない」構図が日常化しているのです。
また、被害者の権利が十分に守られていない現状にも警鐘を鳴らしました。
冤罪が問題視される一方で、裁かれない加害者によって苦しむ被害者の声は取り上げられず、司法の本質が問われる時代に入っているのです。
◉ 今、私たちにできること
坂東氏は、「もはや手遅れ」と語りつつも、国や制度に丸投げする時代は終わったと強く訴えます。
個人の意識改革と行動こそが重要であり、「俺にできることは何か?」を一人ひとりが自問し、具体的に動くことが求められていると説きました。
また、選挙においても、政党ではなく「人物」で選ぶ意識の重要性を強調。
日本という国の原点に立ち返り、真面目に生きる人々が安心して暮らせる社会を取り戻すために、草の根の力が必要であると結びました。