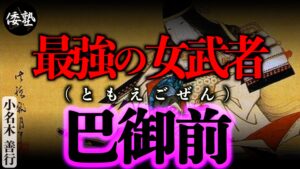百人一首は、単なる娯楽ではなく、血で血を洗う戦乱の時代に、平和と心の豊かさを取り戻すために編まれた“心の文化”です。本配信では、定家の想いと日本語の本質に迫ります。
◉ 歴史の転換点に学ぶ:秩序・責任・文化
5月27日には、三つの重要な出来事がありました。
1867年、江戸幕府が「外国総奉行」を設置。裁判官・警察長官・大臣の役割を兼ね備えたこの役職には、全権が委ねられた代わりに、失敗すれば切腹という厳格な責任が課せられていました。この背景には、日本独自の「秩序は責任によって成り立つ」という考え方があり、現代のような法治国家とは異なる、“人が法を超える”在り方が存在したのです。
続いて紹介されたのは、1905年の日露戦争「日本海海戦」。東郷平八郎率いる日本艦隊がバルチック艦隊に大勝し、日本が独立国家としての存在を世界に示した歴史的勝利です。
一方、1980年に起きた「光州事件」では、韓国政府が自国民に戦車を向け、多数の市民が犠牲となりました。これは“法”ではなく“力”で民を支配する国家の悲劇であり、「国家は誰のためにあるのか」という普遍的な問いが投げかけられました。
これらの話題を通して、日本文化における「統治と責任の倫理」、そして他国との違いが浮き彫りになっていきます。
◉ 百人一首に込められた“文化による平和”
文暦2年(1235年)5月27日。藤原定家は、自身が編纂した『小倉百人一首』の完成を日記『明月記』に記しました。この出来事が「百人一首の日」の由来です。
定家は和歌の大家であると同時に、当時の朝廷を支える政治家でもありました。源平の争乱により血なまぐさい世の中になっていく中、「政治だけでは世は治らない。人々の心が荒んでいるのが問題だ」と気づいた定家は、政から離れ、文化の力によって平和を取り戻す道を選びます。
そのきっかけとなったのが、式子内親王の一首──
玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば
忍ぶることの 弱りもぞする
戦乱と混乱の中で、貴族社会の崩壊を憂いた内親王が詠んだこの歌に、定家は心を打たれ、深い自己反省の末に「百人一首を編もう」と決意します。500年にわたる天皇と貴族による平和な時代の象徴を、和歌に託して未来に伝えるために。
こうして定家は70歳を過ぎてから小倉山荘に籠もり、4年をかけて百人の歌人の歌を選び抜き、ひとつの文化としてまとめ上げたのです。
◉ 日本語は「応答」ではなく「関係性」を語る言語
本講話の核心は、百人一首がただの“かるた遊び”ではなく、「関係性の文化」を表現する媒体であったという点です。
西洋文化は“応答”を重視します。英語の「Thank you(I will think of you)」や「Let’s eat」には、相手の行為に対するリアクション(反応)という性質があります。これは「個」と「個」の間に明確な線を引いた上で、行為に返す言葉です。
それに対して日本語は、「ありがとう=有り難し」「いただきます=命の恵みに手を合わせる」など、相手との“関係性”そのものに意識が向いています。たとえば「月が綺麗ですね」という一言に「愛してるよ」という深い意味を込める。言わずとも伝わるのが、日本語の美しさであり、本質なのです。
和歌は、こうした“言わない文化”の最たるものです。31文字の中で、言いたいことは語られず、手がかりだけが置かれる。読み手はその背景や心情を“察する”必要があります。つまり和歌とは、文字情報ではなく、心のやりとりを通じた“関係性の詩”なのです。
◉ 歌の裏にある「思い」を察する文化
藤原定家の百人一首の意義は、和歌という関係性の言語を通じて、分断や暴力ではなく、“共感”と“察し”による和の世界を築こうとした点にあります。
講話では、台湾の現代でも「歌会」が文化として残っている例が紹介されました。台湾では、即興ではなく事前に練りに練った歌を持ち寄り、その歌の裏に込められた感情を皆で読み合うのです。
「ああ、この人は恋をしているな」
「いえ、そんなつもりでは……」
「いやいや、あなたの歌には切なさがにじんでいますよ」
このやり取りには、“本音を察してもらえた喜び”という、日本文化特有のあたたかさがあります。そうした共感によって、心と心の交流が生まれ、社会は穏やかに、丁寧に紡がれていくのです。
◉ 今こそ見直したい、日本文化の“深み”
現在のSNS社会では、自分の意見を大声で発信するばかりで、相手の思いや背景を「察する」文化は影を潜めつつあります。
「違う意見=敵」と見なすような構図は、関係性を破壊し、人々を分断へと導きます。
こうした風潮に対し、定家が百人一首を通じて訴えた“文化による平和”というメッセージは、今こそ必要とされているのではないでしょうか。
百人一首は、戦乱を止めるための歌であり、人の心を再び結び合わせるための道具であり、そしてなにより、言葉にできない想いを届け合う日本語文化の結晶です。
藤原定家が最後に選んだ「文化で国を護る」という道。その想いを、現代に生きる私たちも、もう一度心に刻むべき時が来ているのかもしれません。