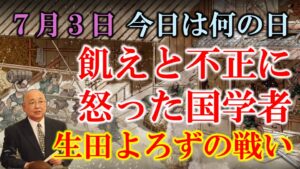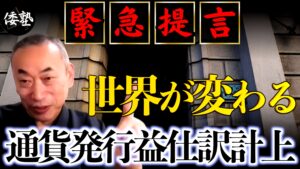アメリカ独立宣言の精神と、鎌倉幕府滅亡に見られる日本の「関係責任」の文化を対比。さらに20世紀梨誕生の心温まる物語を紹介。自由と責任、教育のあり方を問い直す。
【鎌倉幕府の滅亡──責任を背負う武士たち】
1333年7月4日、新田義貞の進軍によって鎌倉幕府が滅亡しました。
北条高時をはじめとする一族約800人は、この日に一斉に自刃。
これは単なる戦敗の自殺ではなく、鎌倉幕府という政権の失政の責任を取る“関係責任”の文化から生まれた行動でした。
日本では、為政者たちは「自らの失策で民が苦しめば、自ら腹を切って責任を取る」という覚悟がありました。
それは、武士道の中核ともいえる「恥を知る」精神です。
これは、現代政治においてこそ改めて問い直すべき姿勢ではないでしょうか?
【独立宣言と「権利」の意味──福沢諭吉の翻訳に学ぶ】
1776年7月4日、アメリカはイギリスからの独立を宣言しました。
生まれながらにして人に与えられた「生命・自由・幸福の追求」は、どんな政府も侵してはならないと説かれています。
この独立宣言文を福沢諭吉が日本語訳した際、「権利(right)」を「通義(つうぎ)」と訳したのは象徴的です。
通義とは、
神(天)から与えられた正しい行いであり、
自分勝手な権利主張ではない。
自由とは他者の自由と調和してこそ真の価値がある
──日本的な視点からの再解釈がここに見られます。
【20世紀梨の誕生秘話──「分け与える」心の文化】
7月4日は「梨の日」でもあります。日本で最も知られる梨の一つ「20世紀梨」は、1888年、千葉県松戸市の13歳の少年・松戸覚之助が、偶然拾った苗木を育て、10年かけて改良したことから誕生しました。
特筆すべきは、この梨が評価されたあと、覚之助とその家族が全国の農家に無償で苗木を分け与えたという事実です。
利権や特許に走ることなく、善意と共に日本中に広がった「甘美で瑞々しい」梨。
その背景には、「ともに豊かになる」ことを喜ぶ、日本人ならではの心根があります。
【「教育」とは何か──歴史に学ぶ未来への指針】
ライブの最後には、田村氏が行う「寺子屋教育」にも言及されました。
週1回の歴史授業を通して、子供たちが目を輝かせて成長していく姿──それは、まさに「生きた教育」の姿です。
現在の学校教育は、年号や事件の表面だけを教え、「なぜ起きたか」「どう生きるか」までは踏み込みません。
7月4日という日を、単なる出来事の羅列ではなく、責任、自由、道徳、共生といった“本質”に触れるきっかけとして活かすこと。
それこそが、学びの原点であり、日本再生の鍵でもあります。
→寺子屋あけぼの
https://terakoyaakebono.wixsite.com/mysite