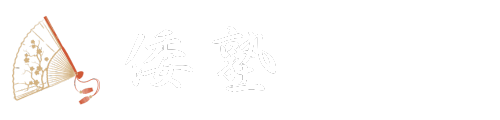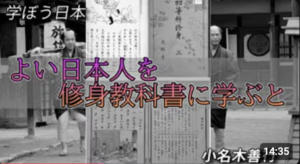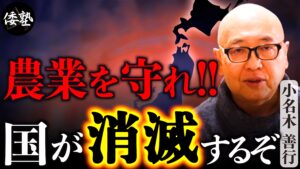日本最初の首都は、外交や行政の中心として機能する場所ではなく、国の存続に不可欠なお米を蓄える「米倉」でした。神武天皇から仁徳天皇、孝徳天皇へと受け継がれた首都の概念の変遷とその背景を解説します。
- 「首都」と「都」は異なる概念だった?
日本の「首都」と聞くと、奈良や京都を思い浮かべる人が多いですが、古代日本において「首都」と「都」は異なる概念でした。現在のように、政治・経済・外交の中心地として機能する「首都」とは違い、古代の「都」は国の食糧備蓄のための「米倉」のある場所を指しました。神武天皇が紀元前660年に建設した「橿原宮」は、単なる王の住居ではなく、日本全国の食糧を集め、蓄える重要な拠点だったのです。
特に日本は災害が多い国であり、毎年の台風や定期的に発生する地震によって、食糧危機に直面することも少なくありませんでした。そのため、長期保存が可能な米を蓄え、災害時の食糧供給を担う「都」の存在は、日本の国家運営にとって不可欠だったのです。
- 日本最初の「首都」難波宮とその短命な運命
仏教を奨励した孝徳天皇は、650年に大阪の「難波宮」を建設しました。これは、日本で初めて外交機能を持つ都市として設計されたもので、都の構造も碁盤の目のように整備され、西洋の首都に近い形をとっていました。
しかし、この難波宮はわずか4年で廃止されてしまいます。理由は大きく二つありました。
(1)米倉の役割を果たせなかった
難波宮は海に近いため、津波や外敵による襲撃のリスクが高く、食糧備蓄の拠点には適しませんでした。中大兄皇子(後の天智天皇)らは、この地に首都を置くことに反対し、再び「都」を大和盆地へ戻すことを主張しました。
(2)仏教勢力の台頭と国内の混乱
仏教の影響力が強まるにつれ、日本の政治に大きな影響を及ぼすようになりました。764年には「藤原仲麻呂の乱」が勃発し、仏教勢力が政権を掌握しようとする動きが見られました。このような政治的混乱の中で、難波宮は外交の拠点としての役割を果たせなくなり、結局、大和盆地へと都は戻されることになりました。
- 日本の「首都」概念の変遷とその背景
難波宮の廃止後、日本は新たな首都を求め、奈良の藤原京、平城京、そして平安京へと遷都を繰り返しました。ここでようやく、日本の「首都」は西洋的な都市国家の形をとるようになります。
しかし、その根底には常に「食糧の備蓄」という考え方がありました。
日本の政治文化の中心は、国民が豊かに、安心して暮らせる社会を築くことにあり、そのために「米倉のある場所」が長年、首都としての役割を果たしてきたのです。
現代の日本においても、この精神は受け継がれています。天皇陛下が「新嘗祭(にいなめさい)」で新米を神々に捧げるのも、古代から続く「食糧を国家の宝とする思想」の名残りです。
まとめ
(1)古代日本の「首都」は、西洋のような政治・経済の中心地ではなく、「米倉」のある場所だった。
(2)仁徳天皇の時代に日本は食糧大国となり、外国との交流が活発化した。
(3)孝徳天皇の「難波宮」は日本初の外交都市だったが、わずか4年で廃止された。
(3)その後、日本は藤原京・平城京・平安京と遷都を重ね、現在の「首都」の形を確立した。
(4)日本の政治文化の根底には、庶民の暮らしを守る「食糧備蓄」の思想があった。
日本の首都の概念は、単なる権力の象徴ではなく、「国民の生活を守るための拠点」として発展してきたのです。