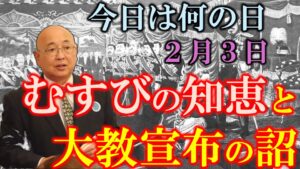名張市の農業は、限られた農地を活かし、兼業農家が発展させてきた。伝統的な知恵と最新の土壌管理技術「菌ちゃん農法」を組み合わせ、自然の力を活かした農業の可能性を探る。食糧自給の未来を考える一作。
名張の農業の歴史と百姓の知恵
名張市は中山間部に位置し、農地面積が狭いため、昔から農業と他の仕事を兼ねた「百姓」の暮らしが根付いてきた。「百姓」とは「百の仕事をする人」の意味を持ち、名張では農業に加え、養蚕、和紙作り、タバコ栽培、しめ縄作り、草履作りなど、多様な生業を組み合わせて生計を立ててきた。
このような背景から、名張の農家は農業単体に依存せず、独自の工夫を重ねてきた。その流れは現在も続いており、農業と他の職業を両立する「兼業農家」が全体の6割を占める。名張の農業の発展には、この歴史を理解することが欠かせない。
土壌菌が育む「菌ちゃん農法」の驚異
最近注目を集めているのが「菌ちゃん農法」という土壌管理技術だ。この農法は、畝の中に枯れた木や落ち葉を埋め、自然発酵させることで土壌菌を活性化させる仕組みになっている。この土壌菌が肥料の代わりとなり、農薬や化学肥料を使わずとも作物が元気に育つのが特徴だ。
欽ちゃん農法のポイント
1. 土壌菌を活かす:枯れた木や葉が分解される過程で土壌菌が増殖し、自然に栄養豊富な土が作られる。
2. 水やり不要:雑草が朝露を吸収し、土壌に水分を供給するため、ほとんど水やりをしなくても育つ。
3. 低コストで持続可能:機械を使わず、自然の力を利用するため、農業の負担を大幅に軽減できる。
この方法なら、兼業農家でも無理なく農業を続けられ、かつ健康的な作物を生産できる。実際に試してみた農家からも、野菜が大きく育ち、味も格段に良いとの報告が相次いでいる。
農業と地域コミュニティの再生
名張では、菌ちゃん農法の普及を目的とした体験会も開催され、多くの人が関心を寄せている。地域のフリーペーパーで紹介されたことで、市外・県外からも参加希望者が集まり、定員を大幅に超える人気イベントとなった。この体験会では、実際に畝作りを体験し、土壌菌の働きを学ぶことができる。
また、農業を単なる生産活動ではなく、「コミュニティの場」として捉える動きもある。かつての日本では、田植えや収穫の際に農村歌舞伎や田楽が行われ、農業と文化が一体となっていた。この考えを現代に応用し、農業を通じた人々の交流の場を作ることで、地域の活性化にもつなげることができる。
食糧危機に備え、自給自足の重要性
近年、世界的な物価上昇の影響で食料品の値上げが相次いでいる。例えば、ニューヨークではもやし一袋が750円、卵10個が2000円にもなるほどだ。こうした状況を考えると、日本国内の食料自給率を高めることが重要になる。
食料を自分で作ることで、出費を抑えられるだけでなく、安全で新鮮な食べ物を手に入れることができる。戦後の日本では多くの家庭で鶏を飼い、卵を自給していたように、自宅での小規模な農業も有効な手段となる。
また、自然農法で育てた野菜は、一般の農薬や肥料を使った野菜と比べて、「腐る」のではなく「枯れる」という違いがある。これは、農薬や化学肥料を使わないことで、野菜本来の自然な状態が維持されているからだ。こうした健康的な食材を自給することは、食の安全を守る上でも重要である。
地元の食文化と「水が合う」原則
食べ物の美味しさには「水が合う」という重要な要素がある。例えば、新潟産の魚沼産コシヒカリは、現地の水で炊くと絶品だが、他の地域の水で炊くと味が落ちることがある。これは、米と水が同じ土壌の環境で育っているため、最適なバランスを持っているからだ。
名張の米も同様に、伊賀の水で炊くことで最高の味を引き出せる。こうした「地元の食材を地元の環境で味わう」という考え方は、日本の食文化に深く根付いている。
さらに、名張の藤堂藩時代には、自然災害で収穫ができなくなった地域に対し、火縄作りを許可し、それを年貢の代わりとする支援策が取られていた。このように、地域の資源を活かして困難を乗り越える知恵は、現代にも活かせるものである。
まとめ
名張の農業は、単なる生産活動にとどまらず、地域の歴史や文化、そして未来の食糧問題とも深く関わっている。欽ちゃん農法のような持続可能な農法を活かしながら、地域コミュニティを再生し、食の安全と自給自足を実現することが求められている。
これからの時代、食の自立は経済的な安心感にもつながる。名張の農家の工夫や、土壌菌を活かした農法の可能性を学び、自分たちの暮らしに取り入れていくことが、これからの日本を支える鍵となるかもしれない。