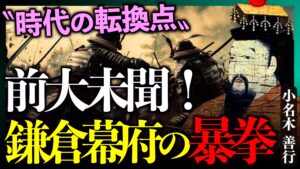日本国憲法は占領統治下で制定された経緯から多くの矛盾を抱えています。改正が難しい構造的問題を踏まえつつ、「執行停止」という法的手段を通じて憲法との向き合い方を提案しています。
◉ 占領統治下で生まれた日本国憲法の正体
日本国憲法は、昭和21年、GHQ(連合国軍総司令部)によって占領統治下で制定されたものです。当時の日本は「Occupied Japan(占領統治領日本)」という名称で、国旗も日の丸ではなく三色旗、輸出品には「Made in Occupied Japan」の刻印がされていました。
このような状態で制定された憲法は、本来の意味での「国民が自主的に作る憲法」ではなく、実質的には「GHQ統治のための日本人服務規程」として押し付けられたものでした。
したがって、日本国憲法を「日本人の憲法」として受け入れるかどうかには、根本的な疑問が残ります。
◉ なぜ日本国憲法は改正できないのか?
現行憲法は、実質的に改正不能ともいえる構造を持っています。
第96条では、憲法改正のために「各議院の3分の2以上の賛成」と「国民投票での過半数の支持」が必要と定められていますが、具体的にどのように過半数を測定するか(有権者数?投票者数?)が曖昧です。
また、国会には予算や補正予算の処理といった緊急の課題が山積しており、長期にわたる憲法改正議論に時間を割く余裕がありません。さらに、改憲派と護憲派の政党対立も激しく、現実的な審議進行は極めて困難です。
加えて、国民意識にも課題があります。「憲法を変える=戦争をする国になる」といった極端な思考が広がっており、議論そのものが感情的になりがちです。このような中で改正を進めるのは極めて高いハードルとなっています。
◉ 「執行停止」という現実的な選択肢
そこで提案されているのが、「法の執行停止」というアプローチです。
これは、法律そのものを廃止・改正するのではなく、政府がその運用を一時的に止めるというものです。実際、明治期に制定された「皇室典範」や、かつての「大日本帝国憲法」なども、廃止はされずに現在も“塩漬け状態”で残っています。
「法の執行停止」は、法的には可能であり、総理大臣や担当大臣の判断で通達や政令をもって実行可能です。オウム真理教事件において「破壊活動防止法」を適用しなかった例などが、それに該当します。
つまり、現行憲法に矛盾を感じながらも、廃止も改正もできない状況であれば、「使わない」という選択が一つの出口となるのです。
この考えは、皇室典範の運用にも応用できます。例えば、男系継承の問題などにおいても、典範の執行を止め、ご皇族自身に判断を委ねるという柔軟な運用が可能となります。
◉ 法をどう見るかで未来が変わる
日本の法体系には、実は「変える」「なくす」以外に、「使わないでおく」という選択肢が存在しています。これを「死文化(しぶんか)」と呼びます。
つまり、法は存在しているけれど、運用しない状態のことです。
これは、イギリスにいまだ存在する奇妙な法律(例えば「夜にケルト人が町を歩いていたら弓で射殺してもよい」)が、運用はされないものの法的には有効であるという事例からも説明できます。
憲法も同様に、“生かすかどうか”は政治の意思次第であり、それには柔軟な発想が求められます。
実際に、国営事業によって国家が収益を得ていた時代には、税負担が今よりも軽く、国民生活も安定していました。再び国家主導の収益構造に戻すという提案も、法律の見直しなしには難しいことですが、「執行停止」の仕組みを活用すれば、現実的な転換が可能になるかもしれません。
◉ 憲法の未来を日本人の手に取り戻すために
結局のところ、私たち日本人が考えるべきなのは、「この憲法を守るべきか否か」ではなく、「この憲法がそもそも誰のために作られたのか」という原点です。
占領統治下で作られた現行憲法を「日本国憲法」としてそのまま使い続けるのではなく、私たち自身の手で新たな憲法を作るべき時期に来ているのかもしれません。
もちろん、新しい憲法を制定することは簡単ではありません。だからこそ、「法の執行停止」という現実的な選択肢を知り、活用することが重要です。
すべては、発想の転換から始まります。
故・多湖輝先生の言葉、「諸悪の根源は個人の頭の固さにある」が示すように、視点を変えれば道は開けるのです。
◉ 補足として
動画の中で、日本国憲法がGHQによる押し付け憲法であったことを述べました。また、昭和27年の主権回復後においても、日本が日本国憲法の執行停止を行わなかったことも申し上げました。だからといってGHQや米国を恨んだり、戦後の日本を腰抜呼ばわりすることは、絶対にあってはならないことです。
なぜなら日本は、この憲法があったから、朝鮮戦争に参戦することをしないで済んだからです。戦争で日本中が焼け野原になり、食料も覚束ない状況下にあって、もし日本が米国の求めに応じて昭和26〜7年の頃に戦力を回復し、朝鮮戦争に参戦していたら、もちろんそれによって朝鮮戦争が韓国側の勝利に導かれる可能性は大であったとしても、日本の復興は遅れ、人々の生活は困窮し、もしかすると戦後の高度成長さえなかったかもしれないし、21世紀となった現代においても、なお、我が国に徴兵制が敷かれていたかもしれないのです。
当時の日本は、泥沼化した朝鮮戦争への参戦を、当時の首相の吉田茂氏がGHQによって与えられた日本国憲法を盾に、断固として拒んだという事実があります。そして、そんな言うことを聞かない日本に対し、米国は日本の主権回復後も様々な便宜を与え、日本の復興を支援してくれたという事実があります。
そうした事実を、私たちは、まず、ありがたいと思い、感謝の気持ちを忘れてはいけないと思うのです。
そのうえで、すでに実体と合わなくなり、限界を超えている日本国憲法の執行を停止し、新たな憲法を創憲するか、あるいは不文憲法でいくのかを、私たちはしっかりと決めて行かなければならないと思います。私たちは、すでにグローバル化した世界の中の一員となっています。その中にあって、我が国がどのように自立し、国民にとっての日本を、神々が目指した「よろこびあふれる楽しい国」にしていくか。
そういうポジティブで前向きな思考こそが、いま求められているのだということを、私たちは原点に置いていく必要があると思います。