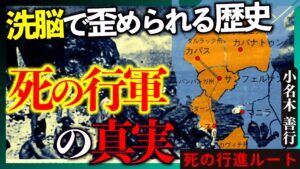日米が理想的に共存するためには、対等な信頼関係、文化的相互尊重、技術と安全保障の協力、民間交流の強化、歴史を見つめる勇気が必要です。小名木善行氏が未来に向けた具体的な提言を語ります。
◉ 対等な信頼関係に基づく日米パートナーシップ
これからの日本とアメリカの理想的な関係性は「対等な信頼と尊重に基づくパートナーシップ」であるべきです。政府間の外交だけでなく、国民一人ひとりの意識こそが本当の共栄を生み出す基盤です。
これまでの日本は「アメリカの傘の下」で安心してきましたが、これからは自立した日本として、主体的に世界と向き合う姿勢が必要です。特に安全保障の分野では、日本がアメリカの「指示待ち」ではなく、自国の国防と国益を自ら考え、行動していくことが問われています。
また、在日米軍基地の存在についても、依存構造ではなく、対話と合意を重ねたうえでの新たな枠組み作りが求められるとし、「日米安保」のあり方も見直す必要があります。
◉ 文化・技術・歴史を共有し、共に未来を創る
文化的側面では、日本の「礼儀・調和・自然との共生」という価値観と、アメリカの「自由・多様性・チャレンジ精神」は対照的でありながら、相互に尊重し合うことで、より豊かな理解と協調が育まれます。
今後の重要な分野として、半導体・AI・宇宙開発などの技術領域での日米共同開発を挙げ、日本の技術力とアメリカの資金・マーケティング力が融合すれば、非常に強力なチームが構築できことになります。
さらに、歴史を見つめ直すことの大切さにも触れ、特に硫黄島の戦いを両国の視点から描いたクリント・イーストウッド監督の映画を例に、「勝者の物語」ではなく、「真のヒストリー」を共有する文化への移行が必要です。
日本映画の質低下にも言及し、「かつては世界と渡り合えた日本映画が、いまや自己喪失に陥っている」と憂い、文化の再定義も日米関係における重要な鍵であるとしています。
◉ 日本の「再定義」と民間交流の強化が鍵
未来の日米関係において、最大のカギは「日本の再定義」です。これまでのようにアメリカ依存の国家でいるのではなく、自国の防衛体制や法制度を自らの意思で整え、「NOと言える日本」になることが、対等な関係構築の出発点になります。
そのためには、自衛隊の制度的な制限の見直しも重要であるとされ、憲法9条の再解釈や法改正についても国民的議論が必要です。
政治レベルの関係だけでなく、民間レベルでの交流──例えば学生の交換留学、スポーツ・音楽・芸術を通じた文化交流なども、国家間の信頼醸成に直結します。これらは政府がもっと積極的に支援すべきことです。
トランプ政権は。日本にとってのチャンスです。今こそ日本が対等なパートナーとして再出発する好機です。そのためにも、「日本とは何か」を自ら問い直し、勇気を持って一歩を踏み出すことが大切です。