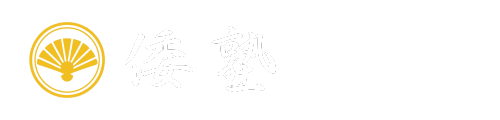赤穂浪士事件は、単なる個人的な感情の衝突ではなく、藩主としての責務や日本古来の皇室尊崇の思想が絡んだ事件です。
浅野内匠頭が松の廊下で吉良上野介に刃傷に及んだ背景には、室町以来の「将軍上座・勅使下座」という伝統と、赤穂藩が重んじる「天皇の勅使を上座に」という信念の対立がありました。
浅野内匠頭に殺意はなく、吉良を懲らしめるに留めた行為に、武士道精神や藩士たちの忠義の根源が表れています。
いわゆる「本当のこと」、「真相はこうだ」といったものは、解釈ですから、様々な解釈が成り立ちうるのです。
赤穂浪士の事件に関する一連の論考も、これは解釈です。
けれど、だからといって、様々な解釈を羅列しても、意味はありません。
むしろ、建前として、「この件は、こういうことであったのだ」と「決めて」しまう。
そうすることによって、具体的正義を実現する。
建前というのは、決して意味のないものではなく、建前が立てられるからこそ、社会が安定し、対立や闘争を離れて、人々の生活の安寧が図られるのです。
このことは、何が正しいかよりも、はるかに重要なことです。
ある方からご質問をいただきました。
それは、
「赤穂浪士の一連の事件の中で、
浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)が、
吉良上野介(きらこうずけのすけ)に、
江戸城内の松の廊下で
刃傷に及んだ理由がわからない」というものでした。
ほとんどの映画や演劇、ドラマでは、浅野のお殿様が、吉良上野介に、
「イジメられて我慢できなくなって刃傷に及んだ」としてドラマ化しています。
しかし浅野のお殿様は、赤穂5万国のお殿様です。
そのお殿様ともあろう御方が、年寄りにすこしイビられたくらいで、逆ギレして刃傷に及んだというのなら、それはあまりにも浅はかだったということになるのではないか。
赤穂5万国の藩士たちや、その家族、そして藩の民に対して、それは殿様として、あまりに無責任とはいえないか。
さらにいえば、そのような殿のために、家臣が討ち入りまでしているということは、すこし筋が違うのではないか、という疑問です。
なるほど鋭い指摘だと思います。
赤穂浪士の物語の醍醐味は、実は、そんな疑問から始まるのです。
そして、浅野内匠頭と赤穂浪士の活躍は、実はその後の日本の歴史を変えたのです。
*
まず誤解を解いて置かなければならないことは、江戸時代の大名(藩主)というものは、絶対王政における君主ではないということです。
我が国のすべては神々のものであり、神々の直系の子孫である天子様(天皇)のものであるというのが、基本です。
我が国は天皇の知らす国なのです。
ですから藩主は、絶対君主ではなく、どこまでも藩の総責任者であって、藩を天子様から将軍を経由して預かっている立場です。
もっというなら藩主は、藩の土地を護り、藩民が豊かに安全に安心して暮らせるようにするための藩の最高責任者です。
従って、藩に何かあれば、その責任は藩主の責任となります。
そしてそれが許しがたい問題であれば、藩主は腹を斬らなければならない。
それが江戸時代の標準となる考え方です。
藩主という地位は、命がけなのです。
このことが理解できず、藩主が傲慢な君主のように振る舞うときには、家臣たちが藩主を座敷牢に押し込め、毎日対話を続けて藩主に考えを改めるように説き、もしそれでも改まらないときには、藩主は家臣たちによってその地位を追われたし、藩主が改心すれば、そこではじめて座敷牢から出されて、もとの藩主の地位におさまりました。
これは「主君押込(しゅくんおしこめ)」といって、有名な上杉鷹山さえも、その「主君押込」に遭っています。
これが我が国の「忠義の道」です。
チャイナ的儒教観では、上長に身を捧げるのが「義」、上長の命令を絶対視することが「忠」、上長に恥があれば、嘘をついてでもそれをかばうのが「諱(き)」です。
けれども我が国は、天の神が中心にあり、その天の神の子の天子様(天皇のこと)が、すべての民を「おほみたから」とする知らす国です。
ですからチャイナとはベクトルの方向が異なり、
「民のために身を捧げるのが義」
「民の幸せを中心に置くのが忠」
「民のために誠意を尽くすことが誠」等と規程されます。
そして上長の恥を隠す「諱(き)」の概念は、我が国にはありません。
たとえ上長であっても、間違っていれば、堂々とこれを諌(いさ)める者こそ忠義の士とされてきたのが日本です。
「主君押込」は、そうした伝統文化の中に存在しています。
播州赤穂藩の浅野家は、そうした日本古来の思考を重要視した山鹿素行によって、藩の教育が施された藩です。
山鹿素行は『中朝事実』を著し、真の中華といえるのは、Chinaではなく我が国であると、言い切った、江戸時代を代表する国学者であり、皇室尊崇論者です。
従って、赤穂藩の藩風は、とりわけ更新尊崇の念が強い。
その赤穂藩のお殿様が、吉良上野介とともに、勅使下向の接待役を幕府からおおせつかります。
勅使下向というのは、毎年正月に、幕府から京の都の天子様に充てて、新年の祝賀の品が届けられます。
その届け物の御礼にと、今度は天皇の使いである勅使が、江戸に下向します。
京の都に向かうのが「上り」、京の都から江戸に行くのが「下り」です。
だから「勅使下向」といいます。
赤穂藩は山鹿流ですから、何よりも皇室尊崇です。
一方、吉良家は、高家(こうけ)といって、もともと室町時代以来の名門の家柄です。
室町幕府は、ご存知の通り将軍が「日本国王」を名乗った政権で、比較的冷静に官位に忠実な気風があります。
そこでトラブルが起こります。
勅使(ちょくし)は天皇の使いです。
ちなみに、天皇の使いが勅使で、上皇の使いなら院使(いんし)、皇后の使いなら皇后宮使(こうごうぐうし)、中宮の使いなら中宮使(ちゅうぐうし)、皇太后の使いなら皇太后宮使(こうたいごうぐうし)、女院の使いなら女院使(にょいんし)です。
勅使は天皇の使いで、大納言、中納言の官位にある人が、勅使を努めます。
将軍は、左右大臣ないし内大臣です。
徳川将軍は、この時代、五代将軍綱吉の時代ですが、綱吉はこの時代には、正二位内大臣兼右近衛大将兼征夷大将軍です。
官位の順番は、
太政大臣
左大臣
右大臣
内大臣 (←将軍)
大納言
中納言 (←勅使)
少納言
と続きます。
つまり、勅使は天皇の名代ではありますが、官位は将軍の下です。
そこで問題になるのが、勅使の席次です。
官位からすれば、将軍が上座、勅使は下座です。
しかし勅使は「天皇の名代(みょうだい)」です。
名代ということは、天皇の代理なのですから、勅使が上座に座り、将軍が下座に座る。
当然のことです。なぜなら将軍は天皇の部下だからです。
ところが、室町幕府以来の伝統は、将軍が上座、勅使が下座です。
徳川幕府も、これを踏襲していたし、室町以来の伝統を保守する吉良上野介もまた、当然、この将軍上座説を採っていました。
なぜそのようになったかというと、理由は室町幕府の初代将軍足利尊氏の時代にさかのぼります。
初代の足利尊氏は、バラバラに分断された全国の土地の管理を、各国ごとに任命した大名主(おほなぬし)のもとにすべての管理権を統合しました。
これは土地に関する「私的所有権」をそのままに、「公的管理権」によって統合したという、近現代の法学的にも、世界史的にも実は画期的なことを実行したわけです。
ところが、こうして土地を分け与えるに際して、幕府所有の土地を、あまりに限られた小さなものにしてしまった
ために、室町幕府にはカネがない。
三代将軍足利義満の時代になると、財政の赤字がとんでもないものになってしまうわけです。
そこで起死回生の策として、成立したばかりのチャイナの明国との交易による財政の立て直しが計策されました。
ところが当時の明国は(できたばかりの国で強気で)、明国皇帝に朝貢する国でなければ、交易を認めないという。
そこで足利義満は、明国皇帝に、自分が「日本国王」であると述べるわけです。
明国は「日本の統治者は天皇であって、将軍ではないのではないか」と問い合わせてくるのですが、義満は、「天皇はあくまで祭司長であって、日本の統治者は自分である」と回答しました。
明国はこれを認め、これによって1404年、日明貿易のルートが開かれます。
日明貿易がどのくらい儲かったかについては記録があるのですが、だいたい一往復で財産が400倍になった(行きで20倍、帰りで20倍)と言われています。
これはつまり、元手100万円が、一往復で4億円になるようなものです。
これによって足利義満は、見事に足利幕府の財政を立て直しました。
そして余力の生まれた財政によって、お能や彫刻、建築物として金閣寺などに代表される北山文化が形成されるわけです。
そういう意味では、つまり財政建て直しの手腕や、文化育成という面においては、足利義満は実に偉大な将軍であったといます。
けれど、天皇と将軍の位置づけを国内向けと海外向けに分けたことが、後年には、結果として、日本国内に価値観の分断を生んでしまいました。
どういうことかというと、日本を古くからの国家最高権威としての天皇を頂点とするシラス国と規定するか、将軍を最高権力者である日本国王とするまったく新たな日本と規定するのか、いう、ふたつの相反する概念(感情とか気分と呼んだほうが良いかもしれません)を生んでしまうのです。
将軍は、毎年正月に天皇のもとに贈り物をします。
その御礼の使者が「勅使下向(ちょくしげこう)」です。
天皇が上、将軍はその部下ですから、「下向」と言うのです。
ところがここで、勅使が将軍と対面するときが問題になります。
本来なら、天皇は将軍よりも偉く、勅使は天皇の名代ですから、勅使となった個人の官位にかかわらず、将軍より上座につくのがあたりまえです。
なぜなら、名代ということは、天皇の代わりなのですから、勅使としてのお言葉を述べられるときには、天皇に準ずる地位になるからです。
ところが室町幕府には、ときに明国からも使者がやってきているわけです。
対外的には、日本でいちばんエライのは日本国王である将軍としています。
天皇は単なる祭祀長という立場です。
そうなると、明国の使者も列席する勅使と将軍の対面のとき、勅使を将軍より上座に座らせるわけにいかないのです。
つまり将軍が上座になり、下である勅使の答礼を聞く、という形になります。
これが室町以来の伝統です。
そして吉良家は、室町幕府の足利将軍家にもっとも近い血筋です。
これを「高家(こうけ)」と言います。
そして高家である吉良家は、代々、室町以来の伝統を江戸の徳川将軍に伝え、それを護る役割を担っていました。
一方、山鹿流の浅野家は、もちろん皇室尊崇ですから、勅使が上座という考え方です。
室町幕府以来の伝統に従う吉良家は、将軍が上座、勅使が下座です。
室町以来、徳川幕府も将軍が上座、勅使が下座で勅使下向の接待を行ってきています。
吉良上野介と浅野内匠頭による勅使の接待役は、二度行われていますが、一度目は、初めてのことでもあり、浅野内匠頭は吉良上野介の指示を受け入れています。
単純に受け入れたのですから、トラブルも起きていません。
しかし皇室尊崇の念の強い播州赤穂家にしてみれば、この席次はどうにも受け入れがたい席次です。
常識で考えても、天皇の勅使が上座は当然のことだからです。
ですから二度目の接待に際しては、これが許せない。
そこで浅野内匠頭は、勅使を上座、将軍を下座として席を準備します。
ところが、これに気づいた吉良上野介が、席を全部やり直してしまいます。
浅野内匠頭ならずとも、赤穂藩士たちにとって、これは許しがたい蛮行です。
このことは、たとえば現代の内閣総理大臣が、その親任式において天皇よりも上座に立ったら、おそらく保守系の考え方をお持ちの方なら、そんな総理を絶対に赦さないどころが、おそらくテロにも走りかねない、といえば、その気持はすこしはわかっていただけるのではないかと思います。
こうして殿中松の廊下の事件が起こっています。
この事件は、江戸城内の松の廊下で、浅野内匠頭が脇差しを抜いて吉良上野介の額を割ったという事件です。
少し補足しますが、吉良上野介は、伝統を受け継ぐたいへん立派なお殿様で、その人格の素晴らしさから、地元でたいへんに尊敬され、息子は上杉家の跡取りになっているし、娘は大納言の大炊御門家、島津家などに嫁ぐという栄誉を得ている人です。
決して、ヒヒ爺のような人物ではありません。
刃を振るった浅野内匠頭も、そういうことをわかっているから、松の廊下の刃傷沙汰においても、実は殺意はありません。
なぜなら、顔の傷はものすごい流血量となるのに、吉良上野介は、そこまでの流血はしていません。
ということは、刃物で切ったのではなくて、刃物の背を使って額を叩いたか、薄皮一枚の傷を負わせただけということがわかります。
浅野内匠頭は、脇差しを抜くと、刀身を返して刀の峰で吉良上野介の額を叩いたか、はじめから額の薄皮一枚を斬るという離れ業を行っているわけです。
これなら多少の出血はあっても、大流血ということにはなりません。
第二に、額に向けて切りつけられれば、誰でも手で額をかばおうとします。
ところが吉良上野介は、手には怪我をしていません。
これはおかしなことです。
顔の前に刃物を振り下ろされて、手でかばおうとしない人などいません。
ということは、浅野内匠頭の小刀の使い方は、よほどの練達であったということです。
なぜなら、吉良上野介が額を手でかばういとまも与えずに、素早く傷を負わせているからです。
まさに抜く手もみせぬ早業です。
吉良上野介が自分の額をかばう間も与えずに、額を割ったのです。
ところが、それだけの早業のできる練達の剣士であった浅野内匠頭でありながら、浅野内匠頭は吉良上野介の額に浅く傷をつけただけです。
つまり浅野内匠頭に殺意はなかったということです。
吉良上野介を懲らしめようとしただけであったのです。
もし浅野内匠頭に殺意があったのなら、脇差しで首を狙うか、肋骨の間に刀身を水平に差し込んで殺害します。
仮に殺意を持って頭部を狙ったのなら、すくなくとも吉良上野介は額を割られているわけですから、渾身の力を込めて打ち下ろしたなら、吉良上野介は頭を二つに割られて即死しています。
後編に続く
引用 https://nezu3344.com/blog-entry-4724.html