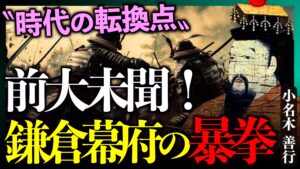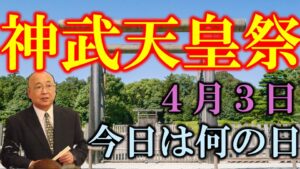坂東忠信氏が、日本国憲法前文を深く読み解き、現憲法が平和時を前提にしたものであることを解説。有事に備えた憲法整備の必要性を訴え、主権者としての国民の自覚と行動を促します。
◉ 憲法前文から読み解く「平和憲法」の限界
坂東忠信氏は、自らの警察学校時代の経験を交えつつ、日本国憲法前文を一文ずつ丁寧に読み解いていきます。憲法は、しばしば第9条ばかりが取り上げられますが、実はその根幹にあるのは「前文」であり、そこにこそ憲法の精神や価値観、国の理想が示されていると強調します。
前文の中では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」とあり、これは憲法が平和国家を前提にしていることの表れです。しかし現実には、平和を愛していない国家や、専制・隷従・圧迫・偏狭といった要素を持つ国も存在します。坂東氏は、そうした現実に直面したとき、この憲法だけでは国民の安全と生存を守ることは難しいと語ります。
また、政府の行為によって戦争の惨禍が再び起こることのないようにという文言に触れ、「戦争をしない」だけでなく、「戦争をしかけさせない」力を持つことの重要性にも言及します。さらに「主権は国民に存する」と明記されていることから、憲法解釈や改正に対する最終的な責任は、国民一人ひとりにあることも強調されます。
◉ 平和と有事、それぞれに対応する憲法を
現行憲法が平和憲法であるならば、有事を前提とした「有事憲法」もまた必要であるというのが坂東氏の主張です。岸田総理自身が「平和憲法」という言葉を用いていることを根拠に、現行憲法は平和時を前提とした法体系であるとし、有事の際には機能しない可能性が高いと指摘します。
では、有事憲法はどうやって整備すればよいのか。坂東氏は、「憲法は一国に一つでなければならない」とする明文規定が存在しない以上、平時用と有事用の二つの憲法が並立していても問題はないと述べます。むしろ、状況に応じてどちらの憲法を適用するかを切り替える体制こそが、真に現実的な国家運営につながると説きます。
さらに、憲法の改正手続きが非常にハードルの高いものである(全議席の3分の2)ことに対し、そもそも新しい憲法を「作る」ことに関しての明確な規定がないことを指摘し、改憲ではなく「並立」という形での有事憲法制定の道も十分に現実的であると語ります。
◉ 主権者としての自覚と「政治参加」の多様性
動画後半では、視聴者に対して強く呼びかけがなされます。「主権は国民にある」とする以上、政治は政治家だけに任せておくのではなく、私たち一人ひとりがその行方を見極め、選択し、時には声を上げなければならないと訴えます。
坂東氏は、投票だけが政治参加ではないとし、草の根で政治家を支援したり、正しい情報を発信したりと、様々な形で政治に関わることの大切さを説きます。保守の価値観を持ちながらも「平和憲法の精神を重んじる護憲派」としての立場を持つ坂東氏ならではの視点は、従来の「改憲か護憲か」という二項対立を超えた、新たな憲法論を示しているといえるでしょう。
さらに、既存の政党や政治家に対する厳しい批判も交えつつ、自らの信念に従って行動すること、そして次の選挙に向けて「誰を落とすべきか」「誰を通すべきか」を明確にすることが重要であると強く語ります。
最後には、「平和を愛する諸国民」に囲まれた前提が崩れた今、現行の憲法では国を守れないという危機感を共有し、未来のために有事憲法を整備することが急務であると締めくくられました。