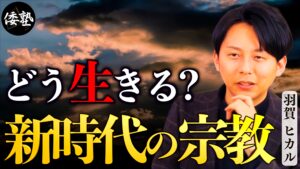徳川家康が征夷大将軍となった背景を軸に、江戸時代の特徴である「権力と金の分離」「広く人材を求める」「筋を通す」という三つの原則について解説し、現代にも通じるその意義を語ります。
徳川家康が築いた「江戸」の意味と志
1603年3月24日、徳川家康は征夷大将軍に任じられ、日本史における江戸時代が始まりました。家康は単に軍事力によって支配を行ったのではなく、「皇尊の大御宝(おおみたから)」としての民衆を尊び、彼らが安心して暮らせる社会の実現を目指しました。
江戸という土地も、あえて「汚れた土地(穢土)」とされた場所を選び、その名を変えずに活用したのは、「人々の力で極楽のような街を築く」という意志の表れでした。家康は江戸を人工的に整備し、全国から人材を集めて開かれた都市を築いたのです。
江戸時代を支えた三つの特徴
江戸時代が260年という長期の安定を実現できた背景には、次の三つの制度的特徴があります。
(1) 権力と金の分離
豊臣秀吉の時代は大阪経済一極集中で、財力が権力と直結していました。しかし家康は関ヶ原の戦いを機に、大阪経済からの独立を図り、生産国主体の体制に移行しました。
その後の江戸幕府では、財力のある大名が幕政の中心にはなれず、老中には石高の少ない譜代大名が就くなど、金と権力を明確に分けました。権力には責任が伴うが、財力には伴わない。この原則が社会の安定に寄与したのです。
(2) 広く人材を求める
家康のもとでは、身内や譜代に限らず、広く全国から人材が登用されました。町人や百姓の出身者でも、才能が認められれば要職に抜擢されることもありました。
これにより、閉鎖的な支配ではなく、柔軟で開かれた統治体制が形成されました。現代の政治にも通じる課題として、政党の枠を越えた有能な人材の登用が求められることを指摘しています。
(3) 筋を通す政治姿勢
江戸時代において重視された「筋」とは、筋書き=ストーリーを意味し、始めに立てた方針を一貫して貫く(通す)という姿勢です。
例えば家庭の中でのお弁当づくりにもストーリーがあり、そこには「子供への愛情」という筋が通っています。同じように、政治においても「民衆を豊かに安全に暮らさせる」という筋を通すことが重視されました。
現代においても、この「筋を通す」ことの重要性が改めて見直されるべきであると説かれています。
江戸時代が残した現代への教訓
260年にわたる平和を維持した江戸時代の知恵は、現代の日本社会にも大きな示唆を与えています。
例えば、財力を持つ者が権力をもつと横暴になりがちですが、それを防ぐ仕組みづくりが社会の安定には不可欠です。
また、広く人材を求める姿勢は、現代の政界にも必要な改革意識であり、私たち一人ひとりの生活にも「筋を通す」ことの大切さが反映されるべきだといえるでしょう。
この動画では、徳川家康の志と行動を通して、日本という国の在り方を再考し、現代に活かすべき精神的土台とは何かを掘り下げています。江戸時代のスタートにあたる3月24日という日を通して、私たちが見つめ直すべき価値観が浮き彫りにしてます。