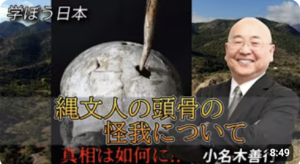自然農法に挑む水野氏が、日本農業の再生を語ります。抑草技術により無農薬農業が「なりわい」に転換可能に。有機給食の必要性や農薬の問題点を踏まえ、持続可能な農の未来を提言します。
◉ 革新の抑草技術がもたらす“なりわい”としての農業
今回の対談では、自然農法を実践する水野清重氏を迎え、日本農業の現状と未来について掘り下げました。舞台は埼玉県見沼区、江戸時代の干拓地を利用した広大な農地で、現在も活発な農業が行われています。
水野氏は、田んぼでの米作りだけでなく、ネギやソラマメなどの野菜栽培にも取り組んでおり、できるだけ自然に近い農法を実践中です。地方で育てられた無農薬野菜は、味も栄養価も市販品とはまったく異なり、特に自然栽培によるほうれん草の甘さは印象的です。
一方で、自然農法を実践する中では、収量減や雑草管理の難しさなど、従来農法とのギャップも存在します。しかし、それを乗り越える技術として注目されるのが「抑草技術」です。これは、除草剤や過度な機械作業に頼らず、田植えの段階で雑草の繁茂を抑える方法であり、有機栽培を現実的に可能にする鍵となります。
すでにこの技術を導入した観光農家では、年間400万円の赤字から、年収500万円の黒字化への道筋が見えてきており、大きな転換点となる可能性を秘めています。
◉ 日本の農薬依存と給食の現実
対談の中では、農薬がもたらす健康被害にも焦点が当てられました。特に「ネオニコチノイド系農薬」は神経毒として知られ、記憶障害・味覚障害・生殖機能低下など様々な悪影響が報告されています。欧米諸国では使用が禁止されている一方、日本では日常的に使われ続けており、学校給食を通じて子どもたちが日々摂取している実情も語られました。
実際に、有機食品を中心に食べていた子どもが、学校給食の開始と同時にアレルギー症状や集中力低下を起こす例も報告されており、「無償化」だけでなく「質」の向上が問われる時代に入っていることが示唆されました。
水野氏は「オーガニック給食」の導入を提案し、自治体の補助によって安全な食を提供する仕組みづくりの必要性を説いています。
◉ 自給・共助によるコミュニティ形成と農の未来
農業が“なりわい”として成り立ち、かつ消費者が安心して食を選べる社会を築くためには、生産者と消費者が直接つながる「地産地消」の仕組みが不可欠です。水野氏らが取り組むプロジェクトでは、志ある財団や支援者が現れ、農産物を買い支える仕組みが着実に整いつつあります。
この取り組みは「四方よし(生産者・消費者・自然環境・支援者)」を基本理念にしており、農薬に頼らない農業が、教育や健康、環境保全にまでつながるという好循環を生み出します。
さらに、水野氏は、国の「みどりの食料システム戦略(2050年までに有機農地面積25%)」にも触れ、民間の力で先行的なモデルを築き上げることの重要性を強調しました。
行政からの支援が少ない中でも、現場主導の自助・共助によって持続可能なコミュニティをつくり、日本の農業と食の未来を守っていくという強い意志が語られました。
*
自然農法は夢物語ではありません。
実践と技術、そして志ある人々の連携によって、「命を育てる」本来の農業が今、再び動き出しています。