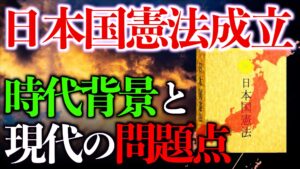前九年の役における義家と貞任の歌合戦は、単なるやり取りではなく、律令体制の崩壊と「天皇の民」を守る武士の気概を示す名場面。現代にも通じる日本精神が、そこに凝縮されています。
◉ 歴史に刻まれた「歌問答」の真実とは
永承6年(1051年)に始まった「前九年の役」は、陸奥の豪族・安倍一族が反乱を起こし、それを源義家(八幡太郎義家)が討伐するという戦でした。その中で語り継がれる名場面が、義家と安倍貞任との「歌問答」です。
戦場で貞任を追う義家が、弓を引きながら「衣のたてはほころびにけり」と詠んだのに対し、貞任は振り向いて「年を経し糸の乱れの苦しさに」と返しました。義家はこれを受けて弓を降ろし、貞任の命を助けたといいます。
近年の一部学説では、このやり取りを単に「古着だから衣が乱れていた」というやや軽薄なやり取りとして解釈するものもありますが、それではなぜこの場面が長く語り継がれてきたのかが説明できません。
◉ 歌に込められた「天皇の民」という思想
実際には、この歌問答は、日本的精神、すなわち「天皇の民」としての誇りと責任を背負った武士同士の、高度な思想のぶつかり合いなのです。
義家の「衣のたてはほころびにけり」は、「お前はもう死んでいる」と同義です。弓の名手である義家が貞任に狙いを定め、まさに今放とうとした一瞬。その言葉に、貞任は「年を経し糸の乱れの苦しさに」と返します。
この「糸の乱れ」とは、律令体制という日本の国家構造が長年の経過でほころび、民が苦しんでいるということを象徴しています。安倍貞任は、この乱れを正すために立ち上がった──そういうメッセージを和歌の上の句で即座に返したのです。
和歌とは、上の句と下の句が「三角形の二点」を成し、そこから第三の「意味(頂点)」を導き出す知的な技術です。貞任がこの技術を用いて、義家の放った「死」の宣言を、「律令体制の死」とすり替えたことで、意味は大きく変わりました。
◉ 義家が弓を下ろした本当の理由
この返歌により、義家自身が「律令体制の死」を認めることになってしまったのです。これは、義家にとって一軍の将として受け入れがたいはずの事態ですが、彼は弓を降ろします。
なぜか。それは、貞任が「天皇の民」のために戦っているという同じ志を持つ「武門の大将」だと見抜いたからです。義家もまた、民の安寧のために立ち上がる者。「俺と志は同じ」と理解した義家は、武士としての誇りと民への慈しみをもって、貞任を許したのです。
この場面が「歴史に残る名場面」とされるのは、単なる武勇や技巧の話ではなく、日本の根幹にある「シラス国」──支配や隷属ではなく、民を宝として共に生きるという日本人の精神そのものが現れているからです。
*
このような誇り高い歴史の瞬間を、現代の私たちがどう伝え、どう学んでいくかが問われています。日本の歴史を単なる事実の羅列ではなく、そこに込められた精神性まで読み解いていくことの大切さを、今一度見つめ直すべきではないでしょうか。