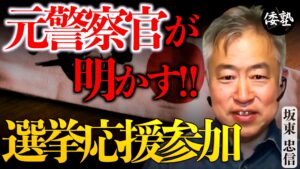江戸時代に「藩」という言葉はほとんど使われていなかったという事実と、新治県の廃止から見えてくる日本人の土地観・文化意識の変遷について解説しています。
◉ 「藩」は明治の造語だった?江戸時代の土地の呼び方
本動画では、まず「藩」という言葉が実は江戸時代には一般的ではなかったという事実から話が始まります。
私たちが「薩摩藩」「長州藩」と呼ぶ地域も、当時の人々は「島津家」「毛利家」など大名の家名で呼んでいました。また、地域自体も「○○領」「○○の国」といった呼び方が用いられており、現代で言う「県」に相当する感覚とは異なる、より文化的・精神的なつながりを大切にしていたのです。
明治新政府が「廃藩置県」と呼ぶ政策を行った際、「藩」という言葉をあえて採用した背景には、中央集権国家の構築という政治的意図がありました。藩という言葉自体、元は中国の「城塞国家」的な意味合いを持つ漢字で、日本の現実とは異なるイメージが導入されていたのです。
◉ 消えた新治県──神と産業が共存した理想郷
話題は1875年に廃止された「新治県(にいはりけん)」へと進みます。この新治県は、現在の茨城県と千葉県にまたがる地域に存在し、鹿島神宮・香取神宮・筑波山を含む、神聖さと自然、そして産業が調和した地域でした。醤油の産地としても有名で、県庁所在地は土浦に置かれていました。
新治という名前は、『古事記』で倭建命が詠んだ歌に登場する「邇比婆利(にひばり)」に由来し、古代の歴史と深く結びつく由緒ある地名です。
それが明治期の行政再編によって姿を消したのは、日本人の土地に対する感覚の変化、特に「名前の持つ意味」を軽視する流れがあったことを物語っています。
◉ 郷土という言霊──土地の名に宿る誇りと魂
江戸時代の人々は、自分の出身を「肥後の者でございます」や「播磨の生まれにて」と語り、土地の名に魂と誇りを込めて生きていたことが強調されます。その土地で採れた作物で自分の体ができている、という考え方すらあったほど、地域との結びつきは深かったのです。
これに対し、明治以降の行政単位である「県」は、そのような精神的つながりよりも、中央からの統治を前提とした制度であり、地方の自主性や多様性が奪われた側面もあります。
こうした流れの中で、地方の文化や経済が衰退し、中央偏重の政治体制が固定化されていったという問題提起もなされています。
◉ 日本の未来に活かすべき「古い呼び名」
終盤では、話は少し未来への提案へと展開します。
たとえば、日本の国体や憲法を見直すとき、行政単位の名前にも古い「国名」を復活させたらどうか?というアイデアが語られます。「埼玉県」ではなく「武蔵の国」と呼ぶ、「茨城県」ではなく「常陸の国」と呼ぶ──。そんな風に土地の魂を名前に込めていくことで、日本人のアイデンティティも再生できるのではないかという提案です。
名前には力があります。「国」という呼び方には、単なる地名以上に、言霊としての重みがある。
それを忘れたとき、私たちは大切な何かを見失ってしまう──そんな深いメッセージで締めくく
られています。