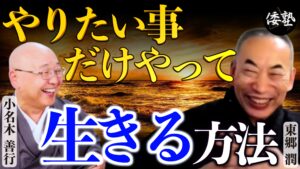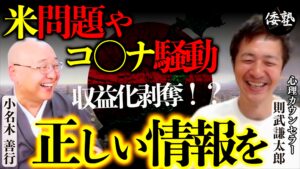地域農業を通じて町づくりと財政再建を進める新たな視点を提案。グローバリズムの限界を超え、「町民ファースト」の精神で持続可能な未来を築くための実践的アイデアを語り合います。
◉ グローバリズムの限界と「町民ファースト」の再評価
本対談では、現代のグローバリズムがもたらす社会の構造的問題に対して、日本がどのように自立し、地域を基盤とした経済活動に立ち返るべきかが議論されました。
グローバル経済の背後には「人間を人間として扱わない」思想があります。
それがかつての植民地主義や現代の支配構造に通じているといえます。
宇井氏は地域農業を軸とした「町民ファースト」のまちづくりこそが、こうした支配構造からの脱却につながると強調されました。
そのために、たとえば「地元で採れた無農薬野菜やお米を流通させ、地域内で経済が循環する仕組みをつくる」ことで、地元住民の生活の質を高め、持続可能な町の未来を実現するのです。
◉ 鎌倉・足利時代の歴史に学ぶ「土地経営」の本質
日本の歴史は、土地経営からはじまりました。
それは縄文弥生にとどまらず、鎌倉時代にも御家人たちが土地分割により没落した事例や、それに続く足利幕府による土地統合政策があります。
そしてそこには、「小規模に分断された土地では経済が成り立たず、まとめて経営することが持続可能性を生む」という視点がありました。
このことは現代の農業にも通じています。宇井氏は、
「小規模農家ではなく、ある程度規模をもった経営体として再編する」提案をされます。
土地を集約し、行政も巻き込んだ農業運営によって、町の経済基盤を再構築していくという発想です。
◉ 第三セクターを活用した「稼げる自治体」づくり
宇井氏は「農業を通じて自治体の歳入を増やし、行政サービスを拡充する」という革新的なビジョンを提示しています。その具体策の一つが、公務員と民間農家が協力して設立する「第三セクター」です。
行政が直接稼ぐことで、自治体財政を強化し、福祉・教育・インフラへの投資も可能になると述べました。
そもそも国や自治体が収益事業を行うことは本来あって然るべきものです。
明治時代に初めて導入された所得税や、戦後の消費税が本来の目的から外れてきた歴史からも、今後の
「税に頼らない自治体運営」
が理想なのです。
そして実際に、地域の農産物が都会の人々を惹きつけ、直売所が大繁盛する実例もすでに生まれています。
◉ 真の保守とは「人を愛すること」──地域を守る経済と思想
対談の終盤では、「保守」の本質についても語られました。
保守とは単に古いものを守るのではなく、
「人を愛し、地域を愛し、国を愛する」
姿勢に根ざすものです。
多様性やグローバリズムも否定されるべきではないけれど、
「自分たちの生活が犠牲になる形」での受け入れはおかしなことです。
そのために、まずは地元を立て直すことが第一です。
宇井氏の「町民ファースト」の発想は、この思想の現代的な実践例といえるでしょう。
日本はもともと持続可能な町づくり、国づくりを行ってきた国です。
地域において、地元の人が安心して食べて暮らせる環境を整えることこそ、地域自治の不可欠であり、それこそが次世代につなぐ「希望」です。