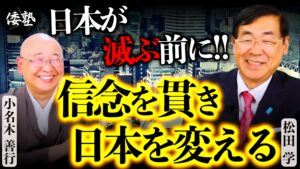「この国」という言葉の普及は、日本人の歴史観や国家観を分断させる意図で植え付けられたものでした。言葉の裏にある思想を見抜き、誇りある「わが国」の精神を取り戻す必要があります。
◉ なぜ「この国」と呼ぶのか──その背後にある思想構造
戦後の日本では、GHQの占領政策の一環として、日本人の国家観や歴史認識を意図的に変える言語操作が行われました。その代表例が「この国」という言葉の普及です。
この呼称は、戦前の日本を否定し、断絶させる「八月革命論」にもとづく左翼思想の延長線上にあります。左翼は共産主義史観──常に“新しいものが正しい”とする思想を信奉し、古き日本の価値観や道徳、宗教、文化を「遅れた過去」として排除してきました。
この「新しさ=正義」という単純思考は、時としてオウム真理教のような危険思想すら正当化する危うさを孕んでいます。そして「古い衣を脱ぎ捨てよう」というスローガンのもと、日本人自身が祖国を「この国」と呼ぶことが推奨されるようになったのです。
◉ 「わが国」と言うことの意味──歴史と誇りの回復
「この国」には帰属意識がありません。政治の話も、戦争の話も、悲劇の話も、すべてが“他人事”になります。こうして国民同士の絆は断たれ、「個」として分断された国民は、国家解体の対象にされてしまうのです。
それに対し「わが国」という言葉は、歴史や祖先への敬意、共同体意識、責任感、そして希望を含みます。日本は1万7千年の縄文以来、人が人を殺すことを否定する文化を築き、祖先たちは橋を架け、水道を整え、未来の世代のために尽力してきました。
そうした祖先への感謝と誇りが「わが国」には宿っているのです。
◉ 国は“誰のもの”か──政治も経済も「わが事」として引き受ける
現代日本でよく聞かれる「この国の政治はダメだ」というフレーズ。そこには自分と国家を切り離す無意識の構造があります。しかし、政治とは本来、国民の共同体全体の幸福のためにあるもの。自分の会社の経営者が無能で無責任であれば倒産するのと同じで、政治家のあり方も「わが国」の未来に直結する重大事です。
「この国」と言ってしまえば、政治や社会の問題は“他人事”になってしまいます。しかし「わが国」と認識すれば、それは“自分の問題”になります。これは単なる言葉遣いの問題ではなく、主体的に生きるか、傍観者として流されるかという、私たち一人ひとりの覚悟の問題でもあるのです。
◉ 結び──「わが国」として生きることが希望になる
司馬遼太郎の名著『この国のかたち』によって「この国」は常識語として日本中に広がりました。けれどその言葉に込められた意味と影響は、非常に深く、静かに人々の国家観を変えてきました。
「この国」と言えば、龍の姿をした日本列島は“他人のもの”になります。「わが国」と言えば、龍は私たちの命の一部となる──これは象徴的でありながらも、私たちの国との向き合い方を明確に示しています。
「わが国」と呼ぶことは、祖先への感謝、国家への責任、未来への希望のすべてを包含した、日本人としての生き方そのものです。
それは、たんなる言い換えではなく、日本再生の出発点なのです。