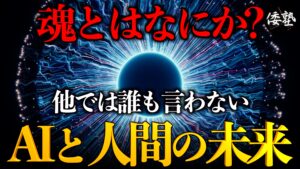お中元の本来の意味から、教育委員会の成り立ち、そして“かわいそうなぞう”の実話と創作の違いまでを縦横に語ります。事実に基づく歴史認識の大切さを問いかける一話です。
◆ お中元に込められた「生き残ること」への感謝の心
7月15日は「中元の日」。本来は「三元」のうちのひとつで、半年間無事に過ごせたことへの感謝と祖霊への供養の日でした。
江戸時代、武士たちは「半年間、生き延びることができた」ということに深い意味を見出し、それを支えてくれた上司や仲間への感謝として、贈り物を届ける風習が始まりました。
現代では単なる贈答習慣に思われがちなお中元ですが、そこには命の尊さと絆を大切にする日本人らしい精神文化が息づいていたのです。
武士とは「責めに任ずる者」であり、常に死と隣り合わせ。
その中で生き延びたこと、命を全うできたこと自体が、感謝の対象だったのです。
◆ 「教育委員会」の誕生と、自虐史観の根
もう一つの7月15日の出来事として、1948年に「教育委員会法」が施行されました。
これは公職追放で排除された“愛国的”な教師たちに代わり、占領政策に沿った教育を進める仕組みとして設置されたものです。
この制度によって「日本人は悪いことをした」「日本の軍隊は残酷だった」といったイメージを子どもたちに植え付ける教育が推し進められ、現在に至るまで続いています。
学校で本当の日本の歴史が教えられなくなったのは、まさにこの制度の結果なのです。
◆ 『かわいそうなぞう』の嘘と、本当にかわいそうだったのは誰か
多くの日本人が知っている童話『かわいそうなぞう』。
戦争中、空襲で動物が逃げ出すのを防ぐため、陸軍が命じて動物たちを殺処分したという物語です。
餓死させられたゾウたちの姿に、涙した方も多いでしょう。
しかし実際には、処分命令を出したのは陸軍ではなく、東京都知事の大達茂雄氏でした。
そしてその時期も、東京に空襲が始まる1年以上も前。
つまり、空襲に備えての“先手”だったのです。
しかも食糧事情が悪化し、猛獣への餌の確保が困難となったことも要因でした。
さらに、職員の中には餓死寸前のゾウにこっそり水を与えていた飼育係もいたという心温まる逸話も。
慰霊祭では職員たちが涙し、深く動物たちを悼んだのです。
創作の童話が人々の心を打つのは事実ですが、それを“事実”として教育し、プロパガンダとして利用することには問題があります。
戦争の悲惨さを伝えるにしても、創作と史実はきちんと区別されなければなりません。
◆ 真実を知ることで魂が響く時代へ
本当に心を打つのは、作られた悲しみではなく、人間と動物の絆の中にある“本当の感情”ではないでしょうか?
上野動物園の飼育係がどれほど苦しみ、涙を流していたか。
その姿こそが、私たちの魂に訴えかける“真実の重み”なのです。
創作は否定しない。
だが、事実に基づいた歴史を教えることで、子どもたちに真の教訓と魂の共鳴を与えたい。
嘘の物語で人を泣かせるよりも、真実が生む涙こそ、美しく清らかなものであるはずです。