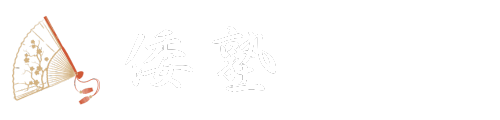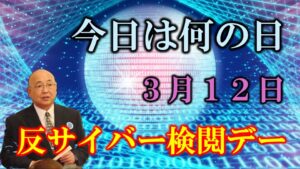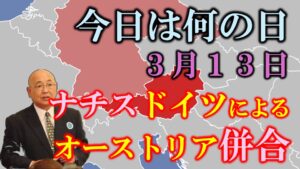SNS規制法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律)の問題点とその本質について解説。名誉権やプライバシーの保護を掲げる一方で、言論の自由が制限される危険性について議論。
(1)SNS規制法とは?その実態と問題点
政府が推進する「SNS規制法」は正式名称が極めて難解であり、一般人が内容を理解しにくい形で発表されています。これは従来のプロバイダ責任制限法の強化版であり、大手SNSプラットフォームの管理を厳しくするものです。しかし、報道では「情報流通プラットフォーム対処法」といった通称が使われ、実際の法律の全貌が分かりづらくなっています。
この法律の目的としては、個人の名誉権やプライバシー保護を掲げていますが、一方で、政府や大企業に都合の悪い情報が「虚偽情報」として削除される可能性が指摘されています。例えば、ワクチンの副作用に関する情報など、社会的に議論が必要な内容まで規制の対象になるかもしれません。
(2)SNS規制の対象と影響
この法律の規制対象は、一般の個人ではなく、大手SNSプラットフォームの運営会社です。例えば、YouTubeやX(旧Twitter)が、利用者の投稿内容を厳しく管理しなければならなくなり、問題のある投稿を迅速に削除する責務を負うことになります。
具体的には以下のようなケースが規制対象になります:
1 名誉毀損や侮辱行為
2 個人情報やプライバシーの侵害
3 デマや虚偽情報の拡散
4 児童ポルノや違法薬物取引の宣伝
5 違法な金融商品や詐欺の勧誘
一見すると、健全なインターネット空間を守るために必要な法律に思えます。しかし、ここで問題となるのが「虚偽情報」の定義です。政府や一部の大企業にとって不都合な情報が、恣意的に「虚偽」と認定され、削除される可能性があります。こうした運用がなされれば、国民の言論の自由が著しく制限される恐れがあります。
(3)法案成立の裏側と政治の現実
驚くべきことに、多くの国会議員がこの法案の正式名称すら理解していません。かつて「国籍法改正」の際にも、議員の多くが内容を把握しないまま賛成票を投じたという事実があります。今回のSNS規制法も同様に、深い議論がなされることなく可決される危険性があります。
また、問題の本質は、政府がなぜSNSを先に規制しようとしているのかという点です。テレビや新聞などの既存メディアは、一方的な情報を流し続けてきましたが、それに対する批判がSNSを通じて広がるようになりました。SNSが強くなるほど、政府やメディアの影響力が低下します。この法案が可決されれば、ネット上の情報発信が厳しく管理され、都合の悪い発言が削除される可能性が高まります。
(4)SNS規制の前に必要なこと
この問題に対処するためには、以下の点が必要です:
1. 国民の政治への関心を高めること
国会で何が決まっているのか、誰がどのような意図で法案を推進しているのかをしっかり監視する必要があります。法律の詳細を知らないまま支持する議員を減らし、きちんと議論を尽くす政治家を増やさなければなりません。
2. 既存メディアの改革
NHKや民放テレビ局などが、国民に必要な情報を提供するのではなく、一部の利権団体の利益を優先している状況が続いています。公共放送としての役割を果たしていないメディアに対する監視を強めるべきです。
3. 言論の自由と責任のバランスを取る
誹謗中傷やデマの拡散は確かに問題ですが、一方で政府の意向によって言論が制限されることは避けなければなりません。そのためには、独立した機関が公正に監視する体制を整える必要があります。
(5)まとめ
SNS規制法は、一見するとネット空間を健全化するための法律に思えます。しかし、その背後には政府による情報統制の可能性が潜んでいます。法律の名前を難しくすることで国民の目を欺き、十分な議論なしに通過させることが恒常化しています。
この問題を解決するためには、国民一人ひとりが政治に関心を持ち、議員の動きを監視することが重要です。SNSを規制する前に、まず既存メディアが公正な情報を提供する義務を果たすべきではないでしょうか。
今回の動画では、坂東忠信氏がこの法案の本質と問題点を鋭く解説しています。ぜひ、多くの人に共有し、考えるきっかけにしていただければと思います。