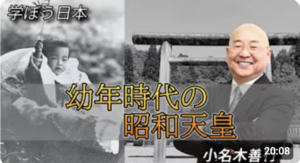日本の米農家は高齢化と赤字経営により、絶滅の危機に直面しています。元金融マンの水野清重氏が実体験をもとに、持続可能な農業への道を探ります。米価高騰の裏側と再生への鍵とは?
■ 日本の米農家は“絶滅危惧種”の状態にあります
日本の農業、とりわけ米農家は今、深刻な危機に瀕しています。平均年齢は70歳近く、農家全体の8割以上が60歳以上で占められており、若手の後継者はほぼゼロという状況です。特に稲作農家では、実に9割が60歳以上という統計もあり、農業人口は減少の一途をたどっています。
さらに、農業の収益性が極めて低いことも深刻です。小規模農家の多くが「時給10円」「年収1万円」といった採算割れの状態で経営しており、これでは新規就農者が増えるはずもありません。農業を職業として続けるには経済合理性が乏しく、多くの農家が赤字で働いているというのが現実です。
■ 米価高騰の背景と、それでも変わらない赤字構造
近年、いわゆる“令和の米騒動”によって米価は一時的に上昇しました。店頭では5キロ2000円だった米が4000円になるなど、消費者にも衝撃が広がりました。しかし、米価の上昇にも関わらず、農家の赤字は改善していません。
その理由は、肥料代や燃料費などのコストが急上昇しているためです。特に農薬を使用する慣行農法では、土壌が痩せ、生産の持続性が損なわれていることも問題です。農薬の使用が前提となった農業構造は、今や限界を迎えつつあると言えるでしょう。
水野氏はこの現状を「赤字前提の経済構造」と指摘し、農業が本来の“なりわい”として成り立たない構造に強い危機感を示しています。
■ 有機農業という希望と、持続可能な未来への挑戦
そんな中、水野氏が注目するのが「有機農業」への転換です。除草剤を使わず、深水管理や代かきの技術、循環型有機微生物の活用などによって、雑草を抑えつつ土壌を健康に保つ方法を実践しています。この方法により、農薬なしでも草の発生を抑えることが可能となり、持続可能な農業への道が開けつつあるのです。
とはいえ、すぐに収益が安定するわけではありません。現在、水野氏の農地規模は1.5ヘクタールで、まだ赤字経営が続いていますが、3ヘクタール以上の規模を目指すことで年間所得500万円程度を確保できる可能性があると試算しています。
この取り組みが成功すれば、農業を“食える仕事”として成立させ、後継者問題の解決にもつながると期待されています。
水野氏の挑戦は、「ピンチをチャンスに変える」具体的な一歩です。
絶望的に見える日本農業の未来にも、実は希望の芽があるのだと気づかされる内容となっています。次回の配信では、さらに深くこのテーマに迫る予定です。農業に関心のある方はもちろん、日本の未来を考えるすべての方にご覧いただきたい回です。