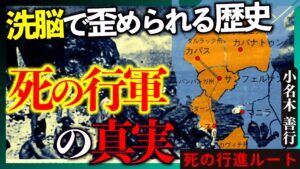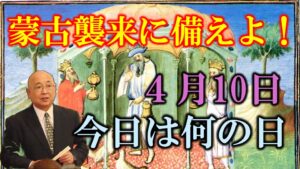坂東忠信先生が、自作の甲冑や刀を通して日本の甲冑文化とその実用性について語ります。制作過程、素材の工夫、地域ごとの違いなど、5月人形の背景にあるリアルな歴史が満載です。
◉ 手作り甲冑に見る「実戦」の知恵と歴史
坂東先生は、自ら叩いて作った甲冑や刀、さらには自作の鞘や柄などについて、素材選びから構造、制作方法まで細やかに語ります。例えば、鞘には水牛の角を使い、ご飯粒を糊にして部品を接着するなど、まるで昔の武士たちが実際に行っていた方法を再現。また、兜に獣毛を貼る理由として「弾の反射」や「夏場の熱対策」など、当時の環境に即した工夫があったことが紹介されました。
甲冑の形や機能は、戦う地域や敵の武器に応じて進化してきました。伊達家の62間筋兜や井伊家の赤備えなど、藩による特色も多彩。さらに、着脱しやすさや衝撃吸収のための工夫など、ただの「飾り物」ではない実戦用の機能美が随所に現れています。
◉ 5月人形の「飾り」に込められたリアリズム
5月人形を飾る際、どちらを前にするかという話題にも触れ、「正面」とされる向きに正解はないことが語られます。戦国武将・黒田長政のように「すぐに抜刀できる配置」にする者もいれば、美しさを重視して飾る者もいたように、目的に応じて配置が変化していたのです。
また、飾り金具の有無や素材の違い、持ち運びやすさの観点からの構造変化にも触れられ、「現代のレプリカ」と「実戦用甲冑」の差異についても考察。戦場での実用性を考えればこその機能が、デザインにも大きく反映されていることが分かります。
◉ 戦国武士の美意識と実用性──刀、槍、陣羽織の意味
刀の柄の巻き方や目貫の配置、さらには槍の構造に至るまで、すべてに理由と工夫があります。柄のぐるぐる巻きは汗や血の影響を最小限にするため、また槍の“血止まり”の工夫なども紹介されました。さらに、夏場の加熱に対抗するための陣羽織や獣毛など、熱中症対策にもつながる知恵も披露されます。
また、兜の装飾(前立・後立)は、戦場で目立ち、手柄を示すためのものであり、単なる装飾品ではありません。戦国時代の戦いの実情──草深い地形や、槍・刀・鉄砲といった武器の進化に応じた工夫が、甲冑や装備の形を決定づけていきました。