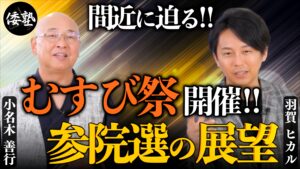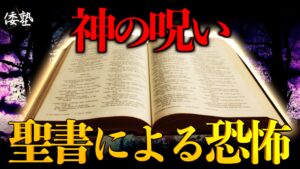660年の百済滅亡と宮女たちの殉死、993年の菅原道真追贈、京アニ事件など、7月18日の出来事を通じて、日本と朝鮮半島の関係、国防と倫理の在り方について深く掘り下げます。
【百済滅亡と「落花岩」の悲劇──命よりも誇りを守った女性たち】
西暦660年、唐と新羅の連合軍によって百済が滅ぼされました。
この日、百済王朝の宮女たちは「落花岩」と呼ばれる断崖から次々と身を投げ、死をもって尊厳を守ったと伝えられています。
その様子は、韓国の皐蘭寺(コランサ)の壁画に記録され、当時の気高さと誇りが今に伝わります。
百済の人々は、目鼻立ちがはっきりした容貌や礼節正しい文化を持ち、日本社会にも自然に溶け込んだとされています。
一方、新羅系の人々は隔離された特区に住まわされることが多く、その振る舞いの差異が当時の対応に表れていました。
このエピソードは単なる歴史の一場面ではなく、「国の防衛を怠ることでいかに民衆が悲劇に巻き込まれるか」という教訓でもあります。
百済は日本との深いつながりを持ちながらも国防を軽視し、それが滅亡につながったのです。ここから私たちは、真の国防とは何かを学ぶことができます。
【京都アニメーション事件と「背景を問う」日本の倫理観】
2019年、京都アニメーション放火殺人事件が発生し、36名の命が奪われました。
この事件は日本のアニメ文化に大きな衝撃を与えたのみならず、反日的勢力による文化支配の一端とも捉えられました。
事件後、他国製のアニメ作品が台頭し、日本発アニメの地位が揺らいでいく現実がありました。
この事件をどう受け止めるかについて、小名木氏は「実行犯」だけに焦点を当てる西洋式の個別責任ではなく、「背後にある構造や操る存在」にまで目を向ける必要があると指摘します。
日本古来の刑法思想は「関係責任」──つまり、背後に潜む悪意まで断つという考えに基づいており、そこに国家としての倫理的基盤があると述べられました。
【歴史の中の国防──対馬の神官や菅原道真公の行動に学ぶ】
1419年の「応永の外寇」では、朝鮮半島からの侵攻に対し、対馬の宗氏が20倍の敵を撃退したエピソードが語られました。
これは、単に武力だけでなく「責任感と信念」が勝敗を分けた象徴であり、日本の武士道精神のルーツにも通じるものです。
また、993年に正一位と左大臣を追贈された菅原道真公は、外国人労働者の過剰受け入れによる社会不安に警鐘を鳴らし、民を守る政治を貫いた人物として紹介されました。
「神のまにまに」、つまり神意に従う政治という道真公の姿勢は、現代に通じる国家倫理の原型といえます。
【光化学スモッグと“見えない脅威”への対応】
1970年7月18日、東京都杉並区で日本初の光化学スモッグ被害が発生しました。
大気中の窒素酸化物と紫外線の反応により有害なオゾンが発生し、生徒たちが体調不良に陥ったのです。
これは日本の公害対策の出発点となり、環境問題への意識が国民に広がる契機となりました。
このような「見えない脅威」への対応もまた、「国を守る」ことの一環であると語られます。
防災、治安、環境管理──それらすべてが民の暮らしを守る“現代の国防”なのです。
🎯まとめ
7月18日には、古代の百済滅亡から近年のアニメーション事件、公害問題に至るまで、さまざまな歴史の節目が刻まれています。
そこに共通するのは、「国をどう守るのか」という根本的な問いです。
国防とは単に武器を持つことではなく、文化を守り、民を守り、未来を育むこと。
その多面的な視点から私たちの生きる今を照らし出します。
どうぞこの機会に、「国家とは何か」「守るとはどういうことか」──一緒に考えてみませんか?😊🇯🇵