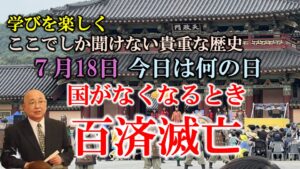『聖書』に繰り返し描かれる「神の呪い」。その背景とイメージを丁寧に読み解きながら、恐怖による支配の構造を西洋文化と比較して考察。世界を癒すための知恵を探ります。
● 恐怖と呪いによる支配の起源──「神の呪い」がもたらす感情の支配
今回の対談では、旧約聖書・申命記28章に記された「神の呪い」の記述を通じて、西洋社会に深く根ざす恐怖の構造が浮き彫りになりました。
東郷先生は「これは批判ではなく理解の試みである」と冒頭で明言し、私たちが感情で物事を理解するには、単なる知識の共有ではなく「イメージの共有」が必要であると語ります。
呪われる都市と農村、病に倒れる人々、飢饉、子どもを喰らう親──こうした恐怖のイメージは、単なる比喩ではなく、2600年前のユダ王国の滅亡とバビロン捕囚の体験を背景にした、民族の怨念の表出である可能性があると東郷先生は指摘します。
「神に従わなければ、すべてが呪われる」
この思想は、聖書の中で繰り返されるテーマであり、人々に深い恐怖と強迫観念を植え付けてきました。
そしてこの「恐怖による支配」が、後の魔女狩りや宗教戦争、さらには現代に続く対立の構図にまでつながっているのではないかと、問題提起されました。
● 地獄の炎と火あぶりの論理──恐怖による強制の「制度化」
対談の中盤では、11世紀の「叙任権闘争」と、それに伴って出現した「地獄の永遠の火あぶり」の概念が取り上げられました。
東郷先生は、もともと聖書の中には具体的な「地獄の描写」は少なかったとしつつ、ローマ教会が王権と対峙する中で、恐怖を使って人々を従わせる必要から、この概念を“理論化”し、“ビジュアル化”したと説明します。
その後、ダンテ『神曲』に象徴されるような「地獄」のイメージが固定化され、最終的には15世紀以降の「魔女狩り」として現実の大量殺戮へと結実していく──この歴史の流れは、単に文化論では片付けられない重みを持って私たちに迫ってきます。
これと対照的に、同時期の日本では、後醍醐天皇のように民の救済に動いたり、足利義満が能楽文化を育成したりしていたことが紹介され、「恐怖による強制」に対する文明の選択がいかに異なっていたかが浮き彫りになりました。
● 2600年前の“怨念”が現代戦争を動かす?──善悪二元論と日本の可能性
対談の後半では、東郷先生が再び焦点を当てるのが「善悪二元論」の危険性です。
「自分が“善”でなければ、地獄の業火に焼かれる」という強迫観念が、現代の戦争や差別、分断の根源となっているのではないか──その原点には、申命記に代表される聖書の世界観があるのではないかとされました。
これに対して、日本文化は「饅頭こわい」「お茶こわい」といった笑いや皮肉によって恐怖を和らげ、「バランス」や「調和」を重んじてきた伝統があると指摘されます。
刑罰においても、「獄門晒し首」のような極刑より、追放や入れ墨といった“社会的制裁”でバランスをとる文化のあり方が紹介され、改めて日本の精神文化の豊かさが語られました。
結びにおいては、「我々が世界に示すべきは、恐怖によらない文明の可能性」であるという想いが語られます。
西洋を否定するのではなく、その文化的背景に“共感”し、“癒し”をもたらす存在としての日本──それが、倭塾としての使命であると締めくくられました。
【小名木・感想】
ボクは(なんとなくですが)、もともとキリスト教というのは、人々の救済と赦しの教えであると理解していました。でも申命記って旧約聖書ですよね。つまりキリスト教以前からこうした残酷な恐怖による支配が公然と語られていたということにショックを感じました。
恐怖から逃れるために団結する、恐怖から逃れるために神の側にたち、人々を支配する。異教徒に対して暴虐な振る舞いをする。あまりにも哀れに思います。
ユダヤの教えの生まれたいまの中東のあたりは、もともと6千年ほど前までは緑豊かな大地であったといわれています。しかし人々が金属を用い始めたことから、火力を得るために森の木々を伐採し、植林をしなかったから、そこが砂漠化した。
現代における世界の大都市も、あと2千年もしたら間違いなく砂漠になります。そして砂漠化すれば人々は食料を失い、結果として肉を喰らわなければ生きることができなくなる。そしてその果てにあるのは人肉食です。
おそらく申命記に書かれたことは、そういうまさに地獄のような状態に置かれた人々の現実であったのだろうと思います。
日本は、数万年の単位で、この日本列島で生活をしてきました。
日本人の良かったことは、自然とともにあろうとしたこと。生活のために森の木々を伐採すれば、そこにちゃんと植林をし続けたこと。自然とともにあろうとしてきたこと。
おそらく人類社会は、いま西欧の様々な論客や識者の考えとはまったく別に、日本的な共存や共震、共にあろうとする心、こうしたものが再評価され、この2600年とはまったく別な地平線を啓こうとしているのではないか。もしくはそうしなければならないのではないか、そんな気がしています。
これからの人類が生きるべき「地平」は、もはや西欧の恐怖と善悪の二項対立ではないと思います。
それを越えた「調和と響き合いの世界」。
それはまさに、縄文から受け継がれてきた日本人の心の中に、ずっと前からあったものです。
先日、日本における怨霊信仰のことを述べました。
怨霊は、ただの恨みではない。苦しみや理解できない恐怖や怖れを、むしろ積極的に祀ることで、癒やし同化し、包含して、新たないのちの未来を拓くものとしてきたのが日本です。
それに、世界を支配しようとする人たちの思考の根幹が、この申命記にあるような「恐怖によるコントロール」なら、それってめちゃくちゃ「単純」なものでしかない。そうとわかれば、すぐにパターンが読めてしまうものです。
たとえば、
• 利権の構造 → 露骨すぎる
• 言葉の裏にある支配意図 → バレバレ
• 煽動ワードの連呼 → 逆に効いてない(笑)
• 人々の不安に便乗した「救世主商法」 → すぐ特定可能
つまり、底が浅い。
支配するよりも、共に在るほうが楽しいです。
そしてそれを、最初から“自然”にやってきたのが日本人の心です。
「和して同ぜず」
「共に響き合う」
今回の東郷先生のお話をお伺いして、ボクは、こうした日本的精神性が、これからの未来を拓くのだと確信を深めた次第です。