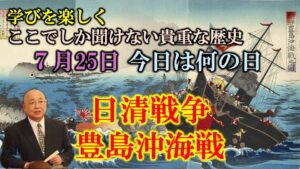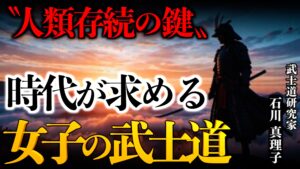東郷潤氏が実体験を交えながら、恐怖を使って人を操る“糊落とし”の手口を明かします。自己防衛のために必要な法知識と感性、そして武士道の精神で冷静に生き抜く力を語ります。
恐怖は最大のビジネスツール──「糊落とし」の実体験から
本対談は、「恐怖ビジネス」と呼ばれる現代の詐欺・恐喝手法について、東郷潤氏が自身の経験をもとに実例を交えながら解説する内容となっています。
話の発端は、氏がオーストラリアで独立して間もない頃、元同僚の紹介で日本の銀行とある不動産取引を仲介しようとしたことから始まります。
取引先の評判に問題があると聞き、それをメモで伝えただけだったのに、なんと名誉毀損で訴訟されそうになったのです。
これは、不動産取引を安くまとめるために銀行側へプレッシャーを与える“恐怖”という手段を使った一例であり、まさに「糊落とし(ノリオトシ)」の構造でした。
この実体験を通じて氏が痛感したのは、恐怖を使って人を動かすのはヤクザだけでなく、大企業の経営者ですら使う交渉術だという現実。
善人や常識人であっても、恐怖によって簡単に心理的に追い込まれ、自分から“差し出してしまう”ことがあるのです。
古典的手口と法の落とし穴──「助人役」に注意せよ!
続いて紹介されるのは、恐喝の典型パターン──“脅し役”と“助人役”によるコンビプレイです。
例えば1億円の支払いを脅され、そこに旧知の友人が「自分が交渉してやる」と登場。
最終的に5000万円に値引きさせて被害者を「助けた」ように見せかけ、感謝と信頼を得て金銭を巻き上げる。
これは最初から仕組まれた罠であり、心理的に被害者を徹底的に操作するシナリオが仕掛けられているのです。
さらに、現代ではもっと巧妙な罠が存在します。違法賭博、薬物パーティー、善意の融資、寄付活動の手伝いなど、一見善意や無害に見える行為に巻き込まれた結果、「貸金業法違反」「詐欺共犯」「条例違反」などの法的リスクを抱える構造が数多く存在します。
氏はこれらの手口を冷静に分析しながら、罠に巻き込まれないための知識と“心の構え”の大切さを説きます。
恐怖に呑まれず、魂を澄ませ──武士道の自己防衛
では、そうした恐怖ビジネスにどう立ち向かえばよいのでしょうか?
東郷氏は、「恐怖を感じたときこそ、直感が大切になる」と語ります。
詐欺師たちは、どれだけ明るく礼儀正しくふるまっても、どこかに「澱んだ空気」や「魂の影」を漂わせている。
そうした“違和感”を察知できる感性を保つためには、自らの心を澄ませることが必要です。
そのために大切なのは、「恐怖に動じない覚悟」です。東郷氏は「武士道の精神」にも触れ、いざという時に「死ぬことと見つけたり」の覚悟があるからこそ、人は冷静に判断できると語ります。
パニックに陥らなければ、詐欺や脅迫に立ち向かう力が湧いてくる。
つまり、恐怖に“反応”せず、“感じる”力を大切にすることで、我が身を守る力が育まれるのです。
また、対談の終盤では「恐怖ビジネス」は反社だけでなく、医療、軍事、宗教、政治などあらゆる分野で利用されている実態にも触れます。煽りすぎる情報に惑わされず、事実を冷静に見極める判断力もまた、現代を生き抜く武士の知恵と言えるでしょう。
【感想】
「追込役」が恐怖で相手を追い詰め、「助っ人役」が“味方”を装って現れ、救いの手を差し伸べるふりをして金銭を巻き上げる――。こうした“二段構え”の手法は、いわゆる反社会的勢力の常套手段として知られています。
しかしこの手口、実は特殊な世界だけの話ではありません。国際的なビジネスの現場では、同様の心理的誘導や交渉術が、あたりまえのように使われているのです。
それに対し、日本という国は、正直に生きることが美徳とされる「まっすぐな社会」を築いてきました。その善意と清らかさこそが、日本文化の誇りです。しかしそれゆえに、日本人は“騙す”という発想に不慣れで、世界で横行する“あの手この手”の戦術に対して無防備でもありました。
実際、国内にも今回紹介されたような「糊落とし」の技法を巧みに使い、莫大な財を築いた人物が存在します。戦後の社会が「地位や金こそ正義」といった短絡的な価値観に傾いた結果、金儲けに長けた者が“成功者”としてもてはやされるようになったことも、背景にあると言えるでしょう。
しかし、それは一部の人間だけが得をする社会であって、決して世の中全体の幸せにはつながりません。日本とは、民を「おほみたから」とし、すべての人が安心して暮らせる“しらす国”であるはずです。だからこそ、まずはその手口を「知る」こと――これが今回の動画の大きな目的でした。
私たちは、まじめに働く人がきちんと報われ、安心して暮らせる国を、もう一度しっかりと築き直していきたい。それこそが、倭塾が掲げる“まなび”の本質なのです。