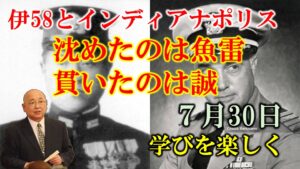富士山の名前に込められたさまざまな説や古代の記録、781年の最古の噴火、そして現代の予言騒動や自然災害への備えまで、多角的に語られる1時間。日本の自然と文化の奥深さに触れる貴重な内容です。
🌄 富士山の名前と噴火の記憶──日本人の心に生きる“ひとつらなり”の精神
【1】「富士山」という名前に込められた日本人の感性
日本一の山、富士山──その名前の由来には、さまざまな説が伝えられています。
まず有名なのが、『竹取物語』に登場する「不死山(ふじのやま)」説です。かぐや姫が天に帰る際、帝が不老不死の薬を焼いた山、それが「富士山」だとするロマンあふれる伝承です。
次に、「不尽山(ふじんさん)」説。これは「雪が尽きない」「美しさが永遠に尽きない」といった意味で、山頂に年中雪を頂く富士山にふさわしい命名です。
また、アイヌ語の「フチ(huci)」=火の神に由来する説もあります。古代の火山信仰と重なり合うこの解釈は、富士山が火の霊峰として敬われてきた背景とも合致します。
さらに、「ふ=秀でる」「じ=士・山」とする大和言葉由来説では、「富士」とは「偉大な山」「秀でた山」を意味し、日本人の自然観や言霊の力が反映されているともいえます。
つまり、富士山という名前そのものが、日本人が自然に対して抱いてきた畏敬、感動、祈りの結晶なのです。
【2】富士山の噴火記録とその地質的な変遷
歴史資料に残る最古の富士山噴火は、781年(天応元年)の『続日本紀』に記されています。この年、朝廷が「富士山の噴火に伴い火山灰が広く降った」ことを正式に記録しました。
その後の三大噴火として知られているのが、
• 延暦の噴火(800〜802年)
• 貞観の噴火(864〜866年)
• 宝永の噴火(1707年)
とくに宝永噴火では上空に巻き上がった火山灰が日照を遮り、冷夏と飢饉を招きました。自然の猛威がいかに人々の暮らしに影響を与えたかがよくわかる事例です。
また地質学的には、富士山の原型は10万年前に「小御岳」など複数の小山として形成され、1万年前の縄文時代に現在の円錐型の富士山が完成しました。このように富士山は、比較的新しい火山でありながら、私たちの精神文化に深く根ざす存在となっているのです。
【3】歴史をどう語るか──対立ではなく、“ひとつらなり”の視点を
ここで私は、歴史の語り方について一つの大切な視点をお伝えしました。
歴史において「事実」は証拠に基づいて追求されるべきですが、「ストーリー」は語り手の心によって異なるものです。
そして、その語られ方には、その人の性格や人生観までもが現れます。
たとえば、歴史を常に「征服」や「戦争」、「支配・被支配」の枠組みで捉える傾向があります。
しかし私は、それに強い疑問を持っています。
日本列島の各地にあった「国々」──たとえば駿河、甲斐、出雲、琉球、蝦夷(えみし)などは、けっして「異民族同士の対立関係」ではなく、長い年月のなかで血縁的に深くつながった“ひとつらなり”の親族関係だったのではないかと考えます。
実際、各地の豪族や国造たちは、「我が家は◯◯天皇の末裔である」という誇りをもち、天皇家を中心とした精神的ネットワークを築いてきました。たとえば沖縄(琉球)や北海道(アイヌ)も、本来は対立していたのではなく、地理的・文化的に異なりながらも、日本という大きな家族の一員だったはずです。
それが戦後の分断的教育や「対立構造」を描く歴史観によって、「征服された少数民族」として語られるようになった。この風潮には注意が必要です。
【4】希望をもって歴史と未来をつなぐために
富士山の話題から始まり、アイヌ語や駿河国の語源、さらには旧暦の「予言」騒動にまで話が広がった今回の放送。しかしその根底に流れていたのは、「いま一度、私たちはどんな歴史観で未来を創っていくのか?」という問いかけです。
富士山という山は、火山という自然の力の象徴であると同時に、日本人の精神性、美意識、そして共同体意識を体現する存在でもあります。
大きな噴火の記録を忘れず、過去の教訓を備えとして受け止めながらも、私たちの歴史を「争いの記録」としてではなく、「共に助け合い、乗り越えてきた物語」として語っていきたい。
富士山の静かな佇まいを見つめながら、そんな思いをあらためて強くした次第です。