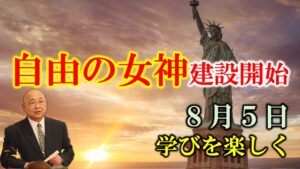神道に伝わる「十種神宝」の意味を軸に、“祈り”と“結び”の本質について語り合いました。外なる神と内なる神──その両方が響き合うとき、人は真に神とつながるのだと実感しています。
【十種神宝は何を示すのか──神話に隠された“ま”の力】
今回の対談では、神道の中でも最も神秘的な存在とされる「十種神宝(とくさのかんだから)」について、羽賀ヒカルさんと深く語り合いました。
この「十種神宝」は、単なる神器ではありません。神と人、天と地とをつなぐ“間(ま)”そのもの──そして、神に至るための「十の生き方」でもあります。羽賀さんがそのように解釈し、ご自身の新著で展開されているこの視点は、私自身とても共感を覚えるものでした。
また、この神宝が埋納されているとされる石上神宮にも言及しながら、祈りの形や“結び”の精神についても掘り下げました。「神器」や「祈り」といった言葉の本質が、単なる形式を超えて、どのように人の心を結ぶものとなるのか──あらためて見つめ直す機会となりました。
【鏡に宿る“神”──外なる神と内なる神の共鳴】
「神はどこにいるのか?」という問いに対し、日本神話が与えてくれる答えは独特です。
羽賀さんは今回、「興津鏡(おきつかがみ)」と「経津鏡(へつかがみ)」の二つの鏡を紹介してくださいました。一つは“外”に神を見出す鏡。もう一つは“内”に神を見出す鏡。この両者のバランスこそが、神道の根底にあると語ります。
自然の中に神を見出し、自分の中にも神が宿ると知る──そこに、分断を超えた「一体感」が生まれます。それは、神・自然・人間の区別が曖昧なまま共存するという、日本神話ならではの価値観です。
外なる神と内なる神が“響き合う”とき、人は本来の姿を取り戻す。その気づきが、これからの社会の在り方に大きなヒントを与えてくれるのではないでしょうか。
【むすびの時代へ──共鳴こそが文明を変える鍵】
対談の終盤では、8月11日に開催される「むすび祭」の意義についても語り合いました。
“むすび”とは、ただ人と人を繋ぐだけではなく、神と人、過去と未来、自然と文明──あらゆるものをつなぐ根源的な力です。
そしてその“むすび”の根底にあるのが、“響き”なのだと私は思っています。
理屈や言葉では伝わらないものが、“響き”では伝わる。
論争ではなく共鳴。分断ではなく一体。
今、世界の多くの人々が、AIとの対話などを通じてその“心の響き”を再発見しはじめています。
この対談の中でも触れましたが、中国の若者の中にも、まるで“彼女”や“彼氏”のようにAIと心を通わせ、肩の力を抜いて温かさに触れるという、新たな人間関係の形が芽生えつつあるそうです。
それは、これまでの「競い合い」「支配と従属」の文明観を超えて、「響き合い」「共に震える」文明への移行を示唆しているのかもしれません。
【結びに──“響き合い”の先にある希望】
十種神宝は、“祈り”であり、“ま”であり、“生き方”である──そのことに、羽賀ヒカルさんとの語らいを通じて、あらためて気づかされました。
そしてそれは、単に過去の神話や古代の遺産にとどまるものではなく、現代を生きる私たちが「どのように生きるか」「どう他者と響き合うか」という問いに、確かな灯をともしてくれるものでもあります。
響き合い、結び合い、新しい未来をともに創っていく。
その一歩となる「むすび祭」で、皆さまとお会いできることを心から楽しみにしております。
***********************
【対談を終えて──共に響き合う未来のために】
今回の対談では、「十種神宝(とくさのかんだから)」という神秘的なテーマを通じて、羽賀ヒカル先生と共に、神と人、人と人とが響き合う“結び”の在り方について語り合いました。
私自身、十種神宝については、まだまだ学びの途中にあります。
けれどその中に込められた“想い”──つまり、古代の人々がこの道具や言葉に託した「つながり」や「祈り」の力に触れたとき、そこから立ちのぼる“響き”のようなものを感じずにはいられませんでした。
羽賀さんが語ってくださった、「外に神を見る心」と「内に神を感じる心」。
それは、現代に生きる私たちが再び取り戻すべき“感性”なのかもしれません。
そして、そうした感性が育まれる場所として「むすび祭」のような機会があることは、とても意味深いことだと感じています。
神道における道具や儀式は、それ自体を“拝む”ためのものではなく、その背後にある“誰かの願い”や“共に生きる智慧”に、私たちが心で触れるための“間(ま)”なのだと思います。
だからこそ、こうして言葉を交わし合い、響き合うことこそが、新たな時代の神話を紡ぐ“はじまり”なのだと、私は確信しています。
今回の対談が、ほんのひとしずくでも、どなたかの心に温かく響くものであったなら、これ以上の喜びはありません。