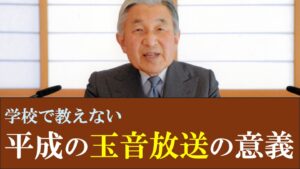60年間も下がり続けた日本の食料自給率。その背後にある構造的問題と、打開策としての「10年備蓄」の必要性について、歴史的視点と国際情勢を交えて語りました。
食料自給率が下がり続けた「不可解な60年」
子どもの頃、小学校の授業で「日本は食料自給率が低いから、将来飢餓になるかもしれない」と教えられた記憶があります。あれから60年、政治家もメディアも専門家も「食料自給率を上げよう」と言い続けてきたにもかかわらず、現実には一貫して下がり続け、現在では38%前後にまで落ち込んでいます。
この現象をどう考えるべきか──東郷先生は、これは構造的な問題であり、日本が実質的に独立国ではなく、アメリカの戦略的経済圏の中で動かされている結果であると指摘されました。つまり、日本が食料自給率を上げるということは、アメリカの農産物輸出に逆行するものであり、日米関係の根幹に関わる問題だというのです。
八郎潟と「農業エリート」への裏切り
戦後、政府は食糧難を解決するため、秋田の八郎潟に広大な干拓地を作り、全国から志ある農家を募りました。厳しい試験と選抜を経て選ばれた農家には、当時としては最新鋭の住環境が提供され、国家事業としての威信をかけた農業政策が始まります。
ところが、数年後、アメリカからの圧力により「米の自給は不要」とされ、農家には「出て行け」と通告されました。自給率を上げるために志を持って集った農家が、突然「国賊」とまで呼ばれるような扱いを受けたのです。農業政策は、国家の戦略と国民の信念を根こそぎ覆す政治の現実を露呈しました。
「10年備蓄」という現実的な選択肢
このような現実を前に、私たちが今選ぶべき道は「自給率の向上」ではなく、まず「10年分の備蓄」です。備蓄であれば、米国との貿易関係を壊すこともなく、豊作時に安く買い入れれば農家の収入安定にもつながります。
さらに備蓄は、気候変動・大地震・戦争・輸入途絶・火山の大噴火・核の冬・隕石衝突など、想定されうるあらゆる非常事態への「唯一の現実的対抗手段」でもあります。自給率を100%にしても、太陽光が遮られる「核の冬」には食料は作れませんが、10年分の備蓄があれば生き延びるチャンスが生まれるのです。
備蓄は国家のレジリエンス(回復力)を高め、さらには国際的な支援体制としても活用できます。飢饉や危機が起こったとき、米や保存食を現物で支援する国になれば、日本の信頼と影響力は飛躍的に高まります。
備蓄は古代からの「日本の知恵」
実はこの「備蓄」という発想そのものが、日本の古代からの伝統でもあります。仁徳天皇は「村の御倉(みくら)」を全国に整備し、豊作の米を蓄え、それによって国民の命を守りました。この知恵こそ、いま世界に示すべき「日本モデル」ではないでしょうか。
現代でも、日本の技術力をもってすれば、米を長期間、冷蔵・真空保存することは可能です。無農薬で高品質な米であれば、保存米として価値があり、後にプレミア付きで販売することすらできます。これは単なる防災対策ではなく、新しい経済循環と国際平和への貢献にもなります。
世界を巻き込む「平和の備蓄戦略」へ
現在、世界中で飢餓や気候災害によって数百万人単位で命が失われています。しかし、備蓄があれば、それらを防ぐことができます。飢えが戦争を生み、備蓄が平和を守る。これはただの理想論ではなく、科学的リスク評価と投資効果(ROI)に基づいた、極めて現実的な戦略です。
倭塾では、すでに無農薬・無化学肥料の「倭塾農園」も始まっています。今こそ、日本全体でこのビジョンを共有し、世界をリードする食料備蓄国家への第一歩を踏み出すときです。
【感想】
人というのは、目の前にどれほど大事なことがあっても、気づけないことがあります。
「あきめくら」という言葉がありますが、まさにそうだと思わされたのが、今回の東郷先生との対談でした。
日本は、初代神武天皇の時代から食料備蓄を重んじてきた国です。
なぜ日本が、小麦やトウモロコシのような効率的な作物ではなく、手間のかかる稲作を重視してきたのか。
それは、災害の多い国土にあって、いざというときに備えるという国家の根幹的な思想があったからです。
そもそも「みやこ」という言葉も、「み=大切な」「や=屋根のある」「こ=米倉」を意味する合成語です。つまり、米倉こそが都=国家の中心だったのです。
ところが明治以降、日本は食料備蓄を次第に後回しにし、とくに昭和44年の食管法改正以降、国による備蓄制度はほぼ消えました。それ以前には、古古米を「標準価格米」として日常的に食べ、新米と古米は備蓄するという国家運営がなされていたのに、です。
現代の技術を使えば、10年分の備蓄は十分に可能です。
それを全国の都道府県単位で進めれば、国内のインフラ整備になり、短期的には景気対策となり、長期的には安全保障にもなります。
そして、食料を蓄えるという行為が、国防意識を高め、危機に対する共通認識を国民全体に浸透させていく。
まさに東郷先生のご提言は、国家運営の根本にかかわるものであり、この対談内容は、もっともっと多くの人に届いてほしいと、心から願います。