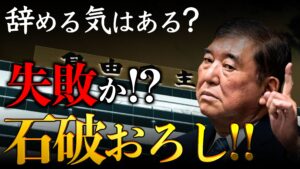日本における「宗教」という概念の成り立ちから、神道と仏教の違い、そして神仏習合の歩みまでを解説しました。信仰と生活がどのように結びついてきたのかを考えます。
宗教という言葉の誕生と日本人の違和感
今回のライブではまず、「宗教」という言葉自体が日本に存在しなかったことから話を始めました。実は「宗教」という言葉は幕末の翻訳家が英語の Religion を訳す際に作られたものです。Religion の語源は「再び結びつける」という意味を持ち、神と人間をつなぎ直すことを指します。しかし日本人にとっては、もともと神々と切り離されるという感覚がなく、常に自然や祖先と共に生きてきたため、翻訳者たちは大変悩みました。結局、「おおもと(宗)のおし(教)え」という意味を持つ「宗教」という言葉が造語して当てられたのです。
この経緯からも、日本における神道は「宗教」という概念よりも古く、日々の暮らしと一体化した存在であったことが分かります。
神道と仏教の基本的な違い
神道は「惟神(かんながら)の道」と呼ばれ、自然や祖先とともにある暮らしそのものです。経典や教祖を持たず、生活習慣の中に自然と溶け込んでいます。いただきます・ごちそうさまといった言葉もその延長にあります。
一方、仏教はインドで釈尊によって説かれ、中国や朝鮮半島を経て6世紀に正式に日本へ伝来しました。仏教は教えを学び、煩悩を克服し、悟りに至ることを目指す体系的な思想です。経典に基づき修行を重ね、心を整えていく点が特徴です。
つまり、神道は「暮らしの道」、仏教は「心を高める教え」と整理できるでしょう。
神仏習合と日本的調和
歴史の中で、日本人は神道と仏教を対立させず、むしろ融合させてきました。推古天皇と聖徳太子の時代、仏教興隆の詔が出され、寺院が各地に建てられるようになりましたが、その後も神祇を大切に祀ることが明記され、神と仏が並び立つ道が選ばれました。
こうして「神仏習合」が進み、神々は仏や菩薩の化身と考えられる「本地垂迹説」も生まれました。これはまさに「和を以て貴しとなす」という日本的精神の表れです。違いを争うのではなく、互いに響き合いながら共存する姿勢が、長く続く文化を育んできました。
神と人との関係 ― 願いではなく誓い
神道における参拝は、単なる願望成就ではなく「誓い」を立てる場だと語りました。受験であれば「合格させてください」ではなく、「努力するので見守ってください」と誓うことが本来の姿です。努力を怠れば神に叱責される覚悟が必要であり、その真剣さこそが信仰の根幹にあります。
一方の仏教は、経典を通じて心を整え、悩みや苦しみを超えていくための智慧を授けます。神道と仏教は、このように役割を分けながら、日本人の精神を支えてきました。
現代への示唆
最後に触れたのは「すべての出来事は自分が作り出している」という視点です。社会問題も個人の悩みも、人間自身が招いたものです。だからこそ、神仏に頼るだけでなく、自らの努力と成長が欠かせません。その上で神に見守られ、仏の教えを学ぶことで、人生をまっすぐに歩んでいくことができるのです。
批判や困難に直面しても、それを通じて心を鍛え、仲間とともに歩む姿勢を持つことが、日本人の伝統的な強さであり、今を生きる私たちにも大切な指針になるとまとめさせていただきました。
【所感】
この動画では、単に宗教史を解説するのではなく、今を生きる私たちへの生き方のメッセージとしてのお話をさせていただきました。
ご視聴いただくことにより、「知識」ではなく、「元気」や「誇り」をお持ち帰りいただけたら、すごく幸せに思います。
また、ここでは神社への参拝を、「お願いの場」ではなく「誓いの場」とお話させていただきました。
神様に甘えるのではない。
努力するので見守ってくださいと、胸を張って言えるような生き方をしていくこと。これこそが、古代から日本人が大切にしてきた潔さや誠実さにつながる文化であると思います。
そして、神と仏を対立させるのではなく「どっちも大切」と受け入れる姿勢。
これは宗教論を超えて、日本人の強みそのものであり、現代社会にも応用できる「違いを超えて共存する普遍的な智慧」なのだと思います。