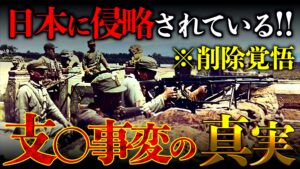東郷潤先生との対談では、500年以上続いた植民地支配の実態と人種差別の構造を解き明かし、日本の戦いが歴史を変える契機となった意義を考察しました。
大東亜戦争を考える意味
毎年8月になると戦争に関する議論が盛んになります。今回の倭塾では「大東亜戦争とは何であったのか」をテーマに、東郷潤先生をお招きし、500年に及ぶ植民地支配の実態とその本質について掘り下げました。
大東亜戦争を単なる「有罪・無罪」「善悪」の視点で捉えるのではなく、人類史の大きな流れの中で位置づけることが重要であり、日本の戦いがもたらした「奇跡」に焦点を当てています。
500年続いた植民地支配と人種差別
東郷先生は、1415年のポルトガルによる北アフリカ侵略から第二次世界大戦までを「植民地主義の500年」と定義しました。この間、ヨーロッパ列強は世界各地を支配し、アフリカ・アジア・アメリカ大陸の先住民を徹底的に抑圧しました。
1939年時点で先住民による実質的な独立国は、日本とタイのみであり、それ以外はほとんどが植民地、あるいは白人支配の下にありました。植民地主義の根底には「有色人種は劣等である」という偏見が存在し、それが人種差別と不可分のものとして機能していました。
法的には奴隷貿易やジム・クロウ法、アパルトヘイト、人種間結婚禁止法などが整備され、人種差別は「合法」とされていました。さらに学問も優生学や誤用された進化論を通じて「白人が最も進化した人種である」と正当化しました。経済面では奴隷労働やプランテーション経済が発展し、搾取と虐殺が正当化されていったのです。
歪んだ認知が生んだ悲劇
ヨーロッパ人が同胞を「魔女」として火あぶりにした時代、異教徒である先住民は「悪魔の眷属」と見なされ、残虐な支配が行われました。征服された民族は「劣等」とされ、反抗すれば「獣」とみなされました。
こうした歪んだ認知の結果、人間性を否定され、奴隷や家畜のように扱われる人種差別が世界を覆ったのです。驚くべきことに、アメリカでは20世紀半ばまで黒人男性を対象とした非人道的な梅毒実験が行われていました。こうした事実は、人種差別が単なる「過去の出来事」ではないことを示しています。
日本の戦いがもたらしたもの
この状況に挑んだのが日本でした。日本はアジアで唯一、西欧列強と対等に立ち、植民地化を免れた国でした。そして大東亜戦争は、500年続いた植民地主義を揺るがし、戦後の独立運動のきっかけを生みました。
東郷先生は「日本の戦いがあったからこそ、世界の構造が変わった」と指摘します。ここに、日本の存在が人類史における「奇跡」である理由があります。
いま私たちが問うべきこと
今日の日本でも、外国人との共生や労働問題が議論されています。しかしそれを単純に「差別」と片付けるのは危険です。歴史における本物の人種差別――植民地支配と奴隷化――と、日本人が直面している課題は質的に異なるものであるからです。
差別を単純に「善悪二元論」で断じてしまえば、社会の複雑な問題は解決できません。私たちが学ぶべきは、過去500年の悲劇の本質と、日本が示した「対等な関係を築こうとする姿勢」なのです。
結び
今回の対談を通じて、私たちは「植民地支配500年」という歴史の重みと、日本の戦いの意味を再確認しました。日本人が進むべき道は、過去の差別を繰り返すことではなく、人と人が響き合う未来を築くことです。
大東亜戦争の真実を見つめ直すことは、未来に向けて新しい文明の基盤を考える第一歩となります。
***
【所感】
今回の対談を整理していて強く感じたのは、「歪んだ認知が生んだ悲劇」という視点の重要性です。植民地支配も人種差別も、すべては「相手は劣っている」「自分たちは優れている」という思い込みから始まりました。そしてその思い込みが法律や学問、経済に組み込まれ、500年もの間、人類社会を覆ってきたのです。
しかし日本は、大東亜戦争を通じてその認知に正面から挑みました。その挑戦が、肌の色による差別の是正という形で現代につながっていることは疑いようがありません。とはいえ「下」を失った白人社会では、今度は内部で上下を作り出し、富裕層が多数の民衆を劣等とみなす構造が改めて問題になっています。その象徴が、近年の米国政治の分断に現れているのではないでしょうか。
大切なのは、こうした問題を「いまある枠組み」で解決できないということです。なぜなら、その枠組み自体が500年の差別構造の中で育まれてきたものだからです。暴力や恐怖に基づく社会では、人はどうしても「体力・情報力・財力」という力に頼らざるを得ませんでした。だからこそ、世界中が必死で経済競争に走り、落伍すれば貧困が待つという仕組みを強化してきたのです。
けれど日本は、この30年間、経済の世界競争から取り残されたことによって、逆に「お金ではない別の価値」を模索する方向へ自然に向かいました。それは、かつて先人たちが掲げた「人種差別撤廃」の志をさらに押し広げ、世界の認知そのものを転換させる挑戦です。経済的利益ではなく「共震共鳴響き合い」を基盤とする社会を築く──その実験を日本が先行して体験しているのです。
だからこそ、この流れをどう形にしていくかが、これからの人類に問われている課題だと思います。そして日本は、その「未来志向の光」を具体例として示し得る立場にあります。
【結びの呼びかけ】
500年にわたる植民地支配と人種差別の歴史を振り返るとき、日本の戦いが世界に与えた意味は計り知れません。
そして今、私たちは「共震共鳴響き合い」という新しい文明の方向性を模索しています。
次の世代へと手渡すものは何か──。
それは、誰かに強制されるものではなく、私たち一人ひとりが選び、育て、響き合いの形で未来へつないでいくものではないでしょうか?