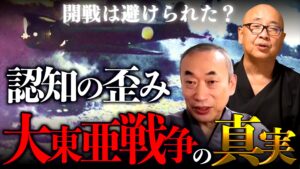埼玉の自然栽培田で、除草剤なし・草取り最小でも稲が優勢となる仕組みを紹介。πウォーターで水と生態系が回復し、経済性は産直で確保。米農家の持続可能なモデルを示します。
Ⅰ.草を「抜く」のではなく、稲が「勝つ」――無農薬・低除草で成立する現場
取材の舞台は、埼玉県・松口の田んぼです。8月24日の猛暑下、早生の収穫前に圃場の全景を確認しました。目をひくのは、除草剤不使用・草取りほぼ無しでも、畔(あぜ)以外の「田面の奥まで土が見える」状態が広く保たれている点です。雑草を“ゼロにする”発想ではなく、稲の生育力を高めて雑草が入り込む余地を与えないという設計が軸になっています。
稲の姿も力強いです。茎が太く、葉はピンと張り、穂はよく垂れています。一本の穂に分かれる小枝(枝梗)は、一般の慣行栽培で10本前後が多いところ、9~13本が標準で、16本に達する穂も確認できました。これは、苗づくりの段階から有機的な育苗で根張りを促し、太い地際茎に十分な維管束(養分通路)を確保した結果です。太い茎は通せる“配管”が多く、充実した穂に直結します。
また、**穂首の強さと登熟(デンプンの詰まり)**にも注目です。籾へ養分を送る微細な“管”が茶変していく割合を見ながら適期収穫を見極める実践が行われ、品質と歩留まりの両立を図っています。**目的は「草を退治する」ことではなく「稲を育て切る」こと。**わずかな雑草は許容しつつ、機械収穫に支障が出ない範囲で畦草管理にとどめます。結果として、草取り労力は最小化され、無農薬でも“業として成立”する手応えが得られています。
対照として、近隣の慣行圃場も確認しました。除草剤を施しても耐性雑草が残り、カメムシ被害による黒変米が散見されます。そこでの対処は「さらに薬剤」という循環になりがちですが、自然栽培の圃場では**生態系の復元(天敵・水生昆虫・魚類の戻り)**による抑制が機能し始め、発生そのものが低く抑えられていることが印象的です。
Ⅱ.水が変わると、田んぼが変わる――πウォーターと生態系の回復
本プロジェクトの見どころは水質の改善です。鉱物・有機由来の素材を独自比率で焼成・複合したπ(パイ)ウォーター用ビーズを、用水の上流側に接触させるだけで、黒ずみやヘドロが目立つ水が、短時間で澄明になっていきます。設置後の水路には、ミズスマシやメダカ、水生昆虫、トンボなどが戻り、生きものの気配が濃くなります。要は、“腐りにくい水環境”が維持されるため、田面の微生物相から高次捕食者までが層を成しやすくなるのです。
この水質改善は、苗の自活力を引き出す育苗とも連動します。化成肥料中心の育苗では、溶けた養分が“受け身”で根に入ってしまいがちですが、有機的な育苗は根が自ら養分を探し取り込む性質を育てます。結果として、環境適応力の高い苗になり、干ばつ・高温・少雨といったストレス下でも、分げつ数・枝梗数・登熟に好影響が出やすくなります。実際、この圃場では猛暑と少雨の年でも健全な穂数と登熟が確認され、近隣で問題化したカメムシ被害も僅少にとどまりました。
さらに、土壌側の改質資材(育苗土への数%混和、代かき・田面への施用)により、団粒構造と通気・保水のバランスを整えます。水が澄み、土が呼吸を取り戻し、生態系が層を重ねる——その積み上げが、「除草剤や殺虫剤に頼らない圃場の安定」を支えます。なお、このビーズは家庭の風呂や炊飯でも効果が報告され、ピンク汚れが出にくい・ご飯が劣化しにくいなどの生活面の利点も語られていますが、ここではあくまで稲作現場での再現性が鍵となります。
Ⅲ.「米で食べていける」をつくる――産直モデルとMOGA(Make O-kome Great Again)
技術と生態が整っても、経済が回らなければ就農は続きません。本取材で提示されたのは、産直による価格の適正化です。一般にJA出荷では60kg=3万円前後という水準が語られますが、消費者が1kg=1,000円程度で買える価格で、一定面積を産直で回せば経営は成り立つという試算が示されました。60kg換算で6万円、すなわち倍近い付加価値が、無農薬・生態系回復・味とエネルギー感という価値とともに、直接「食べる人」に届く形です。
プロジェクト名はMOGA(Make O-kome Great Again)。「日本の米をもう一度“生業”に」という旗印の下、10ヘクタール規模の圃場でも、無農薬・低除草の運用を機械技術と現場ノウハウで再現し、収量は慣行並み~9割以上の手応えを得始めています。初年度から田面の変化が表れ、翌年以降は微生物相の熟成による底力の向上も見込みます。早取りでカメムシ被害を回避する作付計画や、**“太い苗を少苗で植える”**設計も、労力と機械収穫性の両立に寄与します。
課題は横展開と再現性です。ポイントは①上流からの水質改善、②育苗段階での根力づくり、③代かき・整地の精度、④雑草をゼロにせず“稲を勝たせる”栽培思想、⑤産直と予約販売の仕組み化。この一連を地域ごとに最適化できれば、農薬・化学肥料依存からの脱却と農家所得の改善が同時に進みます。結果として、生態系は豊かになり、食味と“腹持ち”の良い米が安定供給され、若手参入の動機も生まれます。輸入に頼る前に、“食べる人”と“作る人”が直接つながる国内の解が、すでに現場で形になりつつあります。
【所感】
今回の取材で強く感じたのは、「草を抜く」のではなく「稲を勝たせる」という発想転換です。雑草を徹底的に排除するのではなく、稲そのものの生育力を高め、雑草が入り込む余地をなくしてしまう。そこにこそ、無農薬栽培が“業として成立”する核心があると実感しました。
また、上流からの水質改善によって微生物が息を吹き返し、魚や昆虫などの生き物が戻るという流れは、自然と農業が一体となって再生していく姿そのものです。育苗の段階で「自ら根を張る苗」を育てる思想も、茎の太さや収量に直結しており、単なる技術を超えた生命観が宿っています。
さらに、産直による価格の適正化は、米農家が胸を張って生業を続けられる具体的な道筋を示してくれました。慣行栽培との比較でも収量は十分に見込め、かつ生態系が蘇り、食味や腹持ちの面でも価値が高い。これこそ未来につながる稲作の形だと思います。
要は、無農薬でも農業は回るのです。そのための条件は〈上流水質の改善・自立する苗・丁寧な代かき・稲を勝たせる思想・産直モデル〉の五つに整理できると感じました。この道が広がれば、農家も消費者も自然も共に元気を取り戻すことができる。MOGAプロジェクトは、その可能性を鮮やかに示していると思います。