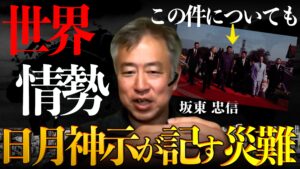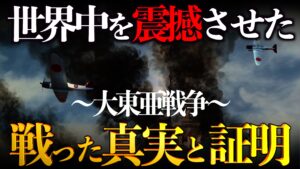義和団事件での日本人外交官殺害を手がかりに、暴力が日常化する国際社会の現実と、命を重んじる日本の文化的作法を対比しました。歴史と時事を往還し、平和を選び取る指針を示しました。
Ⅰ 「力」と「暴力」を同一視する世界──日常会話で人命が消える現実
朝のライブは、現代の国際社会における“当たり前”の落差から始まりました。
日本では、レストランでの商談といえば価格交渉や噂話の域を出ません。
ところが一部の国や地域では、同じような場で「邪魔者を消す」ことが極めて平板な会話として交わされ、そのまま実行される現実があります。
狙撃や暗殺は遠隔から痕跡を残さず遂行され、実行役は捕まらず、代役が報酬と引き換えに罪を被る構造が存在します。
背景には「武力(フォース)と暴力(バイオレンス)を区別しない言語感覚」も指摘されました。
英語では武力も暴力も“violence”や“power”の語で曖昧に表されやすく、正当防衛や公権力の行使と無法な暴力の境界が文化的に不明瞭になりがちです。
対して日本語には「武」と「暴」を分ける感性が息づき、力の用い方に厳格な倫理を求めてきました。
ライブでは、近年の要人襲撃への疑義や、巨大権力が治安機関に与える圧力の問題にも触れました。
要点は「世界には、人命を軽視しつつ利権を回す人々が確かにいる」という事実認識にあります。
そこでは、関係者自身もいつ報復を受けるか分からない恐怖の中で生き、悪循環は終わりません。
だからこそ、日本が示すべきは“命を奪わないで済ませるための作法”であり、力を節度で包む文化なのです。
Ⅱ 義和団事件の再読──「日本人外交官殺害」は誰が行ったのか
歴史パートでは1900(明治33)年の義和団事件を取り上げました。
一般に「義和団による外国人排斥運動」と括られがちですが、日本の大使館員・杉山篤(晃とも)氏が命を奪われた件は、清国の正規軍・董福祥配下の兵士によるものでした。
つまり、暴徒の横行のみならず、国家の正規戦力が外交官の命を奪うという一線越えが起きていたわけです。
この一点は大切です。
国家が「武」を「暴」に転じるとき、国際秩序は急速に壊れます。
外交官の安全は文明国の最低限の約束であり、それを破ることは「言葉による解決」を捨てる宣言に等しいからです。
義和団事件を“群衆の熱狂”としてだけ理解すると、国家の責任の所在がぼやけます。
事件を再読する意義は、国家が暴力の扉を開いた瞬間に光を当て、現在に通じる危機感を共有するところにあります。
併せて、日本の特異性も浮かび上がります。
日本は近代以降、対外関係においても国内秩序においても、形式や礼節を通じて「武の節度」を制度化してきました。
自衛権の発動に厳しい制約を課し、統制なき私的暴力を禁圧してきた歴史は、明らかに「縛りが強すぎる」もので(到底納得できるものではありませんが)、世界標準からみれば、“命を守るための縛り”であるのかもしれないともいえるのです。
Ⅲ 日本的「平和の作法」──縄文から町人文化、武士道、物語へ
ライブの中心テーマは、「日本はなぜ命を重んじるのか」でした。
ここで語られたのは、複数の層からなる文化的作法です。
第一に縄文的な長期平和の記憶。
長い時間、人を人として遇し、殺しの文化を良しとしなかった生活感覚がある。
第二に神話や物語の教え。
古伝承においても、敵を皆殺しにするよりも、追放や改心を通じて共存に戻す筋立てが目立ちます。
第三に武士道の作法。
戦場での一騎打ちは、卑劣な不意打ちが群衆の怒りを呼ぶ構図として語り継がれ、勝つことと卑怯でないことを同時に満たす規範が尊ばれました。
第四に町人文化の知恵。
江戸の町は火事や飢饉のたびに「しらす(知らし)」の原理、すなわち事実をひろく共有し、合意し、役割を分担して粛々と動くことで被害を軽減しました。
第五に、近代以降の「型(かた)」です。
相撲の礼、武道の礼、冠婚葬祭の礼、仕事の段取り、地域の互助……どれも“相手の命と顔を立てる”ための技法です。
暴力が立ち上がりそうな局面ほど、言葉と所作で落としどころを整える。
これが日本で磨かれた“平和の技術”です。
現代のポップカルチャーにも、その流れが映ります。
悪をただ滅ぼすのではなく、悪に至った事情を見つめ直し、社会の不条理側を正していく物語が広がっています。
これは「暴力の鎮圧」から「暴力の根を絶つ」へのシフトであり、世界が必要としている次の段階の平和観と重なります。
ここから導かれる実践は明快です。
1.言葉と作法を整えること
怒りに任せず、情報を正確に共有し、合意形成の段取りを踏む。
2.現場の自律を高めること
地域・学校・職場で小さな互助の網を張り、暴力に至る前に支える。
3.歴史を学び直すこと
義和団事件のような節目を、加害と責任の構図まで含めて読み替える。
4.文化を手放さないこと
礼や型を「古い」と切り捨てず、命を守るための技術として日常に活かす。
世界が“力=暴力”の等式で動くほど、日本の「力≠暴力」という別解が貴重になります。
選び取るのは日々のふるまいの積み重ねです。
笑顔で挨拶し、段取りを整え、相手の顔を立て、弱った人を支える――小さな作法が暴力の芽を摘み、国のかたちを守ります。
結びに、義和団事件からの教訓をあらためて置きます。
国家が武を暴に落とすとき、国際秩序は崩れます。
逆に、武を節度で包むとき、社会は強くなります。
日本が発するべきは「力を節度で包む文化」というメッセージです。
歴史と時事の往還を通じて、その作法を磨き続けることが、次の世代の安全と誇りを守るいちばん確かな道筋です。
今日も“学びを楽しく”、平和の技術を日常に重ねていきたいものです。
【所感】
今回取り上げた義和団事件は、人命を軽視する世界の現実を突きつけるものでした。
世界では、暴力が当たり前のように用いられ、国家さえもその枠を超えて人を害することがあります。
しかし日本は古代から、民衆を「おほみたから」と尊び、一人ひとりを八百万の神々のように敬ってきました。そこに根づいた文化は、礼を単なる形式ではなく、愛と敬意の外にあらわす作法として育んできたものです。
武が暴力と異なるのも、この一点にあります。
武には礼が伴い、礼は相手を人として尊ぶ心に支えられます。
だからこそ日本の武は、ただ力を振るうのではなく、節度をもって人を守るための力となりました。
近年では、日本でも格闘技などで、選手同士の互いの挑発行動や罵倒の応酬が見られるようになりました。それらは日本の文化に、もともとなかったものです。
いま、日本が世界に示すべきは、愛と敬意をもって相手を尊び、礼を尽くす姿勢です。
なぜなら礼さえも、愛と敬意を失えば、ただの暴力的支配の道具に成り下がってしまうからです。
日本の文化をあらためて大切にし、未来へ、そして世界へと結んでいくことこそ、日本人に託された役割だと考えます。
●礼節を重んじても、相手の尊厳への愛と敬意がなければ、それは単なる暴力になる。