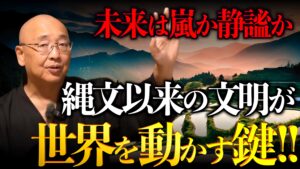国際ビーチクリーンアップデーを入口に、1862年の奴隷解放宣言の本質と、その後の公民権確立までの道のりを整理。北米の雇用構造や日本の共同体の知恵を対比し、現代の教育・社会課題へつなげます。
1.海を守る行動から始める――国際ビーチクリーンアップデーの意味
国際ビーチクリーンアップデーは、9/22を含む週に行われる国際的な清掃活動です。
アメリカの慈善団体オーシャン・コンサーバンシーが提唱し、世界各地で一斉に海岸のごみを拾う取組みが続いています。
日本でも高度成長期には、隣国ほどではありませんが、大量のゴミが海水浴場に放置されるといった出来事が起こりました。
使い捨て、散らかしっぱなし。でも奴隷が掃除をしてくれるといった文化が、戦後の日本に急速に広まりましたが、日本人はわずかの間にこれを反省し、ほとんどの日本人はゴミを捨てないで「持ち帰る」ことを民間ベースの自然な行動にしていきました。
おかげで、地元海水浴場等での清掃も、わずかな努力で対応できるようになっています。
海のゴミは景観の問題にとどまらず、生態系や漁業、観光にも影響します。
そもそもゴミを出さない。使った人が持ち帰るという日本的行動は、ひとりひとりの小さな行動が、結果として景観をまもり、自然を守るという結果となっています。
ゴミを出すだけ出して、あとでゴミを拾う国際事前運動をすることも大事なことですが、そもそも個人の自覚として、「来たときよりも綺麗にして帰る」という日本的発想と行動は、いわば武士道精神であり、古くからの日本に息づくものです。
そもそも縄文時代の遺跡を見ても、貝塚だけにゴミが集中しているのです。
ゴミは出さない、持ち帰る。
それは政治運動ではなく、ひとりひとりの個人の民度と自覚に基づくものです。
2.1862年9月22日――「奴隷解放宣言」をどう読み解くか
同じ9月22日は、1862年にエイブラハム・リンカーン大統領が「奴隷解放宣言(第一部)」を発表した日でもあります。
「奴隷解放宣言」は、予備宣言(1862/9/22)→最終宣言(1863/1/1)の二段階で行われました。
「奴隷解放宣言」は、一般に「奴隷を解放した」と要約されがちですが、現実の権利獲得は一足飛びではありません。米国の黒人が市民権(公民権)を得たのは1964年(昭和39年)のことです。宣言から約一世紀を経た後のことなのです。
では、リンカーン大統領の「奴隷解放宣言」とはどのようなものであったのか。
これを理解するには、当時の米国の産業構造を知る必要があります。
当時の米国は、南部11州が、綿花栽培と輸出による「大農園経済」です。
この時代は、パックス・ブリタニカの時代で、大英帝国が7つの海を支配した時代です。英国の服地は、それ自体がブランド化し、当時の高級嗜好品として世界的に高値で取引されていた時代です。これを着用することが紳士の条件ともされ、英国の影響力で、世界中のVIPが、こぞって英国製の服を仕立てていた時代でした。
ですから英国製服地は、作れば作っただけ売れる。そのためには大量の綿が必要になります。
その綿を栽培していたのが、国土の広い米国南部11州でした。南部では綿花は栽培すればするほど利益があがりました。映画「風と共に去りぬ」でビビアン・リーが演じた主人公のスカーレット・オハラの住む、あの大豪邸は、南部の農家の当時の生活そのものであったわけです。
その大農園では、黒人奴隷が使われていました。
奴隷と、通常の雇用の違いは、奴隷は衣食住を提供する代わりに、月のお手当(給料)は小遣い程度でOKであったことです。
たとえば現代のコンビニでアルバイト従業員を雇えば、月15万円くらいの給料を払わなければならないかもしれない。けれど、奴隷なら、衣食住を除いて、本人には月1万円の小遣いを渡すだけでOKであるわけです。つまり、オーナーからすれば、それだけ人件費コストを安くすることができ、浮いた分が、まるごと利益になるわけです。
ところが南部11州が奴隷たちを大量に使った結果、クビになったり逃亡したりした黒人たちが、米国の北部へと流れていくことになりました。
当時の北部では、白人経営者が白人労働者を雇用することが通例でしたが、奴隷たちがやってくると、黒人たちを奴隷として使ったほうが、はるかに安上がりで会社に利益がでる。
こうなると、圧倒的多数の白人労働者たちは職場を失うことになるのです。
このことが社会問題化したときに、リンカーンが打った施策が、「同一市場での公正競争を促す方向付けを行う」というものでした。奴隷という制度そのものを禁止すれば、黒人と白人は、同じ労働市場での競争になります。
そうすれば、雇用主は白人を雇わざるを得なくなる。
しかしこのことは、北部の白人労働者たちにとっては莫大なメリットを生じさせる一方で、南部諸州は大農園における人件費の急騰を意味します。
「だったら米国にいる必要はない。南部11州は独立してアメリカ共和国をつくろうではないか」
これが南北戦争の発端になります。
ちなみにリンカーン当時の米国に、黒人の投票権はありません。
投票できるのは白人だけであった時代です。
ですからそれが黒人にどれだけ不利益をもたらしたとしても、黒人に投票権がないのですから、それらは完全に無視されることになります。
3.制度と暮らしの距離――「奴隷」と「雇用」、そして日本の共同体
奴隷制と雇用制の差は、家計にとって決定的です。
賃金を払う雇用はコストがかかりますが、労働の対価と権利が明確になり、技能形成や社会参加の基盤が生まれます。
制度の転換は、雇用の公正競争を成立させ、白人・黒人を含む労働市場全体の再設計を迫りました。
一方、日本の歴史には、個の賃金を「家」に付け替えて運用する知恵がありました。
たとえば丁稚奉公に見られるように、稼ぎは家へ集約し、必要分だけを個人に配分して共同体としての生活耐久力を高めていました。
戦後の核家族化・単身化で世帯の分散が進みましたが、本来日本社会は、「力を束ねる」ことで生存力を上げる文化を持っています。
ここで対比したいのは、
米国の「権利の近代化」と、
日本の「共同体の最適化」
という二つのレンズです。
権利の明確化は差別を正し、
共同体の知恵は不況や災害、物価高といったショックへの耐性を高めます。
どちらが上位という話ではなく、社会を支える両輪としてどう配合するかが鍵になります。
海のごみを皆で捨てないという運動が広がるのも、共同体の力を活かす一例です。
理念(環境保全)と実務行動(捨てない・持ち帰る)が結びつくと、成果は目に見える形で蓄積します。
4.歴史を「今」に翻訳する――教育・メディア・市民の役割
宣言から法整備まで100年を要した事実は、教材の一行に収まりません。
文系の学びが重視するのは、異なる視点を照らし合わせることです。
単純化された物語だけでは、制度と暮らしのズレが見えません。
歴史を「今」に翻訳するには、「自分の頭で考える」習慣を身につけることが不可欠です。
歴史の学びと地域の実践は、どちらも「正しさ」を積み上げる作業です。
海岸の一本のペットボトルを拾う手、教科書の一行を深読みする目、その両方が社会を前へ運びます。
9月22日は、言葉の力と手の力を同時に思い出させてくれる日です。
【参考】
日本の「世帯に給金を支払う」仕組みについて
この仕組みは、他国の歴史に類例のない日本的なユニークなシステムであり、以下のような特徴があります。
1.生活の安定性が優先される
丁稚奉公や武家の家禄などに典型的ですが、「個人」ではなく「家」に収入を集約することで、暮らしの基盤が安定しました。
もし一人が病気や失敗で収入を失っても、家という枠組みで支え合える。
これって保険制度に近い役割を果たしていたといえます。
2.教育・技能継承の仕組み
個人の稼ぎを全部自分のために使うのではなく、家に納めて必要分を配分する。残りは次世代の教育や事業投資に回される。
だから奉公人も「家の子」として育てられ、技能を学んでいけました。
単なる労働力ではなく、人を育てる土台だったのです。
3.「義理」と「信用」の経済
米国の賃金労働が契約社会を基盤にしたのに対し、日本の世帯給金制は「義理」や「信用」によって機能していました。
だからこそ経済合理性だけではなく、「この人を裏切れない」「家を守るために頑張る」という心理的支えが強く働きました。
この仕組みは 「日本的セーフティネット」 だったといえます。
アメリカが「権利の明確化」で近代化したのに対して、日本は「家を単位とした共生」で耐性を高めた。
どちらも正しいけれど、時代の波や災害に強いのはむしろ日本型だったのではと感じますが、みなさんはいかがでしょうか。