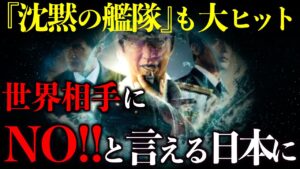祇園の芸妓・お雪がJPモルガンの甥と結婚。見出しは「四万円の貞操」。開戦19日前の出来事と戦費調達の史実を照らし合わせ、因果か偶然かを考えます。晩年の寄付と白いバラの逸話まで紹介。
Ⅰ 「4万円の貞操」と“日本のシンデレラ”
9月30日、秋の気配とともに取り上げたのは、近年語られる機会が減ってきた祇園甲部の芸妓・お雪の物語です。明治36年(1903)の新聞に踊った大見出しは「4万円の貞操」。当時の4万円は、現在価値でおよそ8億円に相当するとされます。
祇園甲部の芸妓で胡弓の名手として知られたお雪は、米国の大富豪JPモルガンの甥、ジョージ・デニソン・モルガンに見初められ、幾度もの来日を経て、明治37年(1904)1月20日、横浜で結婚式を挙げました。世間は「日本のシンデレラ」と沸き立ち、華やかな祝福に包まれます。
芸妓は芸を売る存在であり、祇園には古来、媚びない凛とした気風が息づいてきました。お雪の品位、胡弓の音色、立ち居振る舞いは、失意の旅の途中にあったモルガンの心に深く響き、やがて二人の縁を結びます。
新聞がセンセーショナルに取り上げた金額の大きさに目を奪われがちですが、当事者の心の機微や、異文化の出会いが生んだ共鳴こそ、本質にあることを忘れてはいけません。
Ⅱ 開戦19日前──偶然か、縁か:結婚と戦費調達
注目すべきは、この結婚の日付です。明治37年1月20日――そのわずか19日後、2月8日に日露戦争が始まりました。日本は未曾有の戦費を必要とし、国内資金だけでは賄いきれません。
高橋是清がロンドン、ニューヨークを奔走し、ロスチャイルド家、JPモルガン、クーン・ローブ商会などの国際金融資本から外債発行を通じて資金を調達しました。1904~1905年の外債は総額で巨額に達し、近代国家の命運を支えます。
ここで、自然と浮かぶ問いがあります。それは「偶然に過ぎないのか」というものです。お雪の結婚は国際金融の意思決定と直接の因果関係を持たない、というのが史実の骨子です。甥の私的な結婚と巨大金融の判断は、原則として別筋と考えるのが妥当でしょう。
ただ、人は偶然の重なりの中に意味を見出そうとします。開戦直前にモルガン家へ日本人女性が迎えられた事実を、当時の関係者がどう感じたか。数字や文書に残らない“心の傾き”は、いつの時代にも存在します。
だからこそ、この物語は「偶然をどう受けとめるか」を問いかけます。因果を断定するのではなく、偶然に託された“縁”の作用を想像する。
日本文化には、目に見えぬ働きや“かむはかり(神慮)”を丁寧に見つめる感性があります。お雪の結婚と外債調達の並行は、史実としては別線でも、歴史叙述の余白に柔らかく差し込まれた“縁の光”のように感じられます。
Ⅲ 栄光と孤独、祈りへの回帰──白いバラが届くまで
お雪の人生は、祝福ののちに厳しさを迎えます。夫ジョージは44歳で急逝。遺産をめぐる訴訟に勝利して巨額の資産を得る一方、制度の壁により無国籍の立場となり、居場所の不安定さと向き合います。フランスに移り、社交界の花として注目を浴びても、心の孤独は消えません。結婚すれば遺産を失う可能性があったため再婚は選ばず、学者の恋人の研究を支えるなど、与える生き方を続けましたが、その恋人もまた先立ちます。
欧州情勢がきな臭くなる中で帰国を決断。戦時には送金が途絶え、無国籍ゆえの監視も受け、試練はさらに重なります。敗戦後、権利が回復すると、洗礼を受けてカトリックの名を「テレジア」とし、京都で暮らしました。残る財産の多くを教会に寄付し、祈りの生活へと身を置いた姿は、栄光の眩しさよりも静謐の尊さを教えてくれます。
やがて、訃報に寄り添うようにパリから届けられた白いバラ――「ユキサン」。社交界での記憶と感謝が花となって京都へ帰ってきたことは、ひとつの円環を閉じる象徴に見えます。
人は誰しも、偶然の出会いと選択の積み重ねで人生を紡ぎます。お雪の道のりには、華やぎも、痛みも、そして祈りもありました。歴史の偶然をどう見るか。単なる偶然として切って捨てることもできます。
けれど、偶然の裏側に働く「縁」や「導き」を感じ取ることで、出来事は意味を獲得し、学びへと変わります。開戦19日前の結婚、戦費調達という国家的課題、そして晩年の寄付と白いバラ。数字と事実の列の隙間に、見えない糸が震えている――その感性を、これからの時代にも手放したくありません。
終わりに、小さな提案をひとつ。今日出会う“偶然”を、少しだけ丁寧に味わってみること。そこから始まる学びと響き合いが、明日を変える力になります。
【所感】
歴史を振り返るとき、因果関係の証明ばかりを求めると、大切なものを見失ってしまう気がします。偶然を偶然のまま切り捨てるのではなく、そこに「縁」や「導き」を感じ取ることで、出来事は生きた学びに変わります。
お雪の物語にある華やぎと孤独、そして祈りへの回帰は、私たち自身が人生の中で出う“偶然”をどう受けとめるかを問いかけているように思います。
見えない糸に耳を澄ませる感性を、これからも大切にしていきたいと思います。