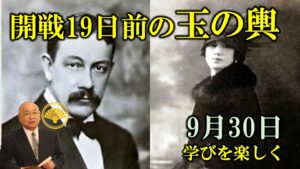『沈黙の艦隊』と1989年前後の現実を重ね、対米関係や経済、技術流出の問題を検討。テセウスの船を手がかりに二項対立を超える視点を示し、「公」を軸に新しい扉を開く重要性を提案します。
1) 『沈黙の艦隊』が映す時代——昭和の終わりから平成の幕開けへ
ライブは、配信ドラマと劇場版で再び注目を浴びる『沈黙の艦隊』から始まりました。
主演の大沢たかおさんの役作りや、過去作『JIN-仁-』『キングダム』との振れ幅にも触れつつ、映像クオリティの高さと実写化の意義を確認しています。
原作は川口開治さんの漫画で、1988年に連載が始まり1996年まで続いた長編です。
昭和63年という「昭和の最後の年」に世へ出たことは象徴的で、当時は“Japan as Number One”と称されたバブル経済の絶頂期。
日本製品の品質と円高を背景に輸出が伸び、企業の設備投資や不動産価格が急上昇していました。
同時に、1989年には元号が平成へ改まり、消費税が導入され、世界ではベルリンの壁崩壊と冷戦終結が起きました。
国内外ともに秩序の書き換えが進む時代に、『沈黙の艦隊』が提示したのは「日本がどう世界と向き合うか」という骨太のテーマです。
作中の独立潜水艦はフィクションですが、“日本が自らの意思で舵を切る”というモチーフは、現実政治・経済が揺れる只中にあって大きな共鳴を生みました。
ライブでは、実写化が「漫画の大胆な骨格を現代に再提示する挑戦」として評価され、その大胆さ自体が“最近の日本すごい”という感覚につながっている点を指摘しています。
ここで話題は、当時ベストセラーとなった『ノーと言える日本』(1989年)へ。
日米貿易摩擦の緊張が高まるなか、日本は“言うべきことを言えるか”が国民的論点になりました。
バブルの熱狂、税制や不動産規制の転換、そして急ブレーキのような景気後退——こうした揺らぎの中で「主体性」の回復は切実な課題でした。
ライブは、過去の論点を懐古するだけでなく、今日の観光地物価やインバウンドの価格形成、賃金・所得の伸び方など具体例も挟み、価格高騰が“泡”ではなく“実体経済の変化”として起こる側面にも光を当てています。
2) 二項対立では進まない——テセウスの船と交渉の現実
議論の核心は、「イエスかノーか」で世界を切り分ける発想の限界です。
『ノーと言える日本』が投げかけた問題意識に敬意を払いながらも、賛成/反対という二分法は、対立の構図を先鋭化させ、最終的に“敵か味方か”の判断へ収れんしがちです。
国際交渉や経済政策は本来、複数の正しさが併存する領域であり、利害が交錯します。
ここで提示された哲学的比喩が「テセウスの船のパラドックス」です。
部品を総替えしてもそれは同じ船か、それとも別物か——物質・機能・歴史のどの軸で同一性を測るかによって結論は変わります。
この比喩は、政策選択や国益判断にも通じます。
どちらにも理があり、見方が変われば価値も変わる。
ゆえに、単純な正誤ではなく“どの物差しを採用するか”が問われます。
具体例として取り上げられたのが、品種や技術の海外提供・流出問題です。
シャインマスカットをめぐる報道に関連し、国内で積み上げた知的資源をどう守るか、またサプライチェーンや食料安全保障、対外関係の駆け引きの中で何をバーターできるのか——感情的反発だけでは整理しきれない難問が浮かび上がります。
実需の現場では、牛肉や鶏肉の国際流通、国内外の価格差、加工・販売の工夫など、複雑な経済の現実が存在します。
ゆえに、単純な「輸入拡大か、内製強化か」ではなく、どの選択が長期で社会全体の利益(雇用、所得、技術蓄積、価格安定、食の安心)に資するのかを、落ち着いて比較衡量する視点が不可欠です。
この文脈で、ライブは「公(おおやけ)」という基準を打ち出しています。
個別の立場の正当性は認めつつも、政策判断の原点は“より多くの人の暮らしに資するか”に置くべきだ、という立ち位置です。
技術や品種は公共的資産でもあり、保護と活用のバランスが要。
保護は国内の正当な報酬や再投資を担保し、活用は国際市場での展開や交渉力強化につながります。
テセウスの船が示す“複数の正しさ”を前提に、二項対立を超えて「最適な折衷」を探る現実主義が求められる——ここが中核メッセージです。
3) 「公」を軸に新しい扉を開く——主体性、国益、そして学び
総括として、過去の「ノー/イエス」論争を踏まえつつ、今必要なのは“第三の扉”を開く発想です。
反対するか従うかの二択ではなく、交渉の土俵を設計し直すこと。
国内の技術・農産物・人材に正当な対価が循環する仕組み、そして所得の底上げによって相対価格の重さを軽くし、生活の実感を改善する経路を太くすることが重要です。
輸入や観光に依存する領域がある以上、外の世界と切り結ぶ現実は変わりません。
しかし、その関係設計を“公”の視点でやり直せば、取引の前提条件やリスク分担、知財保護のルールは確実に改善できます。
ライブ後半では、1989年前後の出来事(改元、税制、インフラ整備、ゲームボーイ、葛西臨海水族館、ベルリンの壁、冷戦終結、天安門など)が想起され、歴史の厚みが現在の判断基準を鍛えることも示されました。
歴史は単なる回顧ではなく、判断の物差しを磨く“道具”です。
だからこそ、沖縄を巡る慰霊と学びの旅の告知が、単なるイベント案内ではなく、「過去を体感し、現在の基準を更新する」実践として位置づけられています。
学びは単発のスローガンではなく、日常に根ざした鍛錬である、という姿勢が全編に通底しています。
最終的に提案されているのは、「公」を基準に、より多くの人がメリットを享受できる解を具体化することです。
技術や産品を守るべきときは守り、開くべきときは十分な対価と条件整備のもとで開く。
価格上昇やインバウンドによる需要変化を“実体経済の変化”として受け止め、賃金や所得、投資、教育で循環をつくる。
対外関係では、ノーかイエスかの二択を超え、交渉の組み替えで国益を最大化する。
テセウスの船が教えるのは、唯一の正解がない世界で、どの基準を採るかを合意し、継続的に更新していく知恵です。
だからこそ、共振・共鳴の輪を広げる学びの場が必要であり、新しい扉はそこから開かれていきます。学びを楽しく——この合言葉こそ、主体性を取り戻すための最初の一歩といえるでしょう。