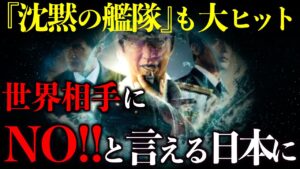1981年の常用漢字表施行を手がかりに、当用→常用→人名漢字の流れと戦後教育の歪みを総点検。字形・筆順が奪った“意味”を取り戻し、日本語と学びの体幹を鍛え直すヒントを語ります。
1) 常用漢字施行という節目——当用・常用・人名漢字を一望し、戦後設計の意図を見直す
10月1日のライブでは、1981年(昭和56年)の常用漢字表施行を入り口に、戦後の漢字政策を三つの柱で整理しました。
第一に、占領直後の1946年に示された当用漢字です。
公的文書や出版で用いる漢字を1850字に限定し、旧字体の簡略化を押し進めました。
目的は「読み書きの平易化」でしたが、同時に使用域の制限・筆順の標準化を通じ、漢字が本来持つ字源的ヒントや造形の物語が後景化した点は否めません。
第二に、1981年の常用漢字。
こちらは“制限”から“目安”へと性格が変わり、社会生活での標準的な用字として整理されました。
その後の追加・見直しを経て、現在は二千余字規模となります。
第三に、人名漢字です。
戸籍名に用いられる需要を踏まえ、常用外でも使用頻度の高い字を枠組みに加えました。
これらは法的強制ではなく指針に過ぎませんが、教育・行政・メディア現場に強い影響を与え、結果として「使われる言葉の幅」「見える字形の型」「学びの導線」を長期にわたり形成してきました。
ライブでは、当用→常用→人名漢字の連続性を踏まえ、「読みやすさ」という利点と引き換えに、漢字という記憶装置が内包していた意味層が薄まった可能性に注意を促しました。
2) 字形と筆順が“意味”を運ぶ——「必」「礼」「学」「教」「権」から考える思考の回路
次に、字形・筆順の変更が思考に及ぼす影響を具体例で検討しました。
最初の例は「必」。
人気時代劇の題字を手がかりに、線の運びや「心に刻む」というイメージが見えなくなると、言葉が帯びる観念の濃度が下がる点を指摘しました。
漢字は音だけでなく、形そのものが意味の手がかりです。
画の省略や筆順の変更が進むと、視覚的に掴めていた“意味の道しるべ”が細り、語感の立ち上がりが鈍くなります。
同じことは「礼」「学」「教」「権」にも当てはまります。
旧字体(禮・學・敎・權)に見えていた所作や関係の構図——礼の“豊かに示す”感覚、學・敎に内在する「子と大人の関係」「躾けとしての学び」、權に潜む“上から見張る眼差し”のメタファー——こうした手がかりが簡略化で読み取りにくくなると、語の運用は平板化します。
結果として、たとえば「権利」「人権」を語る際の緊張感が弱まり、観念だけが独り歩きする危険も生まれます。
さらに、語の読み違いに関しては「平和」の例を挙げました。
国際語の Pax(パクス)が示す“統治と秩序の下の平穏”という観念と、日本語の「平」「和」がもつ「均す・和らぐ」の意味領域は、重なる部分も違う部分もあります。
字源・語源への目配りが薄れると、スローガンだけが先行し、言葉の骨格が空洞化しかねません。
ここで強調したのは、旧字体回帰を直ちに主張するのではなく、「字形・筆順・語義」が結ぶ連関を教育と編集の現場で意識的に可視化することです。
形をきっかけに意味へ、意味を踏み台に思考へ——この順路を取り戻すことが、日本語の体幹を鍛える近道になります。
3) 二項対立を超える基準——“公”を物差しに、日本語と教育をもう一度設計する
ライブの結論は、戦後の言語・教育設計を「良い/悪い」「イエス/ノー」の二択で裁かないことでした。
当用漢字が識字の底上げや印刷・情報処理の実務に資した側面は確かにあります。
一方で、造形由来の意味手がかりが薄まり、語の運びが痩せた場面も現実として存在します。
どちらにも理があるからこそ、基準は“公”に置くべきです。
より多くの人が深く読み、ていねいに書き、誇りをもって語れるようになるのか——この問いに資する再設計が必要です。
具体的には、
①学校での字源・語源への導入(負担を増やすのではなく、既習の常用漢字を題材に短い物語として示す)、
②編集・執筆の現場での表記選択の意図開示(常用漢字を“禁止令”ではなく“目安”として運用し、必要に応じて旧字体や人名漢字を選ぶ理由を脚注・コラムで補う)、
③デジタル基盤の整備(フォント・IME・辞書に旧字体情報や字源メモを組み込み、クリック一つで学べる導線を用意する)などが挙げられます。
また、言葉の運びを現実の暮らしへ接続する工夫も不可欠です。
価格や賃金、観光や輸入といった具体的なトピックに、日本語の精度を持ち込むと、議論はスローガンから実務へと下りてきます。
たとえば「人権」を語る際、自由の拡張とともに責務や相互監視の側面を見落とさない語り方を徹底する。「平和」を論じる際、語源と日本語の意味領域を丁寧に重ね合わせる。
こうした運びが、二項対立の呪縛を解き、合意可能な“第三の扉”を開きます。
ライブ終盤では、学びの旅や勉強会の案内にも触れましたが、これらは単なる告知ではありません。
歴史や土地を身体で感じ、言葉の物差しを磨き直す実践として位置づけています。
日本語は単なる記号ではなく、祖先から受け継いだ記憶の器です。
読みやすさと深さを両立させ、字形・筆順・語義の三層を結び直すこと。
そのための最初の一歩として、常用漢字施行という節目に当用・常用・人名漢字の歩みを振り返り、“公”の基準で学びを更新していく必要がある——ライブではそのように整理しました。