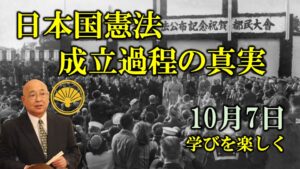知覧の特攻ゆかりの地を案内する武田勝彦さんと新子千晴さんを迎え、
「日本=母」という言葉の感性、英霊の遺書や逸話、玉音放送の真意を確認。
我が国と向き合う言葉の作法、現地で学ぶ大切さを伝えました。
1.「日本=母」と呼ぶ作法――言葉が姿勢を整える
今回の対談は、新子千晴さんの著書に触れたことをきっかけに、知覧で英霊の思いを伝え続ける武田勝彦さんをお招きして実現しました。
冒頭で武田さんは、戦後に残った“言い癖”について指摘します。
自分の国を「日本」と呼び捨てにしたり、「この国」「あの国」と“物”のように言ったりする現状は、母を呼び捨てにするのに似ているのではないか――と。
日本語には、母なる存在に対する自然な敬意が息づいてきました。
空母、母校、母港……私たちの暮らしそのものを支える拠り所に「母」の字が置かれます。
であれば、祖国を語る際は「我が国」と呼ぶのがふさわしい。
言い回しひとつですが、言葉が姿勢を整え、姿勢が行いを正します。
新子さんもこの感覚に深く共鳴し、「宗派や国籍を越えて、世界はひとつの家族」という視点から、言葉を大切に扱うことの意味を語りました。
知覧での体験は、単なる知識ではなく、胸の奥に灯る“実感”として残る――その入口が言葉の作法なのだと思います。
2.英霊が示した「人としての筋」――知覧・富屋食堂・蛍の逸話
武田さんは、知覧での案内を通して出会った幾多の証言を伝えてくださいました。
特攻平和会館(公立)と「ほたる館 富屋食堂」(私設)の二つの資料館があり、後者では鳥濱トメさんと若者たちの具体的なやり取り、性格、遺された品が物語のように展示されています。
語りの核心は、英霊が貫いた「人としての筋」です。
たとえばガダルカナルの話。
島には豊かな木の実が実るのに、日本兵は飢えで倒れました。
なぜか・・・―一本一本の木、ひとつひとつの実に“所有者”がいることを知り、守るべき住民から盗まなかったからです。
軍人は住民を護る者。
ならば、たとえ命が尽きようとも盗みはしない。
世界でも稀な行いが、当たり前のように貫かれました。
もう一つ、知覧に伝わる「蛍」の逸話。
二十歳の誕生日を迎えた宮川三郎軍曹が前夜、富屋食堂で「蛍になって帰ってくる」と語り出撃。
翌夜、戸の隙間から蛍が一匹ふわりと入り、居合わせた隊員たちは肩を組み、涙で声を震わせながら「同期の桜」を歌った――。
この物語は語り継がれ、私設資料館の名「ほたる館」の由来にもなりました。
英霊は、我が国を護るためだけではなく、「人は皆、対等な人間である」という当たり前を世界に通すために戦いました。
白人優位が常識だった時代、アジアの人々が人として立つ道を切り開いたからこそ、今、私たちは世界で普通に仕事ができる。
その背後に、遺書一枚に心のすべてを込めた若者たちの真心があることを、直に確かめたいと思います。
3.玉音放送の真意と、現地へ足を運ぶという学び
戦後を語る際、玉音放送の「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」だけが切り取られがちです。
しかし詔書の結びには、「進むべき道に遅れをとらぬよう、持てる力のすべてを建設に傾けよ」との力強い呼び掛けがあります。
敗戦の悲痛を超えて、未来の建設へ――。
その眼差しは、今を生きる私たちへの宿題でもあります。
新子さんは、幼い頃に抱いた“怖れ”を越え、知覧に立ちました。
現地では、涙が自然にこぼれ落ちる体験がある、と。
耳で聞くのが得意な人、肌で感じる人、涙としてあふれる人――感じ方はそれぞれでも、英霊と向き合う場に身を置くこと自体が、魂の姿勢を正してくれます。
武田さんは、自身の活動を“仕事”ではなく「忘れてはならないことを伝える務め」と語ります。
年に四度、節目の日に合わせた知覧研修を主催し、公の平和会館と私設のほたる館の両方で学ぶ機会を整えています。
対談の終わりに、現地に足を運ぶこと、言葉の作法を見直すこと、そして「我が国」と口にして暮らすこと――この三つを、視聴者と分かち合いました。
結び――「我が国」を口にし、歩を現地へ
英霊が遺した「日本は私たちの母」という言葉は、単なる比喩ではありません。
母を呼ぶように「我が国」と言い、礼を尽くして暮らす。
その小さな一歩が、若者たちの真心とつながります。
知識だけでは届かないものが、知覧にはあります。
遺影と遺書の前に立ち、富屋食堂の台所に想いを馳せ、蛍の光に目を凝らす――そこで初めて、今をどう生きるかが自分ごとになります。
本対談が、英霊への感謝を胸に、言葉・作法・行いを整える小さな起点となれば幸いです。