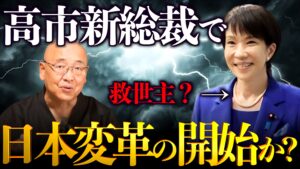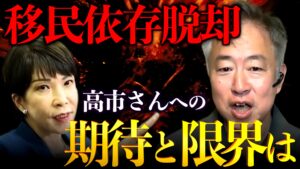10月8日の「そばの日」「足袋の日」に合わせ、蕎麦の由来と各地の名物、足袋・草履・下駄の機能と文化的背景を解説。日本・中国・朝鮮・欧州の履物観の違いと健康面の効用にも触れました。
Ⅰ 10月8日は「そばの日」そして「足袋の日」──日本の風土が育てた知恵
10月8日は語呂合わせで「そばの日」、さらに秋口から足袋を履く機会が増えることにちなみ「足袋の日」とも呼ばれます。
番組ではまず、蕎麦文化の面白さを概観しました。
日本三大蕎麦は「出雲そば・わんこそば・戸隠そば」。
江戸前三大蕎麦は、「藪蕎麦・更科蕎麦・砂場蕎麦」が知られ、いずれも1軒のそば屋から始まり、兄弟や親戚、弟子などが暖簾分けをして広がった蕎麦店で、つゆや粉挽きの違いが個性を生みます。
藪蕎麦は、つゆの濃さが御三家随一。コシがあって海老のかき揚げを名物とする店が多いのが特徴です。
更科蕎麦は、信州で布屋を営む堀井清右衛門が、そば打ちの腕前に長けていたことから、領主の保科氏に言われて布屋からそば屋への転身を勧められ、江戸の街に「信州更科蕎麦所 布屋太兵衛」の看板を掲げたのが始まりです。
更科の「科」の文字は、領主であった保科家に由来しています。つゆは淡くて甘め。
砂場蕎麦は、大坂城築城の際の資材置き場の砂場近くに店があったことに由来し、江戸の街に移ったのは江戸時代中期。砂場蕎麦は、「ざる」がそばの実の中心の粉を卵水で、「もり」が甘皮を含んだ粉を水だけで打つという特徴があります。
蕎麦はイネ科ではない疑似穀物で、痩せ地や寒冷地に適応します。
生育期間が短く、交替作としても優秀なため、山間・高地・寒冷地の食文化を支えてきました。
世界に目を向けると、ロシアの「カシャ」、東欧の蕎麦粥、仏ブルターニュのガレット、北イタリアのピッツォッケリなど、加工の幅が広く、宗教的断食時の食材としても重宝されてきました。
麺として食す文化も日本以外にあり、韓国のマッククスや中国・チベットの蕎麦麺がその例です。
ただし「十割そば」のように粉だけで細く打ち上げる技は、日本独自の到達点と言えそうです。
新そばの季節は、のれんに掲げられる札も心を弾ませます。
香り、のどごし、つゆの切れ。店ごとに異なる妙味を楽しめるのが蕎麦の醍醐味です。
Ⅱ 足袋・草履・下駄の合理性──気候・家屋・身体観が選んだかたち
次に話題は足袋へ。
足袋が親指と人差し指で鼻緒を挟める構造になっているのは、日本の履物(草履・下駄・雪駄)と一体で発達したからです。
高温多湿の日本では、蒸れにくいこと、脱ぎ履きのしやすさが最優先。
家屋は土足厳禁で、屋内外を明確に分ける清浄観もあって、玄関での着脱が生活リズムの一部になりました。
欧州は乾燥・寒冷で石畳も多く、足を守るために革で包む靴が主流になりました。
屋内外の境界が相対的に緩く、靴のまま暮らす前提で耐久性や装飾性が発達します。
中国は礼制の影響が強く、靴は身分と礼の象徴として整えられました。
朝鮮半島ではオンドルの床で靴を脱ぐ生活が基本となり、布靴や儀礼用の靴が身分によって使い分けられました。
足袋と鼻緒履きには、身体面の利点もあります。
鼻緒を挟むことで足指の小筋群が自然に働き、アーチやバランス感覚が鍛えられます。
大地の感触が足裏に伝わりやすいので、体幹が安定しやすく、すり足の所作も身につきます。
高所作業や畑仕事で地下足袋が選ばれてきたのは、足裏感覚の鋭さが安全に直結するからです。
日舞や和装の先輩方が年齢を重ねても溌剌としている背景には、こうした日常的な足指の活性があるのかもしれません。
Ⅲ 「挟む履物」と「包む靴」が映す文明観──暮らしの実感から未来へ
挟む履物は、足を閉じ込めずに外界と響き合う感覚を守ります。
包む靴は、自然から身を守り行動範囲を広げる合理を体現します。
どちらが優れているかではなく、風土・家屋・仕事・礼の体系が、それぞれ最適な形を育てたと捉えるのが自然です。
日本では、「外=足袋と履物」「内=裸足」という清浄観が、玄関文化とともに洗練されました。
鼻緒を挟む所作は、足の指先まで意識を通わせる小さな“修行”でもあります。
子どものころから花緒のある履物に親しめば、姿勢や体幹の安定に役立つという実感も語られました。
使わなければ衰え、使えば思い出すのが人のからだ。
久しぶりに草履を履き直すと、最初は指の間が痛んでも、やがて皮膚も筋肉も応えてくれるようになります。
最後に、季節の話題をひとつ。今日は二十四節気の「寒露」。
空気が澄み、露が冷たさを帯び始める頃です。
とはいえ近年は都市のヒートアイランドで10月も暑い日が続くことがあります。
自然の暦に耳を澄ませつつ、現代の環境課題にも目を向けたいと思います。
そして「国立公園制定記念日」。
名勝を守る制度は、景観のみならず未来の資源を守る仕組みでもあります。
大地と響き合う足裏の感性、四季に寄り添う食と装い、自然とともに生きる知恵。
蕎麦と足袋という素朴な題から、日本の暮らしが持つ底力が見えてきます。
日々の一足、一杯のそばから、からだと心の芯を整える。
そんな小さな実践を重ねながら、「学びを楽しく」、今日も元気に歩いていきます。
【所感】
蕎麦も足袋も、決して派手なものではありません。
けれど、その形や食べ方の中には、日本人が自然と調和しながら生きてきた心が静かに息づいています。
足裏で大地を感じ、指先で鼻緒を挟み、箸で蕎麦をたぐる。
その一つひとつの所作が、私たちの身体と心を自然へと結び戻してくれます。
文明がどれほど進んでも、人はやはり「土と風と水」と響き合ってこそ健やかに生きられる。
それを教えてくれるのが、こうした何気ない日常の文化だと思います。
今日の一歩を、足袋のように軽やかに。
一杯の蕎麦を、感謝とともに味わいながら。
そうして生きることが、きっと未来への「和」をつないでいく道になるのだと思います。