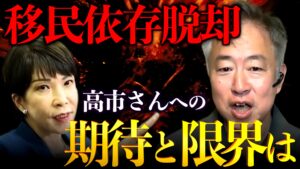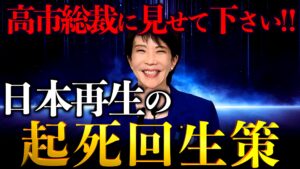ノーベル賞と産業政策、平和賞の評価軸、ハングル普及の経緯を手がかりに、上か下かの二元論から離れ、対等な「響き合い」へ舵を切る必要を語りました。
Ⅰ 二元論の罠をほどき、「響き合い」へ
戦後の空気には、何事も二つに割って「どちらが上か」で決着させる癖が根強く残っています。
家庭でも職場でも、上に立つ者が気分よく、下に回った側は支配される。
ところが日本社会は本来、支配‐被支配の発想に馴染みません。
誰かが誰かの上に乗る感覚が立ち上がると、強い反発と対立を呼び、悪循環になります。
ここで提案したのが「響き合い」の視点です。
上下ではなく対等。勝ち負けではなく共振。
歴史や古典の学びは、知識の蓄積だけで終わらず、日々のふるまいへ降ろされて初めて力になります。
倭塾の学びは、その実装をめざします。
参拝を「宗教」ではなく「習慣」として尊び、見えない世界への感謝を忘れないことも、心の姿勢を整える日々の稽古です。
Ⅱ 10月9日が教える評価軸――ノーベル賞、EV、そして報じられ方
2019年10月9日、リチウムイオン電池の研究により吉野彰氏らがノーベル化学賞に選ばれました。
携帯・PC・EVに至る現代の機動性を底支えした技術は、日本の研究開発と製造現場の底力を示す象徴です。
同時に、研究資金の構造、知財流出、スパイ防止の脆弱さといった現実課題も突きつけます。
研究内容の過度な事前開示、寄付・税制の不整合、産学官の機密管理――どれも技術立国の土台と直結します。
技術が社会に降りると、次は産業政策の番です。
EV一本足の補助金や一律規制は、雇用と裾野産業を抱える自動車セクターに急ブレーキをかけかねません。
外貨を稼ぎ、食料を買い、社会を回す――この日本の現実を直視し、移行のスピード・インフラ・電源構成・部素材国産化を含む「現実解」の設計が求められます。
半年ごとに新車に乗り換えるような過激な比喩を持ち出したのは、消費循環を取り戻すほどの胆力が必要だという合図です。
一方、2009年10月9日のノーベル平和賞(バラク・オバマ氏選出)は、受賞理由と実際の世界秩序の動きが乖離して見える、と批判的に検討しました。
賞や肩書は万能の判断基準ではありません。
大切なのは「何が実際に起き、誰が責任を持ち、社会にどんな影響が出たのか」を冷静に点検する姿勢です。
メディアの言い換えやスローガンに流されず、一次情報と定義を確認し、言葉と現実を結び直す――ここでも「響き合い」の構えが効いてきます。
Ⅲ ハングルの来歴をめぐって――文字はだれのものか
今日の「何の日」からもう一つ。
1446年、李氏朝鮮の世宗が『訓民正音』を頒布したことにちなみ、韓国では「ハングルの日」とされています。
放送では、文字の歴史に関する一般的な理解を俯瞰しつつ、日韓併合期以降の普及過程にも触れました。
要点は三つです。
第一に、朝鮮半島では長く漢字(諺文の用法を含む)が運用され、近代に入って大衆教育の普及とともにハングルの出版・綴字の統一が進んだこと。
第二に、1910年前後の識字率の低さを背景に、近代的な教育制度と出版文化がハングルの大衆化を加速させたこと。
第三に、文字は権力や身分と結びつきやすく、誰でも学べるようにする普及の営みが共同体の力を左右することです。
「誰が発明したか」を巡るマウント合戦は不毛です。
肝心なのは、文字が人々の手に戻り、学ぶ喜びが広がり、社会が豊かになること。
だからこそ、言語教育や正書法の整備、読書環境の充実は、国や時代を超えて最優先の公共事業なのだと位置づけました。
このテーマを語る背景には、二元論の外側にある「共通土台」を取り戻したいという思いがあります。
上か下か、奪うか奪われるか――ではなく、対等に学び、事実を確かめ、違いを尊重しながら合意を積み上げる。
その営みからしか、真の「響き合い」は生まれません。
結び 上でも下でもなく、となりへ
人はそれぞれ、抱えて生まれた課題を乗り越えるために生きています。
親子のすれ違いも、職場の衝突も、社会の論争も、最初から「勝ち負け」に落とし込まず、となりに立って耳を澄ませるところから始めたい。
倭塾の学びは、歴史に学び、定義を確かめ、現場で試す循環です。
スローガンではなく実装へ。
今日も「響き合い」を合言葉に、明るく、具体的に進みます。
ありがとう日本。学びを楽しく、倭塾で。