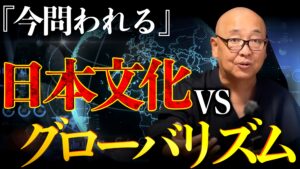戦後わずか19年で開催された東京オリンピックは、人種平等の象徴でした。
昭和天皇のご姿勢や選手たちの誇り、日本人のルールを守る精神が、
世界に「人としての尊厳」を示した歴史的祭典でした。
■ 戦後19年で迎えた奇跡の祭典
昭和39年10月10日。
東京オリンピックの開幕は、戦後の日本にとって奇跡のような出来事でした。
第二次世界大戦が終わった昭和20年から、わずか19年。
国連で敵国とされた日本が、世界の祭典を主催すること自体、当時としては“異常”とも言える出来事だったのです。
しかも、この大会には世界93カ国が参加しました。
戦前のオリンピックでは、参加国はせいぜい50カ国に満たず、アジアやアフリカのほとんどが植民地として扱われていた時代。つまり、白人列強の国々しか「国家」として認められていなかったのです。
それが昭和39年には、戦後独立した多くの有色人種国家が自国旗を掲げて参加。
東京オリンピックは、まさに「新しい世界秩序の誕生」を象徴する舞台となりました。
その中心に日本があったということ――。
これは、敵国としてではなく、“人間としての誇りを取り戻した国”としての復活を意味していました。
■ 昭和天皇が示された「敬意」の姿勢
開会式の日、昭和天皇は、入場行進の全ての選手団を最後まで立ったまま迎えられました。
長時間にわたる行進にも関わらず、座られることなく、一人ひとりの選手たちを「立って」お迎えになったそのお姿に、世界中の人々が深い感銘を受けたといいます。
特筆すべきは、キューバ選手団が日の丸の小旗を振りながら入場したこと。
これは、オリンピック史上初の“他国の国旗を振っての入場”であり、有色人種の国が日本に寄せた敬意と感謝の証でした。
また、ガーナの選手たちは民族衣装で胸を張って入場し、
「有色人種の国が自らの文化を誇りとして出場する」
初めての瞬間を演出しました。
さらに感動的なのは、エチオピアのアベベ・ビキラ選手。
独立して間もない国の誇りを背負い、裸足でマラソンを走り抜け、金メダルを獲得しました。
「靴を買う余裕もないが、
人間としての尊厳は失っていない」。
彼の走りは、世界中に
「人間は肌の色ではなく、心で勝つ」
というメッセージを伝えました。
■ 日本が示した「ルールを守る強さ」
日本はこの大会で、金メダル16個、世界第3位の成績を収めました。
アメリカ、ソ連に次ぐ堂々たる結果です。
特に女子バレーボールの「東洋の魔女」チームは、回転レシーブで世界を驚かせ、柔道では初の正式種目として多くのメダルを獲得しました。
それ以上に重要なのは、日本人が「ルールを守る」という姿勢を世界に示したことです。
欧米のアマチュアスポーツ精神──“ルールを守ることこそ人間の証”──を、日本人は徹底して実践しました。
ずるをせず、誠実に競うこと。
その美しさが、日本選手団の姿に現れていたのです。
やがて、日本が勝つたびにルールを変えられる時代もありました。
バレーのネットが高くされたり、体操の採点基準が変わったり。
それでも日本人は、そのたびに努力で乗り越え、世界の頂点に返り咲いていきました。
その転機を作ったのが、のちに体操日本を復活させた岡野俊明先生です。
彼は選手たちにこう語りました。
「君が代を歌えるようになろう。
君たちは日本人だ。
先輩たちは、
民族と国家の誇りを背負って戦ったのだ」と。
この“誇りの教育”こそが、再び金メダルを生み出す原動力となったのです。
■ 「誇り」と「響き合い」が生む力
スポーツを通して見えるのは「誇り」と「響き合い」です。
人間は、自分のためだけでは本気になれません。
仲間のため、家族のため、国のためにこそ、心が震え、力が湧く。
それが日本人の生き方です。
戦後の混乱期を経て、日本人が再び立ち上がり、世界の人々と「人間として響き合った」瞬間――それこそが昭和39年の東京オリンピックでした。
会場に立ち上がった昭和天皇、
日の丸を振るキューバ選手、
裸足で走ったアベベ選手の姿。
それぞれが、人間の尊厳と希望を体現していました。
現代のオリンピックが商業化や政治利用の色を帯びる中で、原点に立ち返るならば、
あの東京大会こそが“真の平和の祭典”でした。
そこにあったのは「勝ち負け」ではなく、「響き合う心」。
日本という国が示した“誇りある人間の生き方”そのものであったのです。
■ 結び──未来への誓い
10月10日という日は、
昭和20年の政治犯釈放、
昭和42年の成田空港杭打ち開始など、
時代の節目とも重なります。
歴史の分岐点となってきたこの日。
その中心にいつもあるのは、「日本をどう導くか」という問いです。
だからこそ、いま改めて問いかけたいのです。
“日本は、再び世界に誇りを示す国であるか”。
東京オリンピックが教えてくれたのは、力ではなく、心で世界をつなぐ「響き合いの力」であったのです。
【所感】
先の大戦において、私達の先輩たちは「俺たちも人間なのだ」という「人間の証明」を見事に実現してみせてくださいました。このことがひとつの形として結実したのが、昭和39年の東京オリンピックであったのだと思います。そしてこのことは、肌の色や国の大小を超えて、「人間の尊厳とは何か」を行動で示した“人間の証明”でもありました。
では、後に続く私たちは、何を証明すべき世代なのでしょうか。
それは、おそらく、あの戦争で積み残された課題――
「人が人を支配する」という構造そのものの転換への挑戦にあるといえるのではないでしょうか。
力ではなく、心で響き合う世界へ。
競い合いの果てではなく、共に生かし合う道へ。
その文明の方向性を指し示すことこそ、私たちの世代に託された使命です。