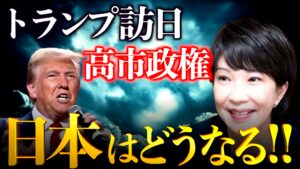放送では新チャンネル移行の裏話から、政治の本質、そして「手洗いの日」の教訓までを軽快に語りました。
手を清めることは、社会を正すこと。新しい時代を迎える倭塾の想いを込めた回です。
1.人生も配信も丸く生きることが大事
今朝の放送は、本来「新らしいサブ・チャンネル」から配信する予定でしたが、YouTube側の設定により24時間の承認待ちとなり、急きょ旧チャンネルからの配信となりました。
「やっと準備できた!」と思った矢先にストップがかかる――そんなバタバタ劇の中での、開始時間が少し遅れたライブでした。
丸い卵も 切りよで四角 ものも言いよで 角が立つ
有名な都々逸(どどいつ)ですが、どんなときも、角を立てずに丁寧に伝えることが大切かなと。
同じく都々逸に、
白だ黒だと けんかはおよし 白という字も 墨で書く
というのがありますが、なんと同じ内容の言葉がドイツの格言にもあるんです。
それが、
「白が黒だと喧嘩はよし、白という字も角で書く」
正しい・間違いを声高に言い合うよりも、白黒の間にある“根っこ”を見つめたいものです。
2.「手洗いの日」──家康の知恵と、清めの文化
10月15日は「世界手洗いの日(Global Handwashing Day)」。感染症予防のため、正しい手洗いを呼びかける国際的な日です。
徳川家康は関ヶ原の戦いで負傷した兵士たちに、「石鹸で傷口を洗え」と命じました。
当時、石鹸は高級品。
それを惜しまず兵士に配り、衛生管理を徹底した結果、感染症で亡くなる兵が激減したといいます。
ここで思い出すのが、「お清め」という日本文化。
手を水で清めるのは、ただの衛生行為ではなく、“心を正す祈りの動作”でもあります。
神社の手水舎(ちょうずしゃ)に始まり、食事の前の「いただきます」も同じ精神の延長線上にある・・・。
日本人は、生活に常に「お清め」を採り入れることで、心と体を整えてきました。
3.「手を洗う」とは社会を清めること
今日の手洗いの日は、政治の世界にも当てはまります。
汚れを洗い流すように、社会の中にも“清め”が必要。
自らを正せる人、自らの行いを省みる人こそが、これからの時代を支えていくのです。
足を洗えないなら、せめて手ぐらいは洗いなさい!なんてね。
政治家の中に「自国のために働く志」なんて露ほども持たず、外国勢力にすり寄る者が増えています。
「政治家は、どこの国のために働くのか」
このことを曖昧にしたままの政治では、日本の未来は守れません。
戦時中に焼け野原となった日本では、焼け跡からの復興に、戸籍や身分が自己申告で再構成されました。
このときだいぶ「背乗り」が横行しています。
本当の国籍を誤魔化し、戦後にいわゆる敗戦利得者となった人たちが、政界の半数を占めている時代。
いまこそ「純粋な日本人としての覚悟と倫理観」を取り戻す必要が生まれています。
4.新しい始まりに向けて──“手を清め、心を新たに”
手洗いは、手についたバイ菌を洗い流すためのものです。
2025年10月15日、手洗いの今日から、新しい時代が始まります。
新サブ・チャンネル開設も、そのひとつ。
なかなか思うように行かなくても、着実に変わっていく。
日本人が覚醒しつつあるいま、もう世の中は、まっとうな方向にしか進まないのです。
【所感】
新しいチャンネルへの移行作業に追われながら、ふと気づかされたのは、
「物事は思うようにいかないときほど、大切な気づきを運んでくれる」ということでした。
うまく進まないことも、流れが滞ることも、実は“立ち止まって整える”ための時間なのかもしれません。
丸い卵を無理に四角く切らず、角を立てずに受け止める。
そこに、日本人の柔らかい知恵が息づいているように思います。
また、「世界手洗いの日」という話題から、徳川家康の逸話に触れながら、人を清め、社会を清めるという視点にもつながりました。
手を洗うことは、身体だけでなく心を整えること。
それは、私たち一人ひとりがこの国のお清めの一部を担うということでもあります。
チャンネルの移行もまた、“新しい倭塾のはじまり”を象徴する出来事でした。
手を清め 心を新たに 扉を開く 倭塾かな
いまという時代の中で、どんな混乱も浄化に変えていける日本人でありたい――
そんな思いを、改めて胸に刻む朝となりました。