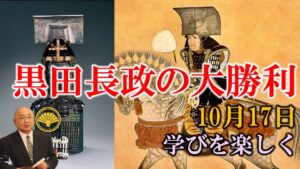世界の9人に1人が飢餓と言われる現実を踏まえ、戦後の支援の記憶と庶民の感覚を手がかりに、日本の食料10年備蓄構想を提案。技術と軍事の関係を見直し、未来の国防を考えます。
■ 世界食糧デーが映す現実――9人に1人の飢餓と国際機関の課題
10月16日は、FAO(国連食糧農業機関)の設立にちなむ世界食糧デーです。
各国でシンポジウムや展示が行われ、飢餓と貧困の解決が呼びかけられます。
ところが、現状は依然として「世界の9人に1人が食料難」とされます。
戦後直後から今日に至るまで、構造そのものは大きく変わっていない側面があり、国際機関の予算配分が本当に現場の飢餓解消に届いているのかという根本的問いが残ります。
一方で、日本では飽食の陰で健康問題が生まれ、豊かさの使い方そのものが問われています。
ここで重要なのは、どこか遠い紛争や災害の話としてではなく、「日本の食料安全保障」を自分ごととして捉え直す視点です。
食は命の基盤であり、ゆえに最大の国防でもあります。
■ 戦後の民間支援に学ぶ――対立を超える庶民のまなざし
戦後日本が食糧難に直面したとき、米国の民間から衣料や食料の寄付が多く届きました。
戦時のスローガンや敵意は、終われば人間どうしの共感に回復していく。
ここには、国家レベルの対立と、庶民の「一緒に生きよう」という素朴で力強い感覚の落差が見えてきます。
情報が対立を煽るときでも、日常を守りたいという庶民の願いは変わりません。
だからこそ、食糧問題は“誰かに任せる”のではなく、“自分たちの暮らしを守る営み”として積み上げる必要があります。
戦後に受けた恩を忘れず、いま困っている人を助ける力を蓄えておくこと――それが日本らしい国のあり方につながります。
■ 「食は最大の国防」――10年備蓄構想という現実解
提案の骨子は明快です。
① 安定供給先(たとえば米国等)から計画的に食料を購入、
② 国内で長期保存インフラを整備、
③ 国家として“10年分”の戦略備蓄を持つ、
という三本柱です。
備蓄食料10年分が確保できれば、海上封鎖や原材料価格の急変、国際的な物流混乱が起きても、人口規模を維持しながら立ち直る時間を稼げます。
さらに運用面では「回転備蓄(ローリングストック)」を徹底します。
毎年1年分を更新し、古い分は国内消費に回すか、国際支援へ振り向ける。
こうすれば備蓄は“眠る資産”ではなく、国内産業を支え、外交の選択肢を広げる“生きた資産”になります。
調達の相手国にとってもメリットは明瞭です。
長期の安定需要は農業生産を支え、サプライチェーン投資を呼び込みます。
日本は価格交渉力と技術支援力を持ち、相手は販路と資本を得る。
相互に利益のある「安全保障としての食の同盟」が成立します。
国内では、保存・物流・加工・検査の各工程で中小企業の裾野が広がり、地方の雇用を生みます。
コメや麦、豆類、畜産飼料、油脂原料、乳製品、非常用加工食品など、品目ごとの最適保存技術を組み合わせ、災害対応とも統合した“食のインフラ”を国策として整備することが肝要です。
■ 技術と軍事の距離――札幌時計台から現代ロボットまで
明治11年に竣工した札幌時計台は、もともと演武場(軍事訓練施設)に付随する時刻管理装置でした。
近代化の象徴はしばしば軍事目的と結びつき、技術の発展は安全保障と表裏一体で進みます。
現代に目を移せば、ロボットや半導体も同じ文脈に置かれがちです。
しかし日本には、軍事偏重ではない技術文化があります。
高性能チップを娯楽や福祉、教育へ向け、生活の喜びと安全を増す発想です。
技術の方向づけを「人間の尊厳」と「生活の質」に結びつけるなら、食の長期備蓄・品質管理・省エネ冷蔵・在庫最適化・非常時配送ドローンなど、平時・有事をまたぐ応用が無数に開けます。
このとき重要なのは、“見える国防”だけでなく、“見えない国防”を丁寧に磨くことです。
食料・水・エネルギー・情報――暮らしの基盤を強くすることが、長期の抑止力になります。
■ まとめ――「和」の国防と、共鳴を広げる教養
世界は分断を煽る言葉で溢れますが、庶民の願いはいつも同じです。家族を養い、子どもを育て、地域で助け合って生きたい。
だからこそ、食の安全保障は理念ではなく実務で積み上げるべき課題です。
10年分の食料備蓄の構想は、財政・倉庫・物流・品質・更新・国際支援の設計が鍵になります。
実務に落ちるほど、雇用と地域経済が温まり、外交の自由度が増し、非常時の耐性が高まります。
戦後に受けた善意へ応える道筋としても、最も誠実なかたちと言えるでしょう。
「技術は人のために」「食は国の礎に」。
和の知恵で足元を固めるとき、日本発の国防が世界の安心に波及します。
共震・共鳴・響き合い──その力で、次の世代の“当たり前の食卓”を守り抜いていくのです。
【所感】
世界はいま、大きな転換点にあります。
分断や恐怖で人々を動かす時代から、共震・共鳴・響き合いを基調とする新たな人類史へと舵が切られつつあります。
求められているのは、言い負かす技法ではなく、誠実な生き方が静かに伝わる「心の教育」です。
古事記に見える父祖の背中、沈黙の責任、連帯の覚悟――これらは日本にもともと備わってきた文化であり、次の文明を支える根幹の知恵です。
同時に、10月16日の世界食糧デーが映す現実は厳しく、食は命の基盤であると同時に最大の国防であることを思い出させます。
平時からの回転備蓄、長期保存技術の磨き上げ、地域の生産・流通との結節を強めることで、災禍や地政学的変動を越える力が養われます。
技術は軍事偏重ではなく、人の尊厳と生活の質を高めるために用いる――その方向づけこそ、和の国が世界に示せる道筋です。
言葉より行いで示すこと、
家族と共同体を支えること、
任せて信じ、失敗の責任を共に引き受けること。
その積み重ねが人の心を震わせ、共鳴の輪をひろげます。
背中から始まる文明の更新は、足もとから確かに進みます。
【倭塾の目指すもの】
学びを楽しみ、背中で示す人をふやすこと。
日々の挨拶・約束・仕事の誠実さという小さな実践を重ね、地域の助け合い、食の備え、技術と教養の結び直しを進めます。
仲間と共に「心に基づく教育」を現場につなげ、和の力を国内外へひろげていく。
それが倭塾の歩む道です。