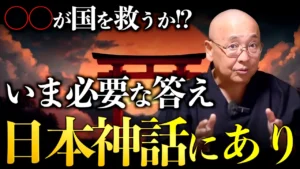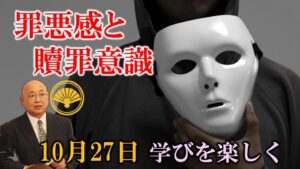須勢理毘売が夫・大国主の死を思いながらも、お葬式の支度を整える姿に、日本人の「凛とした悲しみ」が宿ります。悲しみに飲み込まれず、務めを果たす姿こそ、日本文化の根にある“美しい生”の形です。
1 古事記に描かれた「凛とした悲しみ」
古事記の中に、大国主(おおくにぬし)と須勢理毘売(すせりひめ)の物語があります。
八十神たちにいじめられた大国主が、須佐之男命(すさのおのみこと)のもとに身を寄せ、試練を受けながら成長していく物語です。須勢理毘売は、偉大な須佐之男命(すさのおのみこと)の愛娘です。
須佐之男命は、最初は「ふがいない男を娘の婿にできぬ」と怒ります。
しかし娘の愛の強さを知ると、大国主を鍛えるために、蛇の部屋・ムカデの部屋など、命の危険に満ちた試練を与えました。
このとき須勢理毘売は、自らの「比礼(ひれ)」を夫に授け、「これを振れば、蛇もムカデも退散する」と伝えています。
比礼そのものに魔力があったわけではありません。
それは「あなたを信じています」という妻の愛の象徴でした。
大国主は、その愛を胸に死の淵を乗り越え、見事に生き延びるのです。
こうして彼は、単なる「助けられる存在」から「守る存在」へと成長します。
夫婦の愛とは、相手を思いやる優しさだけでなく、互いに成長を促し合う厳しさでもある。
古事記のこの場面には、そうした人間の深い関係のあり方が描かれています。
2 泣きながらも務めを果たす──日本人の美徳
試練を乗り越えた後、大国主は火の試練にさらされました。
須佐之男命が放った鏑矢(かぶらや)を取りに行くと、草むら一帯が燃え上がり、逃げ場を失う。
そのとき、野鼠が現れて彼を助けるのです。
自らも火に包まれる危機にありながら、鼠は命をかけて彼を救う。
人間だけでなく、すべての生きものに「助け合う心」が宿っているという、古事記ならではの美しい世界観です。
物語の結末では、須勢理毘売が「不葬(ふり)の壷を嘆きながら持ってきた」と記されています。
「不葬(ふり)」とは葬儀、「壷」は葬具。
つまり彼女は、愛する夫の死を覚悟しながらも、涙をこらえ、葬儀の支度をしていたのです。
大切な人を失った悲しみの中でも、人は務めをしっかりと果していく。
それが古代から日本人が受け継いできた「凛とした悲しみ」の姿勢です。
お葬式では、家族が涙を流しながらも、参列者を迎え、食事を整え、儀式を進めます。
感情に押し流されず、役割を果たす。
その凛とした態度こそ、亡き人への最大の供養と考えられてきたのです。
「悲しみを抑えなさい」という教えではありません。
悲しみの中にあっても、姿勢を崩さないこと。
それが生者の務めであり、共同体の秩序を守る力でもあるからです。
3 悲しみを生きる力に変える文化
日本人の文学や武士道の中には、常にこの「凛とした悲しみ」が息づいてきました。
源氏物語の登場人物たちは、涙を隠して和歌に心を託しました。
戦国武将たちは、死を前にしても乱れることなく、最後まで筋を通して別れの言葉を残しました。
死を恐れず、悲しみを美しく整える文化が、日本にはありました。
現代では「悲しみを我慢する必要はない」と言われます。
もちろんそれも一理あります。
けれど、悲しみに溺れてしまえば、人は立ち直ることができません。
涙を流しながらも、自分の役割を果たす。
その行為そのものが、人を再び前へと歩ませてくれるのです。
人は悲しみによって成長します。
そして、悲しみの中でこそ、人の品格が問われます。
凛として悲しみを受け止め、姿勢を崩さずに務めを果たす。
そこにこそ、日本人が古代から伝えてきた“生き方の美”があるのだと思います。
最後に、西行法師の歌が紹介されました。
願わくは 花の下にて春死なん
その如月(きさらぎ)の 望月(もちつき)のころ
桜の花が舞う春の満月の夜に、静かに死にたいという歌です。
死を恐れず、美しい季節に身を委ねる。
西行が見せた静かな死の覚悟もまた、古事記に通じる日本人の精神です。
「悲しみを美しく整える」文化。
そこに、日本人の「美意識」と「責任感」と「愛情」が、三位一体となっています。
それは感情を否定することではなく、悲しみを「生きる力」に変えていく知恵です。
倭塾で学ぶ古事記は、まさにその日本人の心の原点を教えてくれます。
【所感】
古事記の物語に描かれる「凛とした悲しみ」は、感情を抑え込むことではなく、悲しみを通して生きる力を取り戻すための祈りのかたちなのだと思います。
須勢理毘売の姿にあるのは、涙をこらえる強さではなく、涙を抱いたまま役目を果たす覚悟です。
その姿勢こそ、時代を越えて日本人の美意識と魂の軸になってきたのではないでしょうか。
悲しみを恐れず、悲しみを生きる力へと変えていく「凛」という名の希望。
この日本の心を、これからも静かに、そして誇りをもって伝えていきたいと思います。