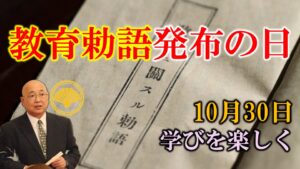10月31日は「ハロウィン」。ケルトの暦では一年の終わりであり、収穫への感謝が捧げられる大切な節目です。なぜ“前夜(Eve)”を祝うのか──。その素朴な疑問から、ケルトの感謝祭とキリスト教の万聖節の結びつき、さらに魔女像や言語の特徴にまで広がる物語をたどります。
同日に起きた出来事(韓国・慶州でのAPEC首脳会議、首里城火災、歴史的円高)を通して、日本が進むべき「自立」と「響き合い」の方向を考えます。
学びは楽しく、そして実践へ──倭塾の視点でお届けします。
Ⅰ.10月31日の三つの出来事──外交・文化・経済をつなぐ視点が要ります
10月31日には、時代の方向を映す出来事が重なります。
まず、2025年は韓国・慶州でアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議が開催されます。
周辺国との関係は、相手の動きに振り回されるのではなく、日本としての軸を定めることが大切だと考えます。改善に向けて対話を重ねるにせよ、必要な距離をとるにせよ、方針の根底に「自立」を据える発想が欠かせません。
次に、2019年の首里城火災です。
焼失は深い痛みをもたらしましたが、復元・展示の在り方を含め、文化をどの視座で伝えるかという問いを私たちに返しました。歴史の語りは時に政治性を帯びます。だからこそ史料に向き合い、地域の誇りを正確に共有する土台づくりが重要です。
そして2011年の歴史的円高(1ドル=75円31銭)です。
円高・円安の善悪ではなく、産業構造や購買力、家計の実感と整合する水準を見極める視野が求められます。輸出の短期的利益だけでなく、国内生産の持続性、価格の妥当性、生活の安定といった総合バランスを整えることが肝心です。三つの出来事は一見別領域ですが、いずれも「自立と設計」という共通課題でつながって見えてきます。
Ⅱ.ハロウィンの起源──ケルト暦の大晦日と「前夜(Eve)」の意味
ハロウィンは、アイルランドを中心に伝わるケルトの暦に由来するとされます。
新暦の10月31日は一年の終わり、いわば大晦日に当たり、かぼちゃを含む収穫への感謝が捧げられました。
のちにキリスト教圏の万聖節(All Hallows:11月1日)と結びつき、その前夜を祝う習慣が広がりました。
「Halloween」という語は “All Hallows’ Eve” の転訛と説明されます。
ところで、「どうして前夜を祝う」のでしょうか。
これは従来ほとんど論じられてこなかった視点ですが──
クリスマスも同じです。なぜか西洋では神様ごとに際して前夜を祝います。
これは実は、13世紀ころまでの世界地図が、「東」を上に書かれていたことと関係があります。
当時の地図は、世界の頂点が東であり、ユーラシア大陸の東の外れ、つまり世界の頂点に四方を海で囲まれた島があり、その島がHEAVEN(天国)とされていました。
そして陽は東から昇ります。
つまり東のHEAVENは、西欧よりも一日早く一日が始まる。
ですから神の祝日は、西洋の前夜に祝う、という形になったとも考えられるのです。
ハロウィンの「ジャック・オー・ランタン」「ほうきに乗る魔女」「黒猫」も、単なる怪談等は、ケルトの信仰に関係があります。
黒衣ととんがり帽子の“魔女像”は、実は薬草を調合して地域の健康を支えた女性の医療者像であり、それが恐怖の対象としての変形は、価値観の揺れを物語ります。
また、ケルト語の語順には独自性が見られます。
動詞を先に置き、その後に主語や目的語が来る語り方は、まずやるべきことを確かに行う労働倫理とも響き合って感じられます。
言語は世界観の鏡であり、ハロウィンの原型にある「感謝」「境界」「共同体」という核を読み解く手がかりになります。
Ⅲ.ケルトと縄文に学ぶ──自立する小さな共同体と“響き合い”の再構築
ケルト社会は、王国の強大さよりも、村落共同体の自立に支えられていました。
自給自足を基礎に、村と村がゆるやかに連携する構図は、日本の縄文文化とも通じます。
歴史の中で大きな権力の拡大に押されながらも、土地と暮らしに根ざす文化は深く残りました。
この視点から見ると、現代の選択肢は二項対立だけではありません。
支配か対立かではなく、「自立した者同士が結び直す」第三の道が見えてきます。
自立は孤立ではありません。
足もとを整えた者同士が、互いの不足を補い、季節や文化の違いを越えて協力することです。
ハロウィンの灯りは、その象徴として味わい深いものがあります。
暗闇の前で火を囲み、物語を語り、子どもたちが笑顔で歩く。
恐怖を煽る儀式ではなく、共同体を再接続する節目の行事として受けとめると、現代のコスプレ的受容にも、暮らしに返す意味を与えられます。
10月31日の三つの出来事を重ねて考えると、外交・文化・経済のそれぞれで必要なのは、事実に即して足で立つ「自立」と、違いを土台から結び直す「響き合い」です。
短期の損得に囚われず、長期の健全性(暮らし・誇り・生産)を整えることが、結果として日本全体の安定につながります。
倭塾が掲げる「学びを楽しく」は、知識を蓄えるだけで終わらせず、生活と地域に返して実践へつなぐ合言葉です。
ハロウィンの夜にともす小さな灯りのように、足もとから光を重ねていきます。
境界を越える合図は、笑顔と響き合いです。
今日もまた、心をあたためる学びを重ねてまいりましょう。
【所感】
ハロウィンの起源をたどると、単なる異国の仮装行事ではなく、人々が自然と共に生き、季節の境を祈りで越えてきた“心の文化”が見えてきます。
とりわけ「前夜(Eve)を祝う」という発想の奥に、東を聖なる方角とみなしてきた古代の時間観を重ねるとき、私たち日本人の「日の出の国」という自覚にも、深い意味が宿っていたのだと感じます。
ケルトと縄文──遠く離れた文明のあいだにも、共鳴する魂の記憶がありました。
力ではなく、感謝と祈りによって世界を結ぶ文化。
そして、それをもう一度、現代に取り戻すことが、これからの「共鳴の文明」への第一歩なのだと思います。
ハロウィンの灯りが、恐怖ではなく感謝と調和を照らす光でありますように。
そして、私たち一人ひとりの心にも、その灯りが優しくともり続けますように。