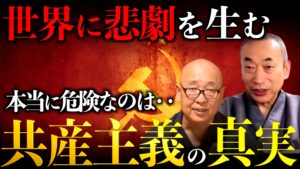1947(昭和22)年11月6日、結婚紹介誌『希望』が主催した集団お見合いが多摩川河畔で開かれ、戦後の混乱期に386人が将来の伴侶を探しました。
この出来事は、単なる出会いの場ではなく、日本の結婚観が「家を守る見合い」から「個人の愛を軸にする恋愛」へと大きく転換していく象徴でもあります。古代の通い婚から戦後の価値観の輸入、そして科学的知見までを横断し、いま求められる夫婦のかたち――“響き合う関係”を見つめ直します。
Ⅰ 多摩川の集団お見合いと、日本の「家」をつなぐ知恵
1947年11月6日に行われた「多摩川・集団お見合い」は、戦火で婚期を逃した20〜50代の男女386人が集まる大規模な催しでした。
会場で相手を探し、終了後に最大3名へ身上書を申し込む仕組みで、家を再建し次世代へ命と財をつなぐための、当時の切実な知恵が反映されています。
日本では近代以前、見合い結婚が一般的でした。
その背景には「家(いえ)」の存続という共同体の目的があり、妻が家政(家の運営と財産管理)の中心、夫が外で働き社会に貢献するという分業が機能していました。
これは支配・従属ではなく、性差の特性を踏まえた“共生構造”として理解されてきたものです。
時代を遡ると、古代には妻の実家に夫が通う「通い婚」も広く見られ、女性側が財や生活基盤を管理して家と村の経済を支えてきました。
『古事記』に描かれる大国主神話には、地域間で血を入れ替える「集団的な縁組」を想起させる場面があり、結婚が「恋愛の成就」だけでなく、ムラや家の持続性を担う社会制度であったことがうかがえます。
このように、見合いは「いのち」と「家」を社会全体でつなぐ仕組みでした。
結婚式の招待状が今も「○○家・○○家」と記す名残は、結婚を家と家の約束として見てきた文化の痕跡と言えます。
Ⅱ 戦後に広がった恋愛結婚――契約観とホルモンのリアリズム
戦後、日本社会にはアメリカ的価値観が流入し、「Love Marriage=当人同士の愛が最優先」という考えが急速に浸透しました。
背景には、キリスト教圏における「神の前で交わす永遠の契約」という婚姻観があり、個人の意志と契約が重視されます。
これに対し日本は、変化と循環を前提に“家と社会の調和”を優先する傾向が強く、婚姻観の土台が異なります。
恋愛は、人を強く引き寄せる一方で、脳内ではフェニルエチルアミン等の“恋愛ホルモン”のピークが概ね数年と言われます。
燃えるような情熱の段階から、助け合い・育て合いの段階へ移行できるかどうかが、長続きの分かれ道になります。
ここに見合い結婚の逆転の妙もあります。
見合いは出発点では恋愛ホルモンが過熱しにくいぶん、共に暮らし、役割を果たし、節目ごとに信頼が積み上がる過程で“あとから恋が育つ”ケースが少なくありません。
つまり、
恋愛結婚は「先に燃えて、その後に整える」、
見合い結婚は「先に整えて、あとから温まる」
という成り立ちの違いがあり、どちらにも長所と課題が存在します。
Ⅲ 良し悪しではなく選び方――“響き合うパートナーシップ”へ
見合いは社会の安定を、恋愛は個人の自由を、それぞれ強く支えます。
問題は二者択一ではなく、「どんな社会を育てたいか」「どんな家庭を築きたいか」という設計の問題です。
日本の伝統は、家政の知恵や地域の相互扶助を通じて「家・ムラ・国」をつないできました。
一方で現代は個人の尊厳と選択を重んじます。
両者を対立させるのではなく、次の三点で折り合いを付けることが鍵になります。
1.家政の復権:収入や支出の見える化、生活設計の合意、親族・地域との関係づくりを“家庭の基盤”として位置づけます。
2.役割の再設計:性差を固定せず、得手不得手で分担し、「外の仕事」と「内の運営」を互いに尊重します。
3.祈りと節目:年中行事や記念日を活かし、家の物語を育てる時間を意識的に作ります。
“響き合い”とは、恋も愛も家も社会も、相手を道具化せず、互いのいのちが調和する方向に手を伸ばす姿勢です。
見合いであれ恋愛であれ、燃える情熱を「支え合う日常」へ、支え合う日常を「感謝と歓びの物語」へと編み直す。
そこにこそ、これからの日本が世界へ示せる成熟があります。
1947年の多摩川の風景は、戦後の再出発を象徴しています。
いま改めて、伝統の知恵と現代の自由を結び合わせ、“響き合うパートナーシップ”を選び取ってまいります。