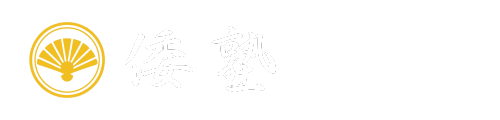古事記には、いまの常識では想像できないほど深い「見えない世界」の感性が込められています。
少名毘古那神が常世国へ去る場面を、単なる「神がどこかへ行ってしまった話」として読み流してきたのが、これまでの通説でした。
しかし本文に立ち返って丁寧に読み直してみると、そこには「見える世界」と「見えない世界」、そして「大自然」が響き合いながら国をつくるという、日本独自の政治観・文明観が浮かび上がってきます。
この記事では、ライブでお話しした内容とスライドをもとに、古事記の誤読を正しながら、「常世国(とこよのくに)」と「御諸山(みもろのやま)」に秘められた世界初クラスの新しい読み方を整理してお伝えしていきます。
1 チャンネル名変更と「歴史とは命の物語」という視点
これまで「倭塾チャンネル」として続けてきたYouTubeを、「小名木善行 歴史チャンネル」へと名称変更しました。
きっかけは、「倭塾という名前だけでは、何のチャンネルか初見の方には分かりにくい」という率直な指摘でした。もともと防衛問題の研究チャンネルとしてスタートし、その後「希望の日本再生チャンネル」、さらに「倭塾」と変遷してきた経緯がありますが、ここで改めて「歴史」を前面に打ち出すことにしました。
概要欄にも、
「歴史とは命の物語です。先人たちの祈りや志に触れ、忘れかけた日本人の優しさを思い出す時間を、皆さんと共に過ごしていきます」
という趣旨を書き添えさせていただきました。
歴史を、単なる年号暗記ではなく「いのちの物語」として受け取ること。
その視点から、見える世界と見えない世界の両方に目を向けていく。
それがこのチャンネルの方向性を示す言葉です。
また、デジタル情報はプラットフォームや企業の都合で一瞬にして消える危うさを抱えています。
だからこそ、古事記や日本書紀のように「紙に書かれたテキスト」が、千年単位で文化の土台を支えてきました。
今回のテーマである古事記の一節も、そうした「残された言葉」を手がかりに読み直していく試みです。
2 原文に立ち返ることの意味 ― 読み下しと現代語訳の「クセ」
倭塾サロンでは、毎週古事記を原文から読む勉強会を続けています。
古事記など、古い文献の読み方は、
1. 漢文原文で読む
2. 読み下し文に翻訳したものを読む
3. 現代語訳したものを読む
の3つのうち、多くが「現代語訳」したものから、意味を探るといった形で行われることが多いようです。
けれど、原文を読み下し文にする段階で、あるいは読み下し文を現代語に翻訳する段階で、それぞれ「翻訳した人の個性」がどうしても入り込みます。
読み下し文を作る段階で、どこで文を切るのか、どの助詞を補うのかといった判断に、すでに解釈が反映されますし、現代語に訳す段階でも、「こういう意味だろう」という先入観が入り込む。
結果として、原文とは意味の違う「解釈の物語」が独り歩きしてしまうことがあるわけです。
だからこそ、勉強会では古事記本文の漢字一文字ずつに向き合い、七五調で区切りながら原文を読み、そこから現代語訳を自分の手で立ち上げていく方法を採っています。
結構やっかいなことですが、やってみると、意外と楽しくてわかりやすい。
同じことは、日本書紀や万葉集にも当てはまります。
万葉仮名は「漢字を当てただけ」などと言われることがありますが、実際に原文を読むと、歌のイメージに最もふさわしい漢字を一本一本選び抜いていることがわかります。
こうした「原文に立ち返る読み」を古事記に対して行なうことで、少名毘古那神と常世国に関する、従来とはまったく違う世界が見えてきました。
3 少名毘古那神と常世国 ― 見える世界と見えない世界の「兄弟関係」
問題の箇所は、大国主神(大穴牟遅)が国づくりを進めていく場面です。
物知りの久延毘古を呼び出して、海の向こうから来た小さな神は誰かと問うと、久延毘古は「神産巣日神(かみむすひのかみ)の御子、少名毘古那(すくなびこな)の神です」と答えます。
ここで大国主は天上界に上り、神産巣日御祖命(かみむすびのみおやのみこと)に確かめます。
すると、
「この神は我が子であり、手の股からこぼれ落ちた奇しき子である。
だから葦原色許男命よ、お前が兄弟となり、ともに国を堅めてくれ」と告げられます。
こうして大国主と少名毘古那の二柱の神が、兄弟となり、相並んで国づくりを進めていくのですが、ある日、少名毘古那神は「常世国(とこよのくに)」に渡ってしまったと記されています。 
ここは従来、「少名毘古那がどこかへ行ってしまい、大国主は見捨てられた」という筋で解釈されることが多かった箇所です。
しかし、常世国とは「この世とつながる閉じた世界」、つまり見えない世界を指します。
神産巣日御祖命は、神々の中でも最初期に現れた「創造神」です。
創造神の命令は絶対です。
まして少彦名神は、その創造神の息子です。
そんな息子が、父であり創造神である神産巣日御祖命の命令に背いて逃げ出すのでしょうか。
ここはむしろ、神の御子である少名毘古那神が、見えない世界=常世国に入ることで、見える世界(葦原中国)を統括する大国主と、まさに「兄弟」となる・・・つまり見えない世界と見える世界が、ともに兄弟となることで、新たな大いなる国を形成しようとしたと解釈すると、筋がすっきり通るのです。
するとここから見えてくる構図は、
● 大国主神:見える世界(人の世)を担うリーダー
● 少名毘古那神:見えない世界(常世)を担当するリーダー
がともに兄弟として協働する構図です。
我が国では政治のことを「まつりごと」と言いますが、どうして現実政治なのに「まつりごと」と呼ばれるのかといえば、それは大国主神話以来の「政治は、見える世界と見えない世界の共同作業」であり、その両方が響き合ってはじめて「大いなる国の経営」が成り立つという理解に基づくと考えられるのです。
でも、実は、これだけでも足りないのです。
4 御諸山と大自然 ― 天・地・人が響き合う「大調和」としてのまつりごと
少名毘古那神が常世に去った後、大国主は「自分ひとりでどうすればこの国をよく作れるのか」と愁えます。そこへ、海を光らせてやってくる神が現れ、「自分を正しく祀るなら共に国をつくるが、さもなくば国は成就しない」と告げます。
大国主が「どう祀れば良いか」と問うと、その神は「倭の青々とした垣のように巡る東の山の上に祀れ」と答えます。
ここでいう山が御諸(みもろ)の山、すなわち自然そのものを御身体とする神の座です。
つまり古事記は、
● 見えない世界(常世国)
● 見える世界の人の世(大国主の政治)
● 大自然(御諸山という山体そのものの神)
この「天・人・地」の三位一体の「大調和」の構図を描いていることになります。
これは現代の、見えない世界を否定し、自然を単なる資源として削り、山を削ってソーラーパネルを並べるような発想とは、まったく逆の世界観です。
見えない世界に耳を澄まし、大自然に畏敬を抱き、人の世をその両方と響き合わせていく――それが古事記が示す「まつりごと」の姿であり、日本的な文明観の核です。
5 21世紀の「古事記再読」と共鳴文明への道
この「常世国=見えない世界」「御諸山=大自然」として読み直す解釈について、同様の解釈が過去にもあるか、AIに文献調査を依頼したところ、
● 体系的な先行例はほぼ見当たらない
● 折口信夫の「まれびと」論など、点として共鳴する思想はあるが、古事記本文から文明論としてここまで構造化した例はないという回答が返ってきました。
古事記を「見える世界と見えない世界の共震・共鳴の設計図」として読み直す試みは、21世紀の新しい「古事記再読の鼓動」と言えるのかもしれません。
倭塾サロンの古事記勉強会では、こうした読みを原文に即して一つひとつ確認しながら進めています。
見える世界だけでの閉じた合理主義だけではなく、見えない世界や大自然、そして人の心が響き合う「共鳴文明」のビジョンを、古事記から汲み上げていく作業です。
日本人は、もともと見えない世界を恐怖ではなく「共にあるもの」として受けとめ、自然・人・神が大調和する姿を理想としてきました。
その原点を思い出し、現代の政治や社会のあり方を見つめ直していくこと。
これこそが、古事記を学ぶ最大の意義であり、小名木善行歴史チャンネル(倭塾)が目指している歩みなのです。
【所感】
古事記を読み解くとき、私が大切にしているのは「これはこうだ」と決めつけることではありません。
権威や立場ではなく、原文そのものに内在する“理(ことわり)”を、どれだけ矛盾なく説明できるか。
偉い先生がこう言ったから、という「正当性」ではなく、普遍妥当性のある「論理性」こそが、もっとも真実に近いのだと思うのです。
だから私は、どんな権威の説であっても、
「なぜそう言えるのか」「論理はつながっているのか」を、必ず自分の中で問い直します。
その場では結論が出なかったり、理解が追いつかなかったことでも、急いで答えを求めず、何年も心の中であたためておく。
するとある日、まったく別の視点から、スッと腑に落ちる瞬間がやってきます。
原則はただひとつ。原文に沿い、文脈に沿い、物語として整合性のある説明ができること。
その積み重ねによって、今回の古事記の世界観――見える世界と見えない世界の調和という普遍の真理が、自然と浮かび上がってきました。
決めつけではなく、静かに理をたどる。
その先にこそ、心が納得し、魂が微笑むような「ほんとうの学び」があるのだと感じています。