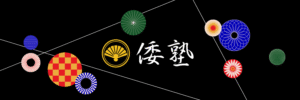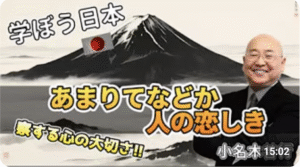世界で最も読まれている聖書の物語は、いまの地球をどこへ導いているのでしょうか。
今回の対談では、創世記の「エデンの園」と「善悪の知識の木」を入り口に、魔女狩りの歴史と、善悪二元論という思考のクセがいかに人間社会を地獄に変えてきたのかを、東郷潤先生と一緒に掘り下げました。そのうえで、日本人が育んできた「和をもって貴しとなす」という感覚から、聖書の物語をまったく別の角度で読み替え、人類が再び「エデンの園」を取り戻す道を探っています。
1 聖書の記述と魔女狩り──「責任」はどこにあるのか
対談の冒頭では、まず旧約聖書に書かれている、
「女呪術師を生かしておいてはならない」
「女霊媒師や女口寄せ師は石で打ち殺せ」といった厳しい文言が取り上げられました。
これらの記述は、ヨーロッパで何万人もの女性が犠牲になった「魔女狩り」を正当化する根拠として使われてきました。
おそろしいことに現代でも、アフリカなど一部地域では牧師が魔女狩りを煽動し、女性や子どもへの暴力が続いている現実があるそうです。
キリスト教の主流派は、
「これは旧約(=古い契約)であり、イエスの十字架によってすでに破棄された。
だから現代の教会には責任がない」
という説明もあります。
形式的には筋が通っているように見えます。
けれど、歴史的に魔女狩りが起きたのは「新約の時代」です。
聖書の影響が完全に無関係とは言い切れません。
ここで単純に「聖書が悪い」「キリスト教が悪い」と断じてしまうと、すぐに文明の衝突や宗教戦争の構図に陥ってしまう・・・というのが東郷先生の問題意識です。
善悪二元論に支配された社会では、「原因は聖書だ」と述べた瞬間に、「だからキリスト教は悪だ」「潰せ」という話に飛び火するからです。
これでは「新たな対立と憎しみ」を生むだけで、何の解決にもなりません。
そこで先生は、
「責任がある/ない」という善悪の裁き方ではなく、
「これは聖書の誤読が原因」という新たな視点を導入されています。
聖書そのものを否定するのではなく、あくまでも「読み方の誤りが悲劇を生んだ」と、整理の仕方を切り替えるのです。
こうすることで、対立を煽らずに、問題の根幹に踏み込む道を探られようとされています。
2 エデンの園を地獄に変えたのは誰か──善悪二元論という「心理トリック」
議論の核心は、創世記のごく最初に登場する「善悪の知識の木」の場面です。
神はエデンの園のすべての木の実を食べてよいとしながら、
「善悪の知識の木からだけは食べてはならぬ」とお命じになられました。
従来の一般的解釈では、アダムとイヴが蛇にそそのかされてこの実を食べたことで「神に背いた罪」を負い、人類は「原罪」を持つ存在になった、とされてきた場面です。
しかし、ここには大きな矛盾があります。
神は「全知全能」で「無限の愛」を持つ完璧かつ完全無欠の存在と規定されています。
そうであれば、何も知らない幼子のような人間の目の前に、あえて魅力的な実を置いておき、「食べるな」とだけ告げて目を離した神の側にも、責任があるように見えてしまうからです。
子どもの前にお菓子を置いておき、食べたら家から追い出す親がいたのなら、それは愛ではなく虐待です。
ここを転換するために東郷先生は、
「善悪の実」を、「人間が作り出した心理トリックの集合体」として読み替えます。
善悪二元論は、「あいつは悪だ」と決めた瞬間に、相手を攻撃することが正義になる、という思考の罠です。
自分をごまかし、相手を裁くためのトリックの寄せ集めが「善悪の実」であるのであれば、
神は、
「それを食べるな=その思考法を採用するな」と警告していたのだと解釈できるのです。
この読み方に立つと、
神は人間に怒って追い出したのではなく、
むしろ、
人間が善悪の心理トリックを得ることで、自分たちでエデンの園を地獄に変えた、という構図が浮かび上がります。
神は自由意志を尊重して黙って見守っただけであり、本来そこに深い愛しかないのです。
さらに重要なのは、「善悪の実は吐き出せる」という点です。
東郷先生自身、20年以上かけて「善悪でものごとを判断しない」訓練をされ続けてきたとのことでした。
言葉として「善」「悪」を使う場面でも、その背後にどんな心理トリックが潜み得るかを常に意識しているという話には、長年の葛藤と覚悟がにじみます。
人間は一度食べてしまった善悪の実を、もう一度自覚的に吐き出すことができる──ここに、エデンの園を再び取り戻す鍵があるのだと感じます。
3 日本人の「和」と世界の作り替え──誤読を正す役割
この「誤読を正す」という姿勢の背景には、日本人としての原体験も語られました。
第二次世界大戦での焼夷弾や原爆投下、その後も続く空爆や戦争への怒りから、「欧米への強い憤り」が心の奥底に溜まっていたこと。
その感情を直視したとき、「ここでキリスト教や西洋文明を悪と決めつけてしまっては、また同じ憎しみの連鎖を繰り返すだけだ」と気づいたこと。
そこから、「怒りを抑え、相手を肯定する根拠を探す」という、長い内的な戦いが始まったというエピソードは、とても印象的です。
そのとき支えになったのが、日本の「和をもって貴しとなす」という価値観です。
善悪で裁き合うのではなく、
「和」を軸に関係をつくり直していく。
この文化を本気で信じるのなら、聖書やキリスト教も「悪」と切り捨てるのではなく、「誤読」として捉え直し、誤読をほどいていく方向で努力しなければならない。
そこに、日本人としての誇りがあります。
創世記の物語を通じて今回は、
「神の第一の命令は『善悪の実を食べるな』であり、
人類はそれを無視し続けている」
という視点からの読み替えが紹介されました。
このように読み替えることで、聖書全体の意味が180度変わってきます。
エデンの園を、善か悪かという二者択一、
しかも悪と決めたらどこまでもその悪を攻撃して良いとする身勝手によって、
神が作った楽園を地獄に変えたのが人間自身であるなら、
善悪の実を手放すこともまた、人間にできることです。
つまり、再び楽園を取り戻す鍵は、人間の手の中にあるのです。
【所感】
「人が作った地獄なら、人の手で楽園に戻せる」──ここに最大の希望があります。
この末尾の一節は、今回の対談の中でも、もっとも深く、もっとも未来へ開くメッセージだと思います。
エデンの園を失わせたのが、
神の罰ではなく、
人間が「自分でつくり出した善悪という心理トリック」なら、
それは同時に、
「人間が自分で直せる」
という意味だからです。
この視点は、とても日本的で、とても優しい哲学でもあると感じました。
人はときに、自分で壊したものを「神のせい」「運命のせい」「誰かのせい」と外へ押し出しがちです。
けれど、
「人の手で壊したものは、人の手で治せる。
だから、人の世に絶望はないのです。
再び楽園を取り戻す鍵は、人間の手の中にあります。
これは、希望であると同時に、責任の宣言でもあります。
その責任は、重荷ではなく、むしろ人間への信頼と可能性に満ちた責任です。
● 神に依存するのではなく
● 誰かを責めるのでもなく
● 自分たちの手で世界を作り替えていく
そんな未来を見据えた、大人としての責任です。
これは、日本文化の根幹にある、知らすの思想や、和の文化と完全に共鳴する思考です。
神は裁かない。
人間同士の、善悪の裁き合いが、世界を地獄に変えてきたのです。
この構造を手放すことで、世界は自然に和へと還ることができます。
人は、本当はもっと優しい生き物です。
それがこの最後のメッセージで、静かに花開いているように感じました。
● 善悪二元論も、人間の恐れが生んだもの
● ならば、恐れを手放せば、響き合いが戻る
● 世界を壊したのが人間なら、世界を癒すのも人間
これは、決して大きな視野ではありません。
一人ひとりの心の手のひらに乗る小さな理解であり、優しさです。
「神が罰した」のではなく、
「人が心理トリックを採用して世界を地獄化した」のなら、
「楽園」を取り戻す力も、人の手の中にあるのです。
これは宗教を超えて、文化を超えて、人類すべてにとっての希望の言葉です。
そして何より、我々日本人の、普遍の祈りであり、思想であり、人生であるのだと思います。